
WALLA|Artpoint Radio 東京を歩く#8
執筆者 : 屋宜初音
2025.03.19

「Artpoint Radio 東京を歩く」では、都内にあるさまざまな拠点を訪ね、その運営にかかわっている方にインタビューを行い、その様子をラジオとレポート記事の2つの形式でお届けします。
拠点によって、その業態や運営の手法、目指す風景はさまざま。そうした数多くのまちなかにある風景には、運営者たちの社会への眼差しが映し出されているのではないでしょうか。
本シリーズでは、拠点の運営にかかわるひとびとの言葉から、東京の現在の姿をともに考えていきます。
――
第6回は品川区にある「コウシンキョク-交新局」を訪ねました。JR西大井駅から徒歩10分、東京駅からも新宿駅からも電車に乗って15分ほどで到着する、アクセスのいいエリアです。駅前は開発が進んでいる一方、高架下をくぐり路地に入ると昔ながらの商店や民家、公園が点在しています。

今回は彫刻家でもあり、コウシンキョク-交新局(以下:コウシンキョク)の局長でもある平山匠(ひらやま たくみ)さんにお話を伺いました。コウシンキョクは、平山さん自身がアトリエとして活用しているほか、展示をしたり、粘土で誰でも何をつくってもいいという「トウゲイ・コウシン・基地」を定期的に開催したりしているそうです。平山さんの制作への姿勢のお話から、「トウゲイ・コウシン・基地」に至ったいきさつ、そこで繰り広げられている光景についてお聞きしました。
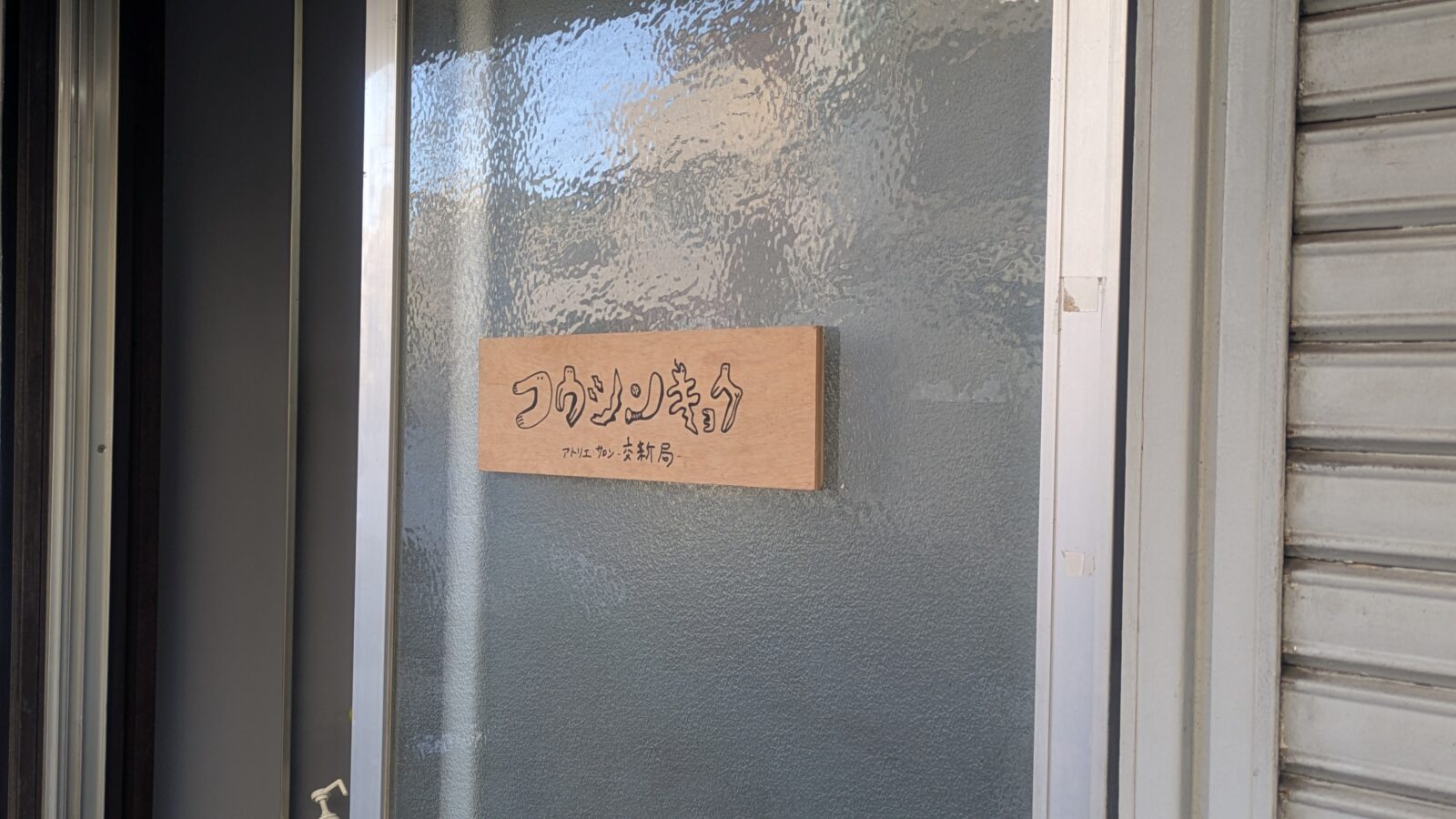
平山:1年以上物件探しをしていて、やっと見つけたのがこの物件だったんです。家から近いし家賃も一人でギリギリ払える。しかも1階で間口が広い。大きい作品をつくると、車を横に停めて搬入出をする必要があったので、ここがベストだと思って、即決でしたね。
平山:コウシンキョクとして正式にオープンしたのは2021年の8月ですが、その前からこの場所はアトリエとして借りていました。大学院の卒業制作をしなきゃいけない時期が、ちょうどコロナ禍だったんですが、大学の設備を使うことに制限がかかっていたんです。僕はそのとき、友達と3人で別にアトリエを借りていたんですが、距離の問題とか、いろいろあって、一人のアトリエが 欲しいと思ったのが、場所をもつきっかけでしたね。

平山:そうですね、曳舟・押上エリアか、このあたりで考えていました。 もともとこのあたりは地元なんです。便利だし、アートスペースがあまりないので、 それが逆にいいなと思って。周りにアートスペースがいっぱいあるところって、何か暗黙のルールだったり、そういう雰囲気がなんとなくある気がしたので、そうではない何もないところでスタートするのが面白いなと思ってここに決めました。
平山:とにかくつくる場所にしたかったのと、あとは展示やトークイベントとか、バーイベントのようなみんなで集まって飲む、みたいな使い方ができればいいなと思っていました。でも、まさか陶芸教室をひらくとは思っていませんでしたね(笑)
平山:そうですね。自分がいいなと思っている作家をピックアップして、どういう内容にするのかを一緒に考えながら展示をつくりたいと当初から思っていました。それに、使いたい人がいれば、レンタルスペース的な感じでもいいかなとも。そこは柔軟にできればいいなと考えていましたね。
平山:どちらでもしっくりきてますね。 作家としての僕が運営している場所だし、これといってやっていることが決まっているわけでもないので、どちらも事実だと思います。だけど、もし呼び方を決めてほしいと言われると、公民館かな。 誰が来てもいい場所でありたいというか。
平山:陶芸教室的なことをやりはじめて1年半くらいが経ちました。はじめたころは、ちょうど自分の展示のための制作をしていた時期だったんですが、1人で作品をつくるのに飽きてきてもいたんです。もともと、ここは自分の作品制作のための窯があるし、それならほかにも粘土を触りたい人いないかな、ものをつくっているときに、話し相手がいたら面白いかなぐらいの感覚で、SNSで「自分のアトリエに窯があって、焼けるんですけど、一緒に粘土で何かつくりたい人いませんか」って投稿してみたんです。そしたら40人くらいから連絡が来たんですよ(笑)

平山:これは需要があると確信して、それからいまの活動をはじめました。きちんとした陶芸教室っていうと器をつくらないといけなかったり、敷居というか、ルールみたいなものがあるじゃないですか。それは好きじゃないけど、陶芸はやってみたいっていう人が多かったんじゃないかなと思います。
平山:この活動は「トウゲイ・コウシン・基地」という名前にしています。陶芸的なことをやりながらみんなで時間を共有しよう、みたいな感じですね。教室っていうと、先生と生徒みたいな関係が生まれるじゃないですか。それってある種、上下関係とか、教える側と教えられる側っていう、固定的な立場が生まれる気がしていて、それが嫌で。だからもっとフラットに、メンバーと僕がいるみたいな、そんな感じにしています。
平山:そもそも自分の作品のテーマにも繋がっている話なんですよね。僕の兄は障害を持っていて絵描きなんですけど、僕は兄と粘土で遊んだっていうところが美術をはじめたスタート地点になっています。おそらく、その時間じゃないとできなかったコミュニケーションがあったと感じていて。その経験をもとに、4年前に兄と一緒に、《モンスター大戦記ハカイオウ》という作品をつくりました。それは僕と兄が昔のような関係性に立ち返って、一緒にコミュニケーションをとりながら、兄の絵を僕が立体化するっていう作品です。その制作の中で、理解を求める対象は、兄だけじゃないなと思ったんです。

平山:そもそも障害という概念自体がすごく抽象的だし、障害のあるなしに関係なく、人を理解することってそもそもなんだろうって思って。それをテーマにいろんなチームや形式で作品をつくってきています。そして、そのひとつとして場所をもとうと思いました。その場所にいろんなステータスの人たちが流動的に入ってきて、お互いにコミュニケーションをとって、また新しい人が入ってきて……それを繰り返すみたいな、そういう場所があったらいいなと思ったんです。新しいものを供給する「郵便局」のようなサイズの場所っていうことで「コウシンキョク–交新局」という名前にしました。コウシンって意味も、アップデート(更新)だったりとか、マーチ(行進)だったりとか、何かと交信するとか、いろんな意味があるのがいいなと思っています。
平山:作品制作のほかに、トークイベントに呼んでいただいたり、あとは定期的にアートセラピーの仕事もしていますね。足立病院という、戦後からデイケアという通院型のアートセラピーを続けている病院があって。そこで何十年もアートセラピーを担当されていた先生が退任されるということで、僕に白羽の矢が立ったみたいです。基本的に通院している方々が来るんですけど、何かを教えるとかじゃなくて、そこに来てある種の社会参加として、話をすることだとか、自分を開示することとか、そういうことがメインになっています。なので、何かを完成させるというよりは、その場の時間を共有することが第一の目標で。圧迫するようなアプローチはせずに、コミュニケーションをとることを意識していますね。
ずっと美大にいると、やっぱり美大の中の価値感とか、そういう基準でいろいろ考えてしまうことが多いんですけど、病院で仕事をしていると、病院の中で初めて絵を描いたという人とか、絵に興味があったけど小学校ぶりに描きはじめたみたいな人がいたりして。そんな人たちと一緒につくる状況、美術のあり方がすごく面白いですね。アートってどういうことなのか、何かをつくるってことってどういう行為なのかっていうことを、いろんな角度で考えられる仕事です。
平山:もともと幼少期から、粘土で何かをつくるのが好きだったんです。それで高校生になって、進路をどうするのかを決めるときに、もうこれしかないんじゃないかって気持ちで、粘土で何かをつくれる学科を探しました。陶芸科も考えたんですが、陶芸科だと器をつくったりとか、緻密な作業をやらないといけないけれど、別に器がつくりたいわけでもないしなあと。そういう理由で東京造形大学の彫刻専攻に進みましたね。
平山 :彫刻家とは言っているんですけど、でもなんだか最近わからなくなってきました。彫刻っていうと、削ったりするイメージがあるじゃないですか。でも僕は削ってないしな、と思って。彫刻家ですと話すと、「木とか、石ですか?」と聞かれて、「いや、粘土です」って答えることが多いんですよ。だったらもう、肩書きをアーティストとか粘土彫刻家とか、彫塑家とか、そういう感じに変えようかなって。ちょうど3日前くらいにそれを考えていましたね。

平山:そうですね。もう粘土でいこうって決めて、ここ5年ぐらいはやっています。自分の手を使って何かのかたちになれる。寄り添えるというか、そういうメディアだなと思っているので。
ただ、粘土の使い方は少しずつ変わってきました。いままでは粘土を焼いたり、石粉粘土を使って塗装をしたりしていたんですが、最近発表した《ハニラ》という作品では粘土を焼かずに生のまま使ってみたり、だんだん粘土側に視点が寄ってきたというか。これまでは粘土をツールとして捉えていたんだけど、ツールとして使われていた粘土はどういう気持ちなんだっていう視点になってきました。粘土サイドに自分が入ってきちゃったっていうか、僕から寄り添いはじめちゃって。《ハニラ》は 東京駅のそばにある「BUG」というスペースで展示させていただいたんですけど、そのときは、粘土が乾いて作品が崩れないように 、日々水をかけ続けるっていうパフォーマンスをして。《ハニラ》で使った粘土は再び倉庫に持ち帰っていて、今後はその粘土を使ってまた作品をつくるというプロジェクトにしようと思っています。

平山:この場所を運営して維持させるためには、お金がないとやっぱり難しいじゃないですか。 だからここを維持させるためにはどうすればいいのかっていう、すごく現実的なところで苦戦しています。そういう点で考えると、いろいろ変わったのかもしれません。月々いくら払わないといけない……と考えると、バイトだけじゃ無理だなとか、作品収入があったとしても……みたいにいろいろ考えることがあります。でも、もう無理かもしれないって思ったときに、タイミング良くお金が入ることがあったり、本当に水切りみたいな状態で続いている感覚もありますね。それでも、最初は助成金の申請もできなかったけど、いまでは申請するようになったし、どうすれば続けられるのかを意識して考えていますね。
平山:作品なんじゃないですかね、ある意味。自分にとってもすごく実験の場でもあるので。
平山:そうです。誰かがやってきて、僕と交流して、来た人同士も交流して、新しいものを自分のなかに取り込んで、アップデートして、また歩んでいくみたいな、そういう感じですね。その場所に自分がポンって居たらおもしろいな、みたいな。
アトリエを持った当時、コレクティブっていう概念もすごく流行っていて、それこそシェアアトリエとか何人かで場所を運営している友達が多かったんですけど、うまくいってないところも多くて。何人かで運営しようとすると、どこかにピラミッドの上下構造ができてしまうというか、リーダーがいてそれをサポートする人っていう関係によって、搾取構造が成立しちゃうんじゃないかって、客観的に見ていて思ったんです。僕もシェアアトリエをやっていたから、その実感がありましたし、それは健康的じゃないなと思っていました。どうすれば健康的な状態で場所を続けられるのかと考えたときに、人は流動的に変わり続けた方がいいんじゃないかって思ったんです。
来る者拒まず去る者追わずみたいな状態が、水みたいだし、雲みたいでいいなって。それが自然なことだし健康的なことだなって思いました。スタジオとしての利用だけでこの場所を借りるのも勿体ないし、僕がある程度まで場を用意しておいて、あとは来た人や成り行きに任せる、そういう場所があったらおもしろいというスタンスで運営しています。
平山:いまは粘土1キロ1000円で渡していて、ただ触るだけの人もいれば、一生懸命にすぐつくる人もいますね。 あとは展示に備えて陶芸の作品をつくりたいっていう作家さんも多いです。僕は来た人に粘土を渡して、後はわからないことがあったら声をかけてください、くらいの居方でいます。 こういうのがつくりたいんだけどつくり方がわからないっていう場合は、僕がサポートしたりとか、それくらいの感じです。

平山:つくっているものは、本当にそれぞれです。アザラシをつくっているイラストレーターの方がいたり、ピアスをつくっている方がいたり。あとは、背中をつくっている方もいます。たまたま満員電車の中で背中合わせになったスペイン人と思われる男性の背中が、すごくいい背中だったらしくて、そういうものに影響を受けてつくっている人もいますね。
平山:そう、交流するっていうのを前提にしていなくて、粘土で何かをつくるということをメインにしているんです。その状態での交流って何かリラックスできるんですよね。話をすることをメインにすると、話をしなきゃって注力しちゃうから、逆に話せなかったりもするんですけど、別の目的があった方がみんな話せることが多くて。そんな感じでゆるゆると恋愛相談とか、老後の話とか、どうしようかなとか、いろんな話をしています。
いざはじめてみたら、たくさんの人が来るようになりましたね。一度来た人がまた別の人を呼んでっていうふうに、どんどん人が増えていきました。たまたまここに集まった別の界隈の人同士が、友達になったりすることも。みんなが粘土を触りながら交信、交流しているのを、僕はこの席でただ座って見ているみたいな、いまはそういう状況です。
平山:展示のときには、僕の知り合いと、展示している人の知り合いが来て、ここで交流したり、飲み会をひらいたら来た人同士が繋がったりという形式はありましたね。でもいまのペースほど、サイクルが早いわけじゃなかったです。なので、最近はよりコウシンの機会が増えて、僕の目指していた光景により近い状態になってきたな、と思います。

平山:ここではじめて展示をしたときに来てくれたこどもがいて、それを機にその少年とお母さんと交流が進んで、いまその子は中学生になりましたね。もう4年くらいの付き合いで、いまだに学校帰りとか、ここの扉をガラガラって開けて、「こんにちは~」って入ってきて5分くらい喋って帰るみたいな感じです。あと犬を散歩している元バンドマンの方とか、お祭り好きのおじいちゃんとか、カードゲーム好きのお兄さんとか、地元のレギュラーメンバーがいますね。
飲食店と比べると、どうしてもここはなんかよくわかんない場所だなと見られることが多いし、そんなに親しみがある業態ではないと思います。だけど時間とともに、話す人は少しずつ増えていっていますね。
平山 : 美術の業界ってとにかく狭いし、 あまりひらかれてないじゃないですか。だから、普段はお互いに話す機会がそんなにないと思うんですよ。人生の経験の中で美術を経由してこなかった地元の人も多いので、そういう人と、ここに来る作家の人が交流する場にもなっているのはすごく面白いなと思っています。そういう点では、この場所の意味をすごく意識しながらやれているのかなと思います。 公民館じゃないけど、誰が行ってもいいような場、それは本当に意識してやっていますね。敷居みたいなものがすごく強くある業界だからこそ、そうじゃない、 ある種のセーフティゾーンのような場所でありたいなと思っています。
平山:オルタナティブスペースって、なかなかアクセスしづらい場所も多い気がしていて。自分が場所をやるのであれば絶対にそうはしたくなかったんです。1階にあって、誰でもふらっと入れるかどうかで、場の雰囲気がすごく変わってくるので。そうして地元の人とここに来ている人が交流する場になるのはすごく楽しいですね。
実はいま、透明な入口の扉をつくっていて、外から内側が全部見えるようにしようと準備しています。あとは、いまはひとまず看板を仮設しているんですけど、明かりの灯る看板をつくろうとしていて。より入りやすくするための工夫を増やしたいなと思っています。
平山:最近は、みんなが来たときに自分の力を供給しすぎていて。毎回違うメンバーがバーッと来て、時間を共有して帰って……というのを繰り返しているので、むしろ一人でいる時間が貴重になってきていますね。 だから夜の一人の時間もめっちゃ楽しいです(笑)

平山:現状維持ですね。現状維持ができるのって逆にすごいから、それができれば何でもできるんじゃないかなと。あとは、ちょっと手狭だなと思うときがあるので、もっと広い場所があると良いなと思っています。
平山:あまりないですね。やっぱり一人でやっているので、どうしても限界がありますし。一方で、最近はここをひらいていると、自分の感覚や考え方を他者と共有する時間も長くなってきて、そうすると、この人と自分はとても目線が近いな、と思える人も出てくるわけですよ。そのときに、この人とだったら一緒に場所をやってもいいのかな、みたいな気にもなってきていて。もしかしたら今後、この場所を何人かでやる形式に変化していく可能性はあるかもしれません。
平山:兄と一緒に作品をつくったときに、これは僕だけではこんな考え方にはならないな、という気づきがあったんです。僕の作品でもあるんですけど、作品のなかに兄の絵があって。兄のことをより理解する行為を進めていく中で、その人が考えていることのおもしろさと対峙することになるんですよね。そのときに。自分自身にとっても物事を解釈する量が増えていくような感覚があって。

平山:そのおもしろさが自分の制作にも生きていくから、いろんな形式をつかって「他者のおもしろさ」と対峙することを続けているんだろうなって思っています。たとえば昨年の2月もオーストラリアのアーティストがここで滞在制作をして、二人で展示をしたんですけど、そのアーティストも自分にないものを持っていたり、あるいは共通点をすごく見つけられたりするんです。人と何かをやる、ただ一緒に時間を共有するだけじゃなくて、創作を介して共有することによって見えてくる景色が変化していくのが、すごく面白いんです。その量が増えていけば増えていくほど、自分がおもしろいって思えるポイントの手札が増えていくわけですよ。
平山:その人のステータスの見え方、たとえば年齢とか性別とか国籍とか、特性とか、一人ひとりの持っているステータスがやっぱりより見えやすく、増えていきますよね。そうするとコミュニケーションの仕方もどんどん変わってくる。この人にはこういうコミュニケーションの仕方がいいんじゃないかっていう、選ぶ言葉とか、交わすコミュニケーションの量とか。
平山:そうですね。スペイン人の背中の温もりや筋肉質なのがすごい良かったっていう話も、それを作品化する視点があるのって面白いなとか、この人はこんなこと考えて、こういうものをつくっているんだっていうスタートを見ているわけじゃないですか。展示と違って、相談も含めていろんな話をしながらつくっていくことは、一人で作品をつくって発表する、発表されたものをただ見るということとはまた違う体験なので、あらためて何かをつくるということを考え直す場になっているんです。

――
インタビューをしている途中、話題にあがっていた常連の中学生がやってきました。ガラガラと扉を開け、何の戸惑いもなく部屋に入り、授業でつくったという木箱を手に平山さんと話しはじめました。すごい綺麗に釘打ったね、ここだけ寄木にしたんだ、と会話を5分ほど重ねて、じゃあ、と言って帰っていきました。思いがけず居合わせた、自然なコウシンの風景。わたしたちを含めて、ここに訪れる人々やコウシンキョクにとって、なんらかのコウシンがいまも続いているのかもしれません。
――
コウシンキョク-交新局
住所:東京都品川区二葉4丁目11−13 サンハイツ大竹102
アクセス:都営浅草線中延駅から徒歩8分、JR横須賀・総武快速線・湘南新宿ライン・埼京線西大井駅から徒歩10分
公式ウェブサイト:http://takumi-hirayama.site/space.html
話し手:平山匠
聞き手:櫻井駿介、小山冴子、屋宜初音
執筆:屋宜初音
編集:櫻井駿介、小山冴子

執筆者 : 屋宜初音
2025.03.19

執筆者 : 屋宜初音
2025.03.19

執筆者 : 屋宜初音
2025.02.20

執筆者 : 屋宜初音
2025.01.30

執筆者 : 屋宜初音
2025.01.30

執筆者 : 屋宜初音
2024.12.26

執筆者 : 屋宜初音
2024.12.26