共通: 年度: 2017
まちにアートは必要か?/アーティストの見ている世界を信じる(APM#03 後編)
ART POINT MEETING #03 –まちで企む- レポート後編
ART POINT MEETING、第3回のテーマは「まちで企む」。八王子市議会議員を務めながら同市で空きテナントの活用プロジェクト「AKITEN」を運営する及川賢一さん、足立区で「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」の事務局長を務める吉田武司さん、JR中央線の高円寺から国分寺間を舞台に「TERATOTERA」を展開してきた小川希さんと、東京の各所で存在感のあるプロジェクトを仕掛けている3人のプロジェクトリーダーが登場しました。
後半のレポートは小川希さんのセッションからスタート。これまでの回にも増して、アートとまちの関係についての各人の考え方の違いが浮かび上がり、聞き手も巻き込んだ活発な議論が起こった今回のART POINT MEETING。はたして彼らは、何を目指してまちにアートを投げ入れ、その実現のためにどんな工夫をしているのでしょうか? ライターの杉原環樹がレポートします。
>>レポート前編
アーティストの見ている世界を信じる
「まちにアートは必要か?」。そんな根源的なテーマのトークで最後に登場したのは、小川希さんです。2008年、吉祥寺に芸術総合施設「Art Center Ongoing」を立ち上げた小川さんは、翌年より中央線沿線を舞台にしたプロジェクト「TERATOTERA」を開始しました。さきほどの問いは、「さまざまな市民活動があるなかで、なぜアートに関わるのか」と、プロジェクトを進めながら繰り返し考えてきた問いだと話します。

美術大学で教鞭も執る小川さん。毎年、その最後の授業では、「アートが社会に必要だと仮定して、それを証明せよ」という課題を学生に出しています。すると、そこで学生たちが返してくるのは、「社会の一員である私にはアートが必要だから」、「アートがないと効率ばかりの社会になってしまうから」など、数パターンに分類できる答え。
「最近ではそこに、『アートは多様性を担保するから』という、流行りの言葉も加わりました。でも僕は、こうした答えに疑いがあるんです。はたしてアートは、本当にそんな風に機能しているのかと。2016年の『TERATOTERA祭り』では、『involve(巻き込む)』をテーマに、価値観の異なる他者とアートの関係性を考えようとしました」。
イベントにあたり、小川さんは趣旨を書いたステートメントを執筆。そこには、昨今の世界や日本における政治的・社会的な動向を前に他者との理解が「簡単ではない」とわかったこと、しかしそれでも、他者と無関係に生きることはできないことなどが切々と書かれています。そして小川さんは、参加アーティストたちに「観客を自らの作品に何らかの形で巻き込んでほしい」と伝えました。
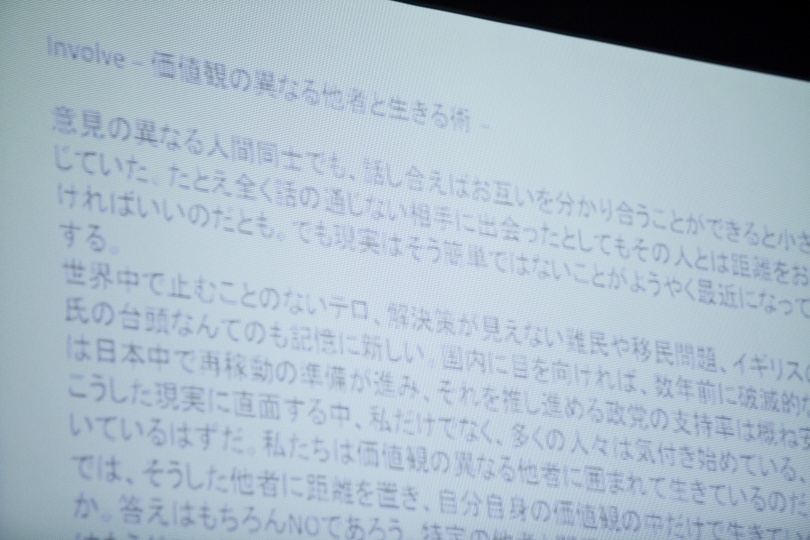
では、それに対してアーティストはどんな表現を出してきたのか。ある作家は、アーティストがホストとして店を開き、訪問客にアートの必要性をひたすら説く作品を、また別の作家は、ある観客の情報が書かかれた風船をほかの観客に渡し、その人を探してもらう作品を発表。河童の姿でまちに出没するパフォーマンスをした作家もいました。
「すごく大上段な真面目なステートメントを書いたのに、それを吹き飛ばすような表現が出てきたなと(笑)。でも、それがとても良かったんです。多様性の担保どころではなくて、自分が考えていた価値観を壊して、スイッチを変えてくれるのがアートだと感じることができた。僕はアーティストという存在の特殊性を信じているんです」。


普段から様々なアーティストと関わっていると、作品の持つ力を信じざるを得ない気持ちになる、と小川さんは話します。10人の作り手と「Ongoing Collective」として参加する「奥能登国際芸術祭2017」の視察でも、地元の人たちのアーティストを見る目が、制作する作品を見せることで変わりました。
「近年ではコンテクスト重視の作品や、具体的に社会の課題の解決を目指す『ソーシャリー・エンゲイジド・アート』の動きも盛んです。その意義は理解した上で、それでも僕は分類できない、根本的に価値観を変えてくれる作り手や作品と付き合いたい。そうした表現は、変化を望まない人も多いまちという場所のなかでは劇薬にもなり得るかもしれないですが、それだけ力がある作品だからこそ可能性の種にもなると思うんです」。
アーティストという特殊な存在。その特殊性をわかりやすく理解するのではなく、複雑さを残したまままちに入れてみること。小川さんの話したアートとまちの関わりは、ある意味、登場した3人のなかでもっとも抽象的なものです。しかしそこからは、あくまでアーティストという個人に向き合おうとする小川さんの姿勢が感じられました。

それぞれの問い、それぞれのアートプロジェクト
3人のプレゼンのあとは、客席の参加者も交えたフロアディスカッションが行われました。「アートプロジェクト」と括られる取り組みの幅広さを前に、会場からは細部についての疑問以上に、「アートとデザインの境界が曖昧では?」、「アートプロジェクトとただのイベントの違いとは?」など、活動の根幹を問うような質問が相次ぎました。
ここでもまた、3人の考え方の違いが浮き彫りに。「解決すべき『問題』とは誰が設定するのか?」との質問に対して吉田さんは、「足立は人情深いまちと思われていたが、近年は孤独死が問題になっており、そこからコミュニティを作るプロジェクトとして『アートアクセスあだち 音まち千住の縁』が立ち上がった。出発点は行政が多いです」と回答。一方で及川さんは、「むしろ、自分たちが『こんな社会を作りたい』と提起するために取り組みを行なっています」と答えます。
また小川さんは、近年の芸術祭などの活況を背景に、プロジェクト型の作品を制作するアーティストが全国で引っ張りだこになっている状況を説明。「しかし、そのなかで疲弊したり、芸術祭に参加するためにわざわざプロジェクト型の作品を作ったりする作り手もいる」と、アーティストが社会に過剰に適応することの問題点も指摘しました。

成果の測り方も、立場によってさまざま。議員の及川さんには、取り組みの現実的な効果の言語化がつねに求められます。他方、吉田さんは受け手の変化について、「以前は《Memorial Rebirth 千住》を『シャボン玉』と呼んでいた地元のおじさんが、あるとき『アート』と呼び始めた。そのとき彼の中で何かが変わったと感じた」というエピソードを紹介。発言の微妙な差異のなかに、プロジェクトに向かう上での各人の哲学が滲みました。
最後にマイクを握った森は、今回集まったプロジェクトのひとつの共通点は、活動の出発点に「問い」や情熱があり、そこから革新が生まれていることだと指摘します。
「しかし問いは、その射程や発せられる空間によって変化します。たとえば、及川さんは厳格な計画を求められる立場から問いを発しているのに対し、小川さんのアートの本質に関する問いは人類普遍のものでしょう。3人はお互いをリスペクトしながらも、人生を背負って自らの問いを実践している。そんなアートプロジェクトの幅広さを見せられたこと、そこから多くの問いが生まれたことが今日の成果だと思います」。

こうして約3時間にわたる、3回目の「ART POINT MEETING」は終了。
イベント後の会場で、繰り返し強調していた「アートにしかできないこと」とは何かを小川さんに尋ねると、「決して消費されないこと。でもそのことで、人生に影響を与え得ることだと思います」との答えが。
「世界を単純にではなく、複雑に捉えさせられるのがアート。社会の課題に合わせて制作をさせるのではなく、アーティストにしか見えない世界と、社会の接点を作るのが僕の仕事です。個人的な問題から出発していても、良い作品は結果的に社会の問題につながっていく。今後も、アーティストという存在にこそフォーカスしていきたいです」。
一方で吉田さんは、プロジェクトを通して多様な人々がひとつの場所に集まること、そのものに可能性を見ます。
「アーティストの野村誠さんと足立でやっているプロジェクト『千住だじゃれ音楽祭』は、原発問題で浮き彫りになった人々の多様な価値観が出発点になっているんです。普段、人は自分と同じ価値観の人たちとだけ付き合いがちですが、違う考え方を持った人たちとどう共生できるかを、プロジェクトの場を通して問いたかった。しかしそこで重要なのは、価値観を押し付けたり、論破したりしてはいけないということ。参加者自身の中から問いが生まれるような場の設定を、いつも大切にしています」。
「賭け」にも近いほかの2人のアート観に対して、「自分はどうしても課題解決という具体的なゴールを見据えた動きをしなければいけない」と語るのは及川さんです。
「プライベートでの活動がどんな風にまちの役に立つのか、議員として説明できる余地をつねに担保しようとしています。でも、何が起こるかわからないのがアートプロジェクトの面白さだという気持ちは一緒。アートの問題提起力や、そこで求められる想像力はこれからのまちに必要です。そのことを認知させる試みを続けていきたいと思います」。
関わるのはアーティストか、住民か、まちの課題か。アートは一体、まちのなかでどのような役割を果たすのか——。そうした疑問のなかで、それぞれが考えるアートプロジェクトのレンジの広さが見えた今回の「ART POINT MEETING」。活発な質問を投げかけていた参加者の頭には、イベントを経てより多くの疑問符が生まれたかもしれません。
しかし、そうしたレンジの広さは同時に、さまざまなプロジェクトの主体が集って言葉を交換する、こうした場の重要性をあらためて感じさせるものでもありました。
「ART POINT MEETING」は、今後も約半年に一回のペースで開催。今回、浮かび上がった疑問点がこれからの議論にどう引き継がれ、発展していくのか。引きつづき、注目していきたいと思います。

>>レポート前編
(イベント撮影:高岡弘)
2つの顔で課題に向き合う/まちで味方をつくるには?(APM#03 前編)
ART POINT MEETING #03 –まちで企む- レポート前編
「アートプロジェクト」と一口に言っても、それぞれの現場には活動のスタイルや根本的なアート観、社会との距離感などの点で驚くほどの幅があるものです。東京アートポイント計画が昨年6月より始めた「ART POINT MEETING」は、そんなさまざまな志向性を持ったプロジェクトの担い手が集い、言葉を交わすトークイベント。その第3回目が、2017年7月2日、東京・武蔵野市の図書館「武蔵野プレイス」で開催されました。
今回のテーマは「まちで企む」。八王子市議会議員を務めながら同市で空きテナントの活用プロジェクト「AKITEN」を運営する及川賢一さん、足立区で「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」の事務局長を務める吉田武司さん、JR中央線の高円寺から国分寺間を舞台に「TERATOTERA」を展開してきた小川希さんと、東京の各所で存在感のあるプロジェクトを仕掛けている3人のプロジェクトリーダーが登場しました。
これまでの回にも増して、アートとまちの関係についての各人の考え方の違いが浮かび上がり、聞き手も巻き込んだ活発な議論が起こった今回のART POINT MEETING。はたして彼らは、何を目指してまちにアートを投げ入れ、その実現のためにどんな工夫をしているのでしょうか? イベントの様子を、ライターの杉原環樹がレポートします。
3名のプロジェクトリーダーは、何を“いじって”いる?
東京都議会議員選挙の投票日でもあったこの日。会場には80名超の参加者が集まり、活況を呈しました。イベントはまず、東京アートポイント計画のディレクターである森司の趣旨説明からスタートします。
今回登場する3人が手がけるプロジェクトには、現在進行形のものも、すでに卒業したものも含め、東京アートポイント計画と共催経験があるという共通点があります。しかし、それぞれがまちと関わる意図は「三者三様」と森。今日のポイントとして、彼らがまちと関わるなかで「何を“いじって”いるのか?」に注目してほしいと話しました。

アートプロジェクト代表と議員。2つの顔でまちの課題に向き合う
1人目の登壇者・及川賢一さんは、経営コンサルティング会社勤務やカフェ経営を経て、2011年に地元である八王子の市議会議員選挙に無所属で立候補し、当選。翌年には仲間のクリエイターたちと、空きテナントを活用するアートプロジェクト「AKITEN」を開始した、異色の経歴の持ち主です。

そんな及川さんのトークテーマは、「まちの課題はアートで解決できる?」。市議会議員として公的な活動をしながら、アートプロジェクト「AKITEN」というもうひとつの車輪を動かしている意図とは何なのか? そうした考え方に至った経緯を次のように語ります。
「アートプロジェクトの可能性のひとつは、問題提起をすることに優れている点だと思います。この可能性を実感したのは、東日本大震災後の原発をめぐる問題のなかで、音楽家の表現の方が政治家の言葉より伝わると感じたこと。空きテナントが増えることによる商店街の過疎化という問題に対しても同じです。駅前でいくら演説をしてもなかなかわかってもらえない。しかしアートプロジェクトで空きテナントの活用可能性を体感してもらえれば、言語的な説明を超え、人の感覚に訴えることができるんです」。
こうした発想からAKITENでは、作品展示やトークイベント、リノベーションスクール、地元の食文化を発信するファーマーズマーケットなど、幅広いプログラムを空きテナントを活用して展開してきました。

「試みを通して、人々に『まちの理想像』や『現状』に触れてもらい(問題提起)、現場で直面した課題を行政にフィードバックして、解決に取り組む(問題解決)。二つの立場をつなぐことで可能になる、そんなまちづくりのあり方を目指してきました」。
どんな空間も、使用によって初めて価値が生まれるもの。以前は自分たちからテナントオーナーに空間の提供を頼んでいたものの、「近年は使って欲しいと頼まれるようになった」と及川さんは言います。この取り組みも一因となり、八王子の中心市街地の空きテナント率は、2012年の約15%から2016年には約9.9%まで改善。使える物件が少なくなったことから、AKITENの拠点も八王子駅から西八王子駅付近へ移りました。
2016年1月に開店した「たねカフェ」は、AKITENの活動から生まれた具体的な成果のひとつです。「障害者が働けるカフェを作りたいが、場所がみつからない」という相談を受け、テナントの紹介や店舗デザインをAKITENメンバーがサポートしました。実現にあたっては、東京都の厳しいバリアフリー条例が課題になりました。
「たとえば、バリアフリー条例ではエレベーターのない建物には福祉施設がつくれません。しかし障害者の方々には、自分で階段を上り下りできる人も多い。そこで議会に提案をして、八王子では都内で唯一、バリアフリー条例の緩和を行いました。かつては厳しい条件のため、施設はまちから離れた郊外に作らざるをえなかった。でも、障害者の人と身近に接することで達成される心のバリアフリーこそ、重要だと思うんです」。

「これからのまちづくりでは、ただ人口の引っ張り合いをするのではなく、まちに関わる人を増やすことが重要」と及川さん。彼にとってアートとは、まちの課題に人の意識を向けるためのひとつのツールであり、そこにはつねに、現実を行政面から具体的に改善しようとする議員の意識が並走しています。アートの専門家はなかなか持つことの少ないこの姿勢にこそ、AKITENのプロジェクトとしての特殊性があると感じました。

関係性=可能性。まちの人たちと見たい風景を共有する
続いて登場したのは、吉田武司さん。吉田さんは足立区で現在展開するアートプロジェクト「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」のほかにも、埼玉県北本市での「北本ビタミン」、東京都三宅島での「三宅島大学」など多くのアートプロジェクトに、そのまちの住人になりながら関わってきました。「まちで味方をつくるには?」と題されたプレゼンでは、プロジェクトを進めるなかで必要となる地元の人々との関係性の築き方を中心に、その体験が紹介されました。

「人との関わりがあって初めてできる作品がある」。そのように吉田さんが実感する原体験となったのは、2008年よりスタッフとして関わった「wah document」の活動だと言います。現在、各地で活躍する現代芸術活動チーム「目」の前身にあたるこの活動体では、一般参加者からアイデアを募り、実現の道を探る試みが展開されました。ただしそのアイデアは、「空中から照明をぶら下げる」「家を持ち上げる」など、荒唐無稽なものばかり。しかしそれを何とか具体化するなかで、人々との連帯が生まれます。
「たとえば照明のアイデアでは、実際に2メートル四方の照明器具をヘリから下げて飛ばしたのですが、一見、何の利益もない試みへの協力者を見つけるのは大変でした。ところが交渉を進めるなかで、ヘリや私有地を貸してくれる人が現れた。すると、実現不可能に思えたアイデアを多くの人が信じるようになり、プロジェクトがドライブしていくんです。見たい風景を共有できるようになる、そんな感覚に魅了されました」。

2013年に関わった「三宅島大学」(※)でも、地元の理解が課題に。プロジェクトのために三宅村役場の職員として働き始めた吉田さんですが、「アートプロジェクト」はなかなか浸透せず、職場では消極的な空気も一部にあったといいます。
(※)プロジェクトは2011年~2013年で実施。
「身内に味方を作らないと前に進めないなと思いました。そこで、『お酒の席や喫煙所での会話を大切にする』、『住民しか知らない情報を集める』、『反発ではなく共通点を探る』など、地域での自分の振る舞い方を基本的な部分から見直しました。簡単なことですが、続けるうちに少しずつ本音も聞けるようになり、味方も増えていきました」。
努力の甲斐もあり、アーティストや地元の人が講師となり、自分の知識やスキルを他の人に伝える開発好明さんによるアートプログラム《100人先生》の参加者も増加。最終的には地権者や役場の人も関わるようになり、それぞれが持つ三宅島の知識や資源を共有する場になったと言います。

現在事務局長を務めている「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」にも、多様な住民が参加。アーティスト・大巻伸嗣さんによる大量のシャボン玉で風景を変貌させる人気プログラム《Memorial Rebirth 千住》では、東京藝術大学の学生から地域の学校のPTAや先生、足立区の職員まで、約150人が運営に携わります。
「まちの人たちに運営まで参加してもらい、その役割を地域の中でリレーのように受け継いでいるのが継続の肝です。そこから『大巻電機K.K』という、シャボン玉マシーンの管理を行う市民チームも誕生し、足立に独自のネットワークを生み出しています」。

こうした活動を通して吉田さんは、「関係性=可能性」だと感じると話します。目的がわかりづらいと思われがちなアートプロジェクトでも、そこに理解者から批判者まで大量の人が関わることによって、何かが生まれる可能性が拓ける。そのとき、吉田さんの担ってきた役割とは、プロジェクトのマネジメントという以上に、住民として入り込み、些細な会話や交流を通してまちの雰囲気や空気を変えていくことにあるのかもしれません。

(イベント撮影:高岡弘)
荒田詩乃
及川賢一
鬼頭健吾
嶋田昌子
水谷朋代
L PACK.
Artpoint Meeting 2017
社会とアートの関係性を探るトークイベント
「まち」をフィールドに、人々の営みに寄り添い、アートを介して問いを提示するアートプロジェクト。Artpoint Meetingは、アートプロジェクトに関心を寄せる人々が集い、社会とアートの関係性を探り、新たな「ことば」を紡ぐ東京アートポイント計画のイベントです。
2017年度は、東京各地で実施しているプロジェクトの実践者による企てや、文化と日常の関係性について議論を深めます。また、東京アートポイント計画に参加する11のNPOによる公開プレゼンテーションを通じて、現場の悩みや展望について語り合います。
詳細
スケジュール
2017年7月2日開催
Artpoint Meeting #03 –まちで企む–
- ゲスト:及川賢一、吉田武司、小川希
- 会場:武蔵野プレイス 4Fフォーラム
2018年1月27日開催
Artpoint Meeting #04 –日常に還す–
- ゲスト:竹田由美、アサダワタル
- 会場:100BANCH 3F LOFT
2018年3月25日開催
Artpoint Meeting #05 公開報告会
- ゲスト:一般社団法人 Ongoing、NPO 法人アートフル・アクション、NPO 法人音まち計画、一般社団法人 CIAN、NPO 法人トッピングイースト、NPO 法人インビジブル、一般社団法人指輪ホテル、一般社団法人 kuriya、NPO 法人場所と物語、NPO 法人神津島盛り上げ隊、社会福祉法人東香会
- 会場:アーツカウンシル東京 大会議室