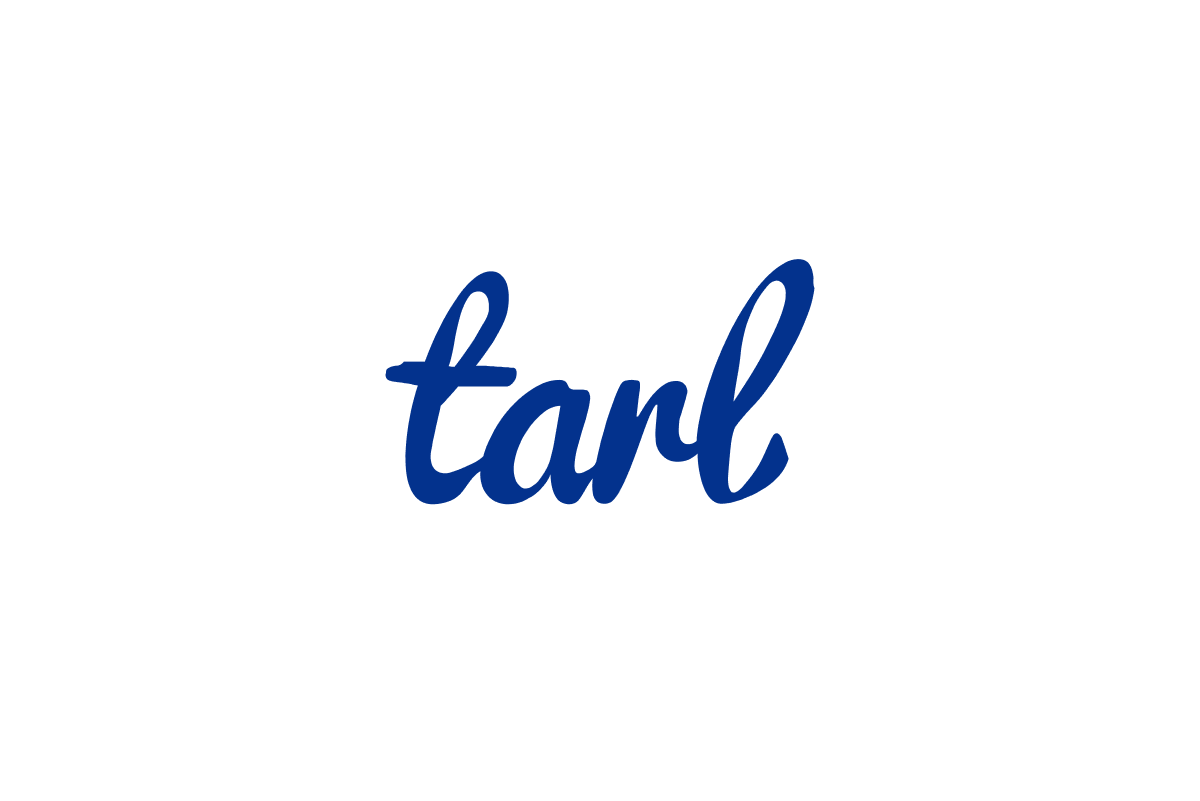「リライトプロジェクト」を運営する、NPO法人インビジブル 理事長/マネージング・ディレクター・林曉甫(写真右)、クリエイティブ・ディレクター/アーティスト・菊池宏子(撮影:高岡弘)
「東京アートポイント計画」に参加する多くのアートプロジェクトは、いったいどのような問題意識のもと、どんな活動を行ってきたのでしょうか。この「プロジェクトインタビュー」シリーズでは、それぞれの取り組みを率いてきた表現者やNPOへの取材を通して、当事者の思いやこれからのアートプロジェクトのためのヒントに迫ります。
第2回で取り上げるのは、2015年にスタートした「リライトプロジェクト」です。東日本大震災を機に消灯された宮島達男さんのパブリックアート《Counter Void》を毎年3日間限定で再点灯する「Relight Days」と、アート的アプローチを生かした行動によって自らの生活や社会を変える「社会彫刻家」の育成を行う「Relight Committee」。この二つを軸としたプロジェクトでは、震災後の社会でアートが果たしうる「装置」としての可能性に焦点が当てられてきました。
一方、プロジェクトと並行して設立されたNPO法人インビジブルでは、地域再生から教育まで、多様な現場でアートを取り入れた実践を展開しています。「大きな時代の流れの中に、小さな支流を作る」かのような彼らの活動、そして、より社会に接続していくこれからのアートの“使い方”とは? インビジブルの林曉甫さんと菊池宏子さん、東京アートポイント計画ディレクターの森司に語ってもらいました。

逆境から生まれたアートプロジェクト
——リライトプロジェクトは、2013年より始まった、六本木ヒルズにある宮島達男さんのパブリックアート《Counter Void》の再点灯を考察する「光の蘇生」プロジェクトを土台としているそうですね。まずは光の蘇生の経緯について聞かせてください。
森:きっかけは、宮島さんとの何気ない会話の中で、彼が《Counter Void》の電気を消していると知ったことでした。当時僕は、美術家の川俣正さんと行っていた「川俣正・インプログレス―隅田川からの眺め」(2010〜2013年)の終了もあり、次に東京で世界的なプロジェクトを協働できるアーティストを探していたんです。そこで宮島さんに会いに行くと、彼が震災から2日後の2011年3月13日、計画停電に先立って、自主的に作品を消灯する決定をしていたと知って。再点灯の議論自体をプロジェクトにしようと考えたんです。
——そこで、多分野のゲストを招いた勉強会を中心とする、光の蘇生の活動が始まったわけですね。当初、林さんはその事務局のスタッフとして、菊池さんは勉強会のゲストとして参加しています。
森:林くんは彼の前職のBEPPU PROJECTでの実力を知っていたし、震災を機にアメリカから帰国した菊池さんは、あいちトリエンナーレでの評判を聞いて、良い人がいるなと思っていました。光の蘇生では、そんな豪華メンバーでチームビルディングすることで、予測できない動きが生まれる生態系を作りたかったんですね。その一方、光の蘇生はまだ20世紀的な価値観で進んでいたプロジェクトでした。というのも、ここで議論していたのは、要は「作品の再生(※)」ですから。物理的な作品を中心にした、従来の芸術観の延長にあるプロジェクトだったんです。しかし途中で、作品の所有者からの要請などもあり、完全な再生が難しくなってしまった。そして、この逆境への応答の中から、インビジブルがプロジェクトを現在のかたちに更新していったんです。
※編注:当時「光の蘇生」では経年劣化した《Counter Void》を修繕し、作品として完璧に再生した上で、再び点灯させることを目指していた。

林:光の蘇生では、作品の修繕資金を集めるファンディングの仕組みなどを作っていたのですが、他方で、ただ作品を綺麗にして再点灯を実現しても、その社会的な位置付けが変わらなければいけません。そこで、宏子さんを招き、コミュニティ開発の領域にもプロジェクトを展開していくことを考えました。しかし、プロジェクトが本格稼働する直前、作品の蛍光灯を全てLEDに入れ変えて再生することは難しいという話になり、一転してプロジェクトをゼロベースで考えなおさなくてはいけなくなりました。ここでプロジェクトを離れることもできたけど、宮島さんは僕が最初に仕事をしたアーティストですし、六本木の喧騒の中に「生と死」をテーマとする《Counter Void》があることは意味があるのでやりたかった。それで、宏子さんとインビジブルを設立することにして、森さんに「この企画を引き取りたい」と提案したんです。
菊池:こうした状況は、コミュニティ開発の世界ではよくあることなんですよ。地権者や所有者の事情で紆余曲折するというのは。でも、そこに対していかに柔軟に、クリエイティブな発想を埋め込んでいくのかが、プロセスの重要な部分になるんです。

——毎年3日間だけ再点灯するRelight Daysの発想は、そこで生まれたのですか?
林:そうですね。どうしたら状況を裏返せるかを考えたとき、3月11日から作品の電気が消された3月13日までの3日間をシンボルに使えないかと。伝統的にも、灯籠流しやお盆のような、失った人へと哀悼を捧げる年中行事がありますよね。作品すべてを再生できなくても、その三日間の再点灯によって失われたものを見せたいと考えたんです。
森:宮島さんが一番こだわっていたのは、点ける理由なんです。でも、作品再生ができなくなったとき、ある意味で点ける理由ができたんですね。その理由を正当化してくれたのがインビジブル。ロジカルに考えると「点けられないなら諦めよう」か、正面突破で抗議をしにいくのが普通でしょう。でも、彼らが提案したのは「三日間だけ点けるのはどうですか?」ということ。これは宮島さんと僕にとっては、すごくシャープな回答だった。このとき、我々が光の蘇生でやってきたことは、リライトプロジェクトとしてインビジブルへと移行されたんです。


考える装置としてのアート
——菊池さんは最初ゲストとして参加した中で、なぜ、このプロジェクトにここまで深く関わろうと思ったのでしょうか?
菊池:タイミングというのは、率直な答えとしてあって。ゲストで関わり、結果NPO法人まで立ち上げるのは、自分の意思以外の部分に促された不思議な感覚もあります。そもそも、今日は整理をして話していますが、当時は考える要素も多く、わからないことや戸惑いもあったんです。でも、森さんのアート作品を装置としてプロジェクト化したいという気持ちは、私がアメリカでやってきたこととも重なっていました。特別な存在としてのアーティストが作る、自我を表現する作品という以外にも、アートには社会的な装置や触媒としての機能がある。どうアートを生かしていくかという意識の重なりがあったから、やりたいと思いました。あと、宮島さんを含めて、こういう人たちと仕事をしてみたいという思いも大きかったですね。
林:スティーブ・ジョブズの「コネクティング・ザ・ドッツ(点と点を結ぶ)」という言葉があるけど、うまい表現だなと。振り返ると整理されちゃうけど、当時は1日1日なんとか前に進んでいるような状態だった。もともとこのプロジェクトの名前を「Relight Project」にするか「Rewrite Project」にするかを考えていたことを思い出し、先日も宏子さんと「『Relight』という表記にしているけど、実際は書き換えるという意味の『Rewrite』の方だね」と笑って話していたんです。このプロジェクトは直線的ではなくて、状況に応じて変化しながら進んできたんですよね。
森:計画的ではなく、現在進行形。チームができるまでには多くの時間を過ごしたけど、そこに良いプロセスがたくさんあったんです。現在のかたちは、当初は誰も想定していなかった。宮島さんはよくこの結果を引き取ってくれたなと思います。

——装置や触媒としてのアートというお話がありましたが、リライトプロジェクトがアートプロジェクトとして異質なのは、いわゆるアーティストを中心とした作品制作が行われていない点ですね。
林:Relight Daysにしても、作品を3日間点灯するだけで、アーティストに新しい作品制作を依頼するわけではないですからね。でも、僕らが問おうとしていたのは、この社会の中で、我々はいかにアートを必要とするのか、ということ。たとえばこのプロジェクトでは、六本木にある港区立笄(こうがい)小学校図工科の江原貴美子先生とその生徒と、ワークショップをしたり《Counter Void》の現場に足を運んだり、様々な形で関わりをもったのですが、結果として彼らは再点灯を自分事として考えてくれるようになった。宮島さんの本来の意図を引き継ぎつつも、それを自分の言葉で紡げる人が生まれたことは、意味があることだと思います。
菊池:一方、Relight Daysが年に3日間のシンボルだとすれば、その土台としてある365日間で、点灯の意味や、震災後の社会とアートを考える場として始めたのが、市民大学のRelight Committeeです。この二つがないと、リライトプロジェクトは成り立たないんですね。作品は、物理的にはすぐ点けられる。でも、なぜわざわざ点けるのか。その社会的な意味とは何か。それを作品の作者や所有者ではなく、本来作品を鑑賞する側が議論するところにこのプロジェクトの本質があります。わかりにくい部分もありますが、やりがいでもあるんです。

社会彫刻家を育てる学びの場
——Relight Committeeがミッションとして掲げているのが、社会彫刻家と呼ばれる存在の育成や輩出です。「社会彫刻」は、もともとドイツ人アーティストのヨーゼフ・ボイスが提唱した概念ですが、このプロジェクトではそれを現代的に捉え、社会彫刻家を「アートが持つ創造性や想像力を用いて、自らの生活や仕事に新たな価値をつくり続け、行動する人」と定義していますね。なぜこの言葉を使うことになったのですか?
菊池:そこにはプロジェクト1年目の、私の認識不足によるつまずきがあったんです。そもそも初年度のコミッティは、「アートと社会について従来の定義や枠組みを超えた対話を重ね、具体的な行動につなげる人を育てる学びの場」という目的を持って立ち上げました。初めての再点灯とそこに向けたプログラムづくりなど、彼らの時間や労働の多くがそこに注がれてしまい、実践からの学びはあるものの、根本のアートや社会の関係などの学びの部分が抜け落ちてしまったというか。いろんな意味での認識の違いやズレから、人が離れることなども起きてしまって。
そこで、どうしても必要な学びの要素を取り入れ、本当に何かを変えたいという思いのある人を育てたいなと。アートファンの育成でも、造形やコンセプトの美しさの学びでもなく、「アートが装置である」という認識を育てるうえでは、歴史上、やはり社会彫刻の考え方に戻らないといけない。そうしないと、いつまでも宮島さんの作品をどうするかという話にしかならないという危機感があったんです。
森:Relight Daysが当初の再生計画の延長上のプログラムだとしたら、Relight Committeeはそこにあるアートをいかに使うかを考えるプログラム。つまり、アートに対するタッチの仕方が違うんですね。ただ、いま菊池さんが話したことは、NPO側の思惑だから、じつは僕も初めて聞いたんです。思いつきじゃないから、我々も引き取ることができたんだなと。

林:社会彫刻は重要な概念なので、使うことには戸惑いもありました。もちろん僕たちもボイスの考え方をつねに振り返っていますが、重要なのは、僕たちが生きている社会はいまこの社会だということ。だから、「ボイスが何をしたか」を学ぶのではなく、ボイスの考えを引き継ぎつつ、現代を生きる僕ら一人ひとりが「社会をいかに彫刻し生きていくか」を考えたい。概念を知るだけでなく、それを踏まえて実装する人を増やしていきたいんです。
森:その意味では、インビジブルは「アートNPO」と呼べる組織になりましたね。アーティストの活動を支えるNPOは山ほどあるけど、インビジブルはひとつの思考体として、NPOそのものからメッセージを発信できる。物言えるNPOになったと。この考え方は、宮島さんのキーワードである「Art in You」(アートはそれを受け取るあなたの中にある)にもつながるものです。
菊池:ただ、日本の美術大学では、意外と社会彫刻についてあまり教えられないんですよね。それは私が通っていたアメリカの美大では、ありえないことだったので。すべての学生が、アートの概念、表現方法のひとつに「行動」があると教えられる。でも、社会彫刻家という考え方が日本でも本当に必要だと納得するために、一年目のつまずきは重要なプロセスでしたね。

>〈後篇〉「問いを通じて見えない状況を可視化する。これからのアートNPOとして ―インビジブル林曉甫・菊池宏子「リライトプロジェクト」インタビュー」
Profile
林曉甫(はやし・あきお)
NPO法人インビジブル 理事長/マネージング・ディレクター
1984年東京生まれ。立命館アジア太平洋大学アジア太平洋マネジメント学部卒業。卒業後、NPO法人BEPPU PROJECTに勤務し公共空間や商業施設などでアートプロジェクトの企画運営を担当。文化芸術を起点にした地域活性化や観光振興に携わる。2015年7月にアーティストの菊池宏子と共にNPO法人インビジブルを設立。International Exchange Placement Programme(ロンドン/2009 )、別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」事務局長(別府/2012)、鳥取藝住祭総合ディレクター(鳥取/2014,2015)六本木アートナイトプログラムディレクター(東京/2014~2016)、 Salzburg Global Forum for Young Cultural Innovators(ザルツブルク/2015)、女子美術大学非常勤講師(東京/2017)
菊池宏子(きくち・ひろこ)
NPO法人インビジブル クリエイティブ・ディレクター/アーティスト
東京生まれ。ボストン大学芸術学部彫刻科卒、米国タフツ大学大学院博士前期課程修了。米国在住20年を経て、2011年、東日本大震災を機に東京に戻り現在に至る。在学中よりフルクサスやハプニングなどの前衛芸術・パフォーマンスアート、社会彫刻的観念、またアートとフェミニズム、多文化共生マイノリティアートとアクティビズムなど、アートの社会における役割やアートと日常・社会との関係について研究・実践を続けている。MITリストビジュアルアーツセンター、ボストン美術館、あいちトリエンナーレ2013、森美術館など含む、美術館・文化施設、まちづくりNPO、アートプロジェクトにて、エデュケーション活動、ワークショップ開発・リーダーシップ/ボランティア育成など含むコミュニティ・エンゲージメント戦略・開発に従事。また、アート・文化の役割・機能を生かした地域再生事業、ソーシャリーエンゲージドアートに多岐にわたり多数携さわってきている。その他武蔵野美術大学、立教大学兼任講師、一般財団法人World In Asia理事なども務めている。
NPO法人インビジブル
アートを軸にした「クリエイティブプレイス(Creative Place)」を標榜するNPO法人。「invisible to visible(見えないものを可視化する)」をコンセプトに、アート、文化、クリエイティブの力を用いて、地域再生、都市開発、教育などさまざま領域におけるプロジェクトの企画運営や、アーティストの活動支援、アートプロジェクトの支援や運営人材の育成、それに伴うプロトタイプの研究に取り組んでいる。
http://invisible.tokyo/
リライトプロジェクト
六本木けやき坂のパブリックアート『Counter Void(カウンター・ヴォイド)』を再点灯させると同時に、未来の生き方や人間のあり方を考えるプラットフォーム形成を目指すプロジェクト。東日本大震災をきっかけに、作者であるアーティスト・宮島達男の手によって消灯されたこの作品を、3.11の記憶をとどめ、社会に問いかけ続けるための装置と位置づけ、様々なプログラムを展開します。
http://relight-project.org/
*東京アートポイント計画事業として2015年度から実施