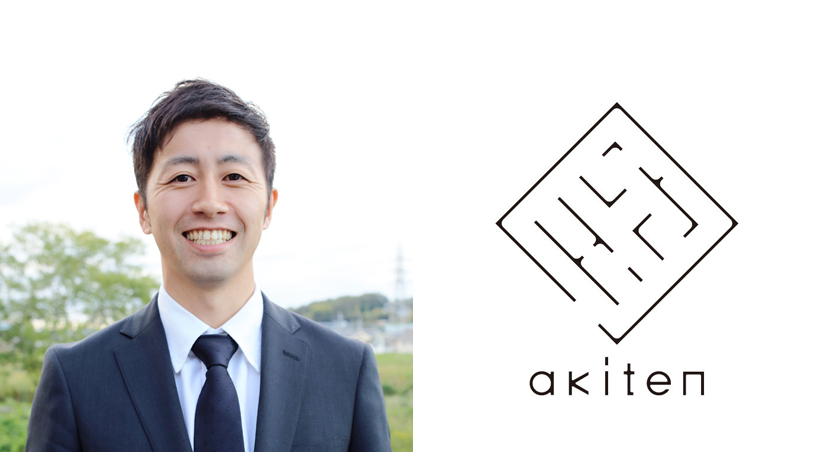
「アートポイントに参加してどうでした? 」卒業NPOに聞く
アートプロジェクトを実施しながら、地域社会を担うNPOの成長を支援する「東京アートポイント計画」(以下、「アートポイント」)。現在までに43団体のNPO等とともに、アートプロジェクトを共催してきました。
東京都、アーツカウンシル東京とともにアートプロジェクトを「共催」することには、NPOにとってどんな意義やメリット、あるいは大変さがあるのでしょうか? 今回は、NPOの視点でアートポイントでの共催について振り返るべく、卒業団体のひとつ、NPO法人AKITEN代表の及川賢一さんを訪ねました。
聞き手:大内伸輔(アートポイント チーフマネージャー ※2014年度AKITEN担当)
お話を伺った人
及川賢一さん(NPO法人AKITEN代表 / 八王子市議会議員)
1980年生まれ。東京都八王子市出身。 東京都立大学大学院修了(経営学修士) 、ソニー(株)、経営コンサルティング会社を経て、八王子にcafé Wを共同設立。 2011年より八王子市議会議員(無所属)。現在2期目。 空きテナントを活用したアートプロジェクトを運営するNPO 法人AKITEN 代表。 八王子のデートスポットを紹介するTV番組「恋する八王子彼女」プロデューサー。
AKITENについて
文化や産業など地域の独自性を持ったコンテンツを空きテナントに持ち込み、アート、デザインの力でそれらの魅力を地域の内外へと発信していくプロジェクト。誰もが空きテナントを使えるシステムを構築し、空きテナントをまちづくりのツールとして活用している。2012年度に任意団体として及川氏らが立ち上げ、アートポイントでは2014年度からの2年間、プロジェクトを共催した。現在は、ギャラリーやレジデンス運営、地域と連携したプロジェクトを続けている。
http://akiten.jp/
1、2年で空きテナントがなくなった
大内伸輔(アートポイント):AKITENは、空きテナントを使って「こんな価値もあるんだ」と見せていく、プレゼンテーションの機会をつくる試みでしたよね。プロジェクトを進めるうちに借り手が増え、空きテナントは減り、短期間で成功していった印象です。
及川賢一(AKITEN):まちづくり会社や市役所と一緒に取り組んだ成果でもあります。最初は僕たちが「貸してください」とお願いして回っていたのに、いつのまにか「うちの空きテナントを使ってもらえませんか」と依頼される側になりました。途中から不動産屋さんが「AKITENのイベントに貸すと埋まるよ」というチラシをつくって配ってくれたり。さらに1,2年経ったら、空きテナントがこのエリアからなくなってしまって、「入居したいけど物件が見つからない」という相談までくるようになりました。他には「お店を始めたいのでプロデュースをしてくれないか」などのお声がけもいただくようになりました。
大内:アートポイントは、NPOが地域で「文化のよろず屋」的に活躍することを目指しているので嬉しいエピソードです。そこまで頼られるAKITENの特徴ってどこにあるのでしょう?
及川:空きテナントを使ってアートイベントをする取組みは、珍しくありません。AKITENの特徴は、「募集中」の空きテナントを使い、超短期でプロジェクトをまわしていくところです。例えば、今月20日の時点で空いてるテナントがあるとして、契約期間を考慮すると、いきなり翌月1日から使う人はいません。そうすると、だいたい1ヶ月~1ヶ月半くらいなら、オーナーからテナントの使用許可を得られます。その短い期間で企画、展示計画、広報、搬入、開催、搬出を行うので、短期決戦になるんです。徹底的なプロジェクトマネジメントでリスクを減らし、超短期でプロジェクトを回し、その分、多くのイベントを開催できるのが、AKITENの強みであり特色です。


行政に提言するような、「モノ言うNPO」を目指して
及川:僕は政治家(市議会議員)なので、市内に空きテナントが多いという課題を前に、普通ならばマイクを持って「空きテナントを使いましょうよ」と言って回ります。でも、耳を傾けてくれる人がいないと意味がない。それより、アーティストが「空きテナントをこういうふうに使ったらこんなに面白くなるよ」と教えてくれたほうが、まちの人たちにも気づきが生まれる。その後は、自分が政治家として行政に具体的な施策や予算を提案をする役割を担えればいい。アートポイントに参加したときも、ディレクターの森さんや、担当の大内さんに言われたのは「モノを言うNPOになりなさい」ということでしたね。発言力を持ち、行政に対して提言ができるNPOになりなさい、と。
大内:そうでした。ただ、AKITENは私達と出会った時点ですでに活動3年目。事業スキームはもう完成していたんですよね。正直、NPOを育成支援するアートポイントとしては「共催の必要はないのでは?」という印象でした。でも、最初にお会いしたとき、「自分達じゃなくても活動が持続していく体制をつくりたいです」と及川さんはおっしゃいましたね。それなら、アートイベントやフェスティバルへの支援ではなく、NPOとして組織やシステムを残す活動を目指そう、と。そのビジョンを共有して、アートポイントでの共催がはじまりました。
及川:なのにそれを無視して、アートポイント参加1年目はイベントをやりまくりました(笑)。自主事業も合わせると年間11箇所の空きテナントを借りて。そうしたら、1年目の途中で「もうアートポイント卒業したら」と言われて。
大内:「共催前と同じようなイベント企画ばかりじゃないか」と(笑)。その頃、AKITENが開催していたイベントは、全部クオリティが高くて内容も面白いのですが、単純に、イベント開催資金が必要なだけなら、アートポイントの共催事業でやる必要はありません。なので「アートポイントは卒業し、助成金を受けては?」という話をしたんです。そうしたら「お金だけが欲しいわけじゃないんです。もう少し続けたい」とおっしゃって、それであらためてシステムづくりに移行したのが2年目ですね。

イベント主義を離れ、システムをつくる
及川:はい、なので2年目ではイベントは別企画や自主事業に回し、仕組みづくりをしました。「AKITEN運営マニュアル」をつくり、「空きテナントマッチングサイト」をつくり、空きテナントの使い方を考えるワークショップも開催しました。年度末には、AKITENのコンセプトを伝えられる企画をやろうということで、「AKITEN PARK」というイベントを開催しました。「空きテナントを空き地化する」というコンセプトをずっと持っていたので、昔の地主さんと同じように、空きテナントを空き地のように貸してもらえたらこんなに面白い空間ができるよということを提示したり。
大内:あと、AKITENは、ワンマン体制脱却も目標でしたね。
及川:チームメンバーは僕以外全員クリエイターなんです。デザインや、写真など専業で分かれていて、当初マネジメントは主に僕がやっていました。今は、僕がいなくても動かせる形になってきています。それにメンバーそれぞれが、どんどんまちのなかに関わっていくようになりました。この間も、市議会議員の研修で、AKITENメンバーの保さんがまちづくりの講師を務めることになって、僕が保さんの話を聞く側になりました(笑)。ある程度は「モノ言えるNPO」に、行政に何か提言できるような存在になったかなと。


共催事務は大変? 事務局はコスト?
大内:アートポイントに参加している間、お金だけじゃない、人的なサポートの面ってどう感じられましたか。
及川:1年目は結構「あれやりなさい、これやりなさい」とか「こうしたほうがいい」とかアドバイスをもらいましたね。ゼミ企画のテキストも全部大内さんに見てもらって、「こうしたほうがいい」と言ってもらいました。多いから削ろうとか、1ページずつ全部チェックしてもらっていました。とはいえ、ちょくちょく相談する機会があったかというと、そこまででもない。でも、誰かに見られているというか、誰かに対して報告しなくてはいけないというのは大事ですよね。第三者機関というか。
大内:私達も公共事業としてしっかり見て評価しないといけませんからね。見るポイントは、目標に対してできているのかどうか。できていたら「できていますね」と言うし、できてなかったら「できていないですね。どう改善しましょうか」と言う役割です。アートポイントの共催は、「事務が厳しくて大変」という声もあります。そのあたりはいかがでした?
及川:僕はもともとプロジェクトマネジメントの仕事をしてきたので、そういう意味では厳しくプロジェクトを進めていくことは慣れてるので大丈夫だったんですよ。ただ、他のメンバーに理解してもらうのは、ちょっと抵抗があったというか、大変でした。
大内:スピード感のあるクリエイティブなメンバーが揃っているとなおさらですよね。
及川:あと、開始当初は、僕の考え方とアーツカウンシル東京の考え方が真逆でした。僕は事務局というのは、基本的にはコストだと考えていました。事務局なしで成果を出せるんだったらそれがベストではないかと。でも、それに対して森さんや大内さんは「事務局という機能を残し、強くしていくことが大事」と言う。今でもはっきりした答えは出ていないのですが、長く活動を続けていると想像だにしない相談がAKITEN事務局宛にぽこぽこ来ます。それは、事務局というチームが存在していて、プロジェクトをマネジメントしている姿も見せられていることによるのかなと。そういう意味では、事務局を残していく必要もあるのかなとだんだん思えてきました。

テナント紹介から条例緩和まで。卒業後の活躍
大内:アートポイント卒業後、AKITENが相談を受けて、発展した活動にはどんなものがありますか?
及川:AKITENでかつて使ったテナントで、障害者の就労を支援する「たねカフェ」がはじまりました。テナントの紹介、ロゴデザイン、内装、カフェのレシピ等をAKITENメンバーがサポートしています。さらに開設にあたって、空きテナントを福祉施設として活用するために、八王子市のバリアフリー条例を緩和しました。
東京都のバリアフリー条例はすごく厳しいんです。例えば、高齢者でも歩ける方はいるし、知的障害や精神障害を持つ方も階段を上れるのに、エレベーターがない建物では福祉施設を開所できない。それはおかしいと八王子市議会で提案し、東京都で唯一八王子市だけは、2016年6月から条例が緩和されました。障害のあるなしに限らず、同じまちなかでごはんを食べ、買い物をしてという暮らしをしたほうが、ハードではなくハートのバリアフリーになるはずなんです。そういう意味で、これからもまちなかのテナント等に障害者の方が参加するお店をつくれるような展開が生まれればいいなと思っています。
大内:店舗の紹介からデザイン、条例緩和の提言までできるのは、クリエイターもいるし市議会議員もいるAKITENチームならではですね。

アートポイントで共催すると、中途半端な団体にはならない
大内:今日はその後の活躍がたくさん伺えて、嬉しかったです。最後に、アートポイントは今、新しい共催団体を募集しています。応募を考えているNPOに向けて、メッセージがあればぜひいただけますか。
及川:そうですね。すでにプログラムや事業が「できている」と思っている団体も、そうでいない団体も、第三者であるアーツカウンシル東京とプロジェクトを共催することで得るものがたくさんあると思います。正直、共催中は「調整が大変」だとか「事務が面倒」と思うこともありました。でも、終わった後はやってよかったなと思っています。ほかの団体もやったほうがいいと思いますよ。第三者に見られているって大事なことなんです。共催することで、中途半端な団体にはならないので。社会的な責任や個人情報等の扱い方含め、しっかりした組織がつくれると思います。
大内:ありがとうございます。AKITENのように、私達との共催スキームを上手に活用し、成長していくチームに出合えればと思っています。
