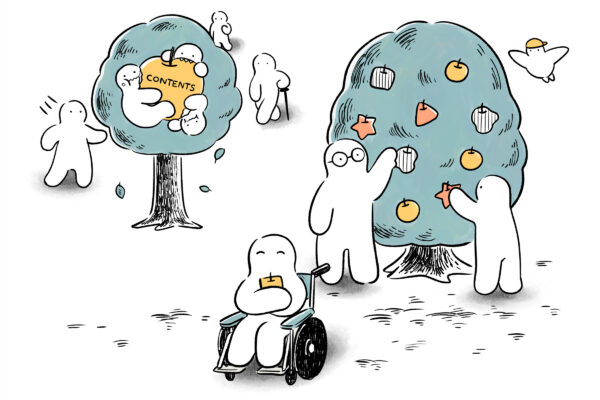
第5回:わたしたちの“ウェブアクセシビリティ”は広がり続ける | わたしたちの“ウェブアクセシビリティ”を考える
執筆者 : 萩原俊矢
2025.03.26

このレポートでは、複雑で多様化する現代のユーザー環境と、ウェブサイト制作のプロセスを見つめ直しながら、ウェブアクセシビリティの“いま”を捉え直します。
全5回を通じて、ウェブサイトづくりのこれからや、わたしたち一人ひとりができることを探ります。
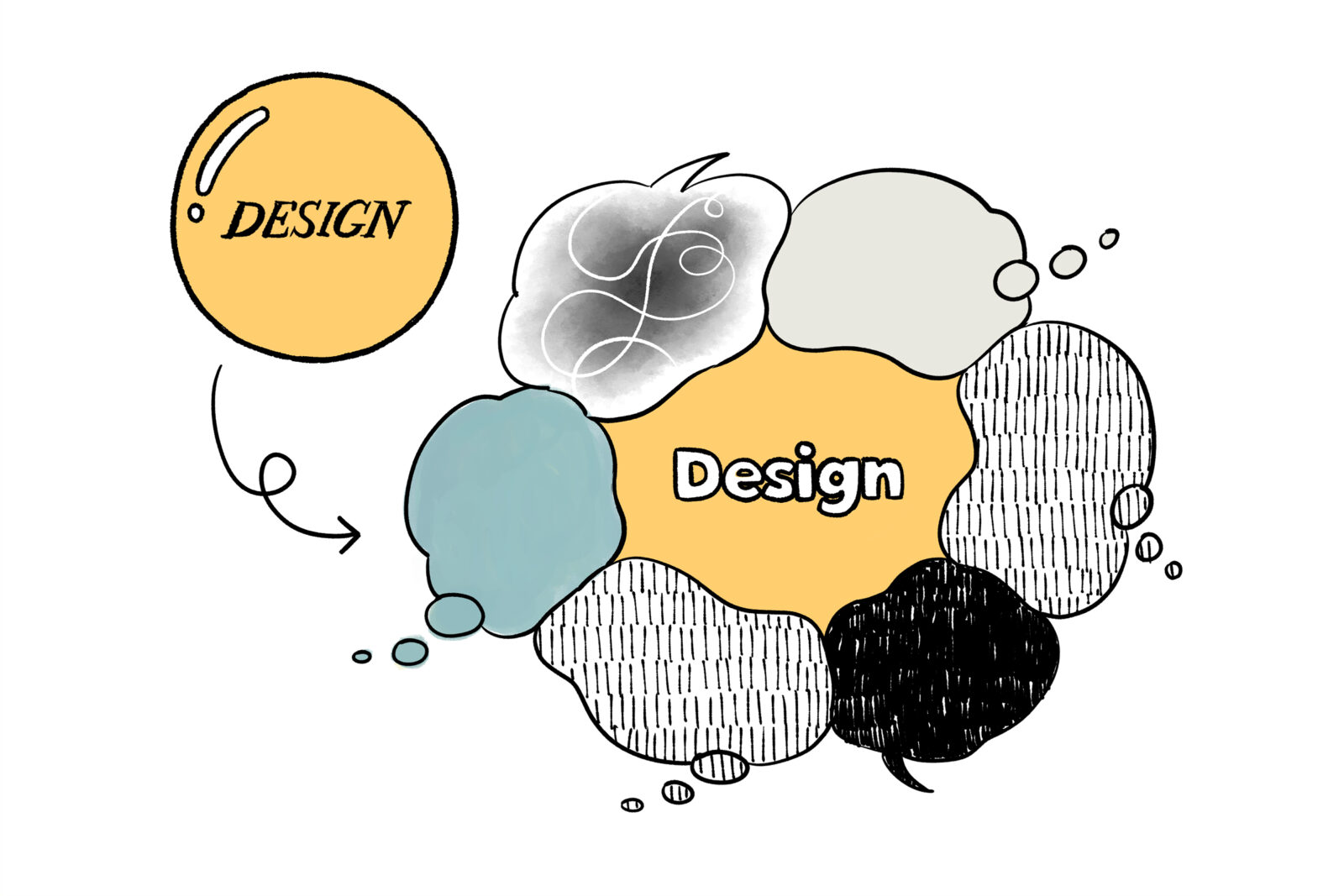
これまでも述べてきたように、ウェブサイトを閲覧・操作するユーザーの多様な視点から意見をもらうことで、制作者では気づけないアクセスしにくさが浮かび上がります。特に、「一般的」とされている設計では考慮されにくい環境で利用するユーザーの感想は、貴重な気づきをもたらします。こういった方々はUX(ユーザー体験)デザインの世界において「エクストリームユーザー(注1)」と呼ばれます。
制作者がどれだけ意識的にウェブアクセシビリティを考え、工夫を凝らしてデザインしても、実際のユーザーが感じるアクセスしづらさは、つくり手の意識の外側からやってきます。よかれと思って実装した機能が、あるユーザーにとってはむしろアクセスの妨げになったり、便利だと思って加えた演出が、別のユーザーにとっては先に進めなくなる要因になってしまうことがあるのです。
制作者が多様なユーザーのアクセスのしかたを的確に想像しながらデザインできれば理想的ですが、経験を積まないとその勘所をつかむことは難しいでしょう。だからこそ、ユーザーとの接点を増やし、実際の声を聞くことが重要になります。
ここでは、わたしがこれまでに経験したユーザーによるレビューの中で、よく意見をもらうポイントを紹介します。
「マウスカーソルを乗せたとき」にメニューが展開するようなインターフェースが、キーボードでは操作できないことがしばしば起こります。また、「Tabキー」で画面上のボタンなど操作可能な要素を選択した際に、強調表示するフォーカスリング機能が無効化されていると、いまどの要素を選択しているのかがわからず、操作ができなくなります。
これらは、実際にキーボードだけで操作してみると、すぐに気づくことができるポイントです。開発者からすると比較的手軽にアクセシビリティ向上に繋げられるポイントと言えます。
ユーザーがボタンをマウスカーソルでクリックしたり、タッチパネルでタップしたときに、その操作に対してインターフェースが適切な反応を示すことは、些末なようで実はとても大切なポイントです。
もし、マウスカーソルをボタンに乗せても、ボタンをクリックしても反応がないとしたら、操作している側はほんの少しだけ不安な気持ちが残ります。多くの人にとっては気にならない程度の違和感かもしれませんが、こうした小さな不安の積み重ねが漠然としたアクセスしにくさを感じさせます。
少し話はそれますが、「ストリートファイター」という格闘ゲームをご存知でしょうか?
この作品は近年、情報のアクセシビリティの観点からも注目されています。このゲームでは、プレイヤーがキャラクターを操作し、攻撃や防御をするたびに、効果音やコントローラーの振動による反応が起こるため、視覚に障害がある方でも楽しめるようです。実際に、ゲームが好きな全盲のスクリーンリーダーユーザーの方から「ストリートファイターは、攻撃や防御、一挙手一投足の動きに対して音や振動のフィードバックがあり、遊んでいてとても臨場感がある」という話を聞いたことがあります。
ウェブサイトのデザインにおいても、ユーザーの操作に対しての反応・手応えを意識的に設計することで、多様な人に、操作できている実感を生み出すことができるのです。
色のメリハリは、ウェブサイトの見やすさに大きく関わるポイントです。一般的にウェブアクセシビリティの規格では、背景色と文字色のコントラスト比は「4.5:1」以上が「レベルAA」として推奨されています。
「コントラスト比」という言葉に耳慣れない方もいるかもしれません。たとえば、白い背景に黒い文字を配置すると、最大のコントラスト比である「21:1」になります。一方で、薄いグレーの背景に濃いグレーの文字を使うと、コントラスト比が低くなり、視認性が低下して文字を判別しづらくなります。
しかし、コントラスト比の基準を満たしているからといって、必ずしもすべての人にとって読みやすいとは限りません。逆に、コントラストを強くしすぎると、別の問題が生じることもあります。たとえば、真っ白で広い面積の背景の上に黒い文字を小さく配置すると、「眩しくて読めない」と感じる人がいます。
また、色に関係なく、文字サイズが小さすぎたり、密度の高くアキが均一ではない書体では、文字が潰れて読みにくくなることがあります。
「読みやすさ」とはコントラスト比だけでなく、画面全体の明るさ、文字の大きさ、書体の種類、さらには文章の書き方など、さまざまな要素が絡み合って決まります。そのため、一概に「正解」を定義するのは難しいものなのです。
こうした小さな改善を積み重ね、ウェブサイトが不便になることはまずありません。きっと多くの人にとって快適な状態に近づいていくはずです。
しかし、実際にユーザーにウェブサイトをレビューしてもらうと、そこで指摘される内容はもっと曖昧で、不確かで、感覚的です。複数の課題が混在していたり、課題なのかも漠然としていて、「それって個人の好みでは?」とツッコミをいれたくなるようなこともあるかもしれません。そうした多様で自由なコメントを前に混乱しそうになったら、まずは次のように分類してみることをおすすめします。
たとえば、このようなカテゴリーに分けて整理すると、誰が主に対応を検討すべきかが明確になります。たとえば、「文字が見にくい」というユーザーの意見に対して、「デザイナーが担当し、リンクテキストを区別しやすくするために色や装飾を見直す」といった具体的なゴールを設定できます。「課題の担当者」と「何をもって解決したといえるのか」の二つの観点を明確にすることで、チームで分担しながらアクセシビリティの向上に取り組みやすくなります。
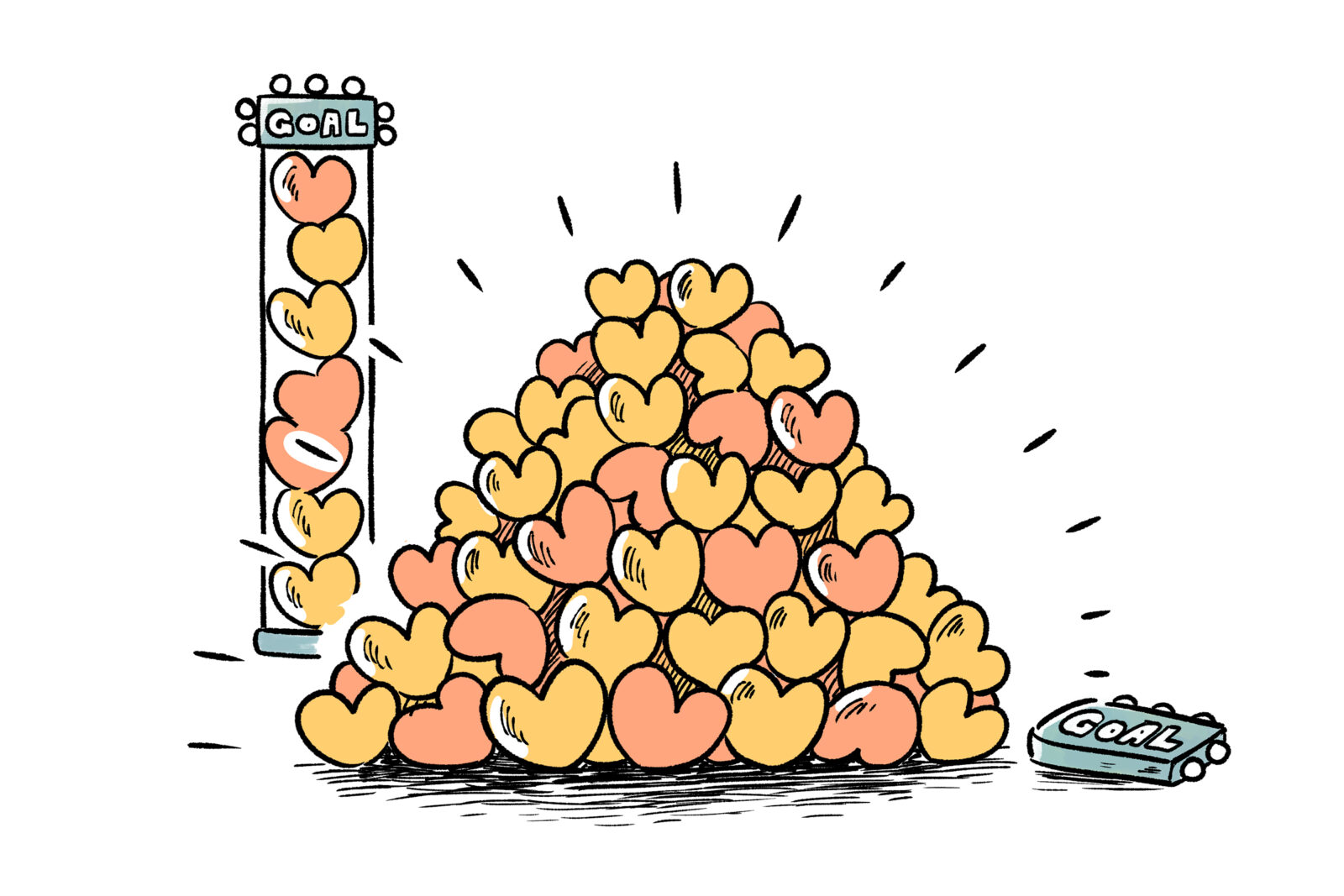
多様なユーザーにウェブサイトを見てもらうと、コントラスト比が低く見えにくい、スクリーンリーダーで適切に読み上げられない、一貫性のないデザインが気になって先に進もうと思えないなど、ユーザーの知覚の特性によって共通する課題があるように感じることがあります。しかし、だからといって「〇〇に障害のある人はこう見る」と決めつけてしまうと、ユーザーや環境ごとの感じ方の違いや、一人ひとり異なる繊細な感覚を見落としてしまうことにもなります。
実際のところ、色の見え方は人それぞれで、わたしが出会った人たちの中でも感じ方はさまざまでした。色覚の多様性は奥深く、一律に「これが最適な配色」と言えるものは存在しません。アクセスのしづらさは単純に「ある・ない」で分けられるものではなく、グラデーションのようにつながっています。固定された枠組みに当てはめることで分かりやすくなることもありますが、実際はもっと複雑で、一つのルールで単純に捉えられるものではないということです。
一方で、より効率的にウェブアクセシビリティの向上に取り組みたい企業や組織からは、ウェブアクセシビリティの指針や対応チェックリストを求められることも多く、わたし自身もそうした資料の作成に携わった経験があります。組織が大きくなればなるほど、ウェブサイトに関わるステークホルダーは増え、一貫して継続できる仕組みとするためにも基準となるものを明確にしたいと考えます。
たとえば、ウェブサイトを管理・運営する担当者からは「委託先の制作会社に伝えるための対応チェックリストがほしい」と言われることがあり、受託側のエンジニアやデザイナーからは「どこでも利用できるベストなメニューの実装方法を教えてほしい」と相談を受けることがあります。
たしかに、チェックリストやWCAGのような規格は、何をすべきかを明確にし、対応状況を把握する上でとても有用です。しかし、それだけでは結局ユーザーの姿がみえず実感を伴わない対応をせざるを得ません。チェックリストの背後には、一律に定義できないユーザーそれぞれの思いや感じ方があるのですが、そのグラデーションは捉えづらく、「型にはめること」と相反することでもあります。
つまり、ゴールを設けられないウェブアクセシビリティに「100点満点」はありません。どれだけ工夫を重ねても、すべてのユーザーにとって完璧にアクセスしやすいデザインを実現するのは不可能です。しかし、部分的な調整を続けることは着実にアクセシビリティの向上につながります。
繰り返しになりますが、まず何から手を付けていいかと悩んだら、まずはガイドラインを参考に、実際にウェブサイトをキーボード操作だけで動かしてみる、スクリーンリーダーで読み上げを試してみるなど、いつもとは異なる環境でウェブサイトを操作してみましょう。それだけでも新たな気づきが生まれます。さらに、自分とは異なる環境でウェブサイトを利用するユーザーに直接意見を聞くことができれば、より具体的な改善のヒントが見えてくるでしょう。
チェックリストや規格の背後にある「一般的と括られてこなかったユーザー」のさまざまなウェブサイトのアクセスしづらさに気づくことで、アクセシビリティは単なるチェックリストを達成するためのものではなく、さまざまな環境に対して改善を繰り返す継続的な取り組みに発展していくのではないでしょうか。
文: 萩原俊矢, イラストレーション: Maya Numata
Extreme Users、 Wikipedia (英語版)、https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_users (2025)
このレポートは全5回でお届けします。