
人と人、記録と未来をつなぐために、いま「オンライン化」を振り返る(APM#16 後編)
執筆者 : 杉原環樹
2025.03.31

毎回、まちで活動するさまざまなゲストを招き、これからのアートプロジェクトのためのヒントを探る、東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。その第15回が、2024年12月14日、「港区立男女平等参画センターリーブラ」にて開催されました。
港区の文化芸術施設や団体などを支援・育成するための取り組み「港区文化芸術ネットワーク会議」との共催で開催された今回のテーマは、「プロジェクトを広げる、“かかわりしろ”のつくりかた」。プロジェクトと、それにかかわりや関心をもつ人たちをつなぐ上で欠かすことのできない余白のありかた、つくりかたについて、語り合いました。
ゲストとして、水戸芸術館現代美術センターで1993年から続く、高校生を中心とした幅広い年齢層の市民とカフェ運営や部活動を行う企画「高校生ウィーク」などに携わる教育プログラムコーディネーターの中川佳洋(なかがわよしひろ)さん、そして、京都のまちで1998年より多種多様な人たちが集まる場づくりを行っている「バザールカフェ」のメンバー、狭間明日実(はざまあすみ)さんと、ソーシャルワーカーの松浦千恵(まつうらちえ)さんらが登壇。実践のなかで感じてきたことを話しました。
人と人、人と場をつなぐものとは何なのか? イベント当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。
(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:高岡弘*1-9、13枚目)

今回の「Artpoint Meeting」のパートナーである「港区文化芸術ネットワーク会議」(以下、「ネットワーク会議」)は、港区で活動する文化芸術施設や団体、企業などが交流、情報交換する機会として、2013年より定期開催されているプラットフォーム型の会議です。
2016年の開始以来、多くのゲストを迎えてきた「Artpoint Meeting」ですが、「今回は企画自体を、同様の活動を行い、近しい問題意識をもつ方と開催しようと思った」と、プログラムオフィサーの佐藤李青。この日のトークは、そんな佐藤と、この取り組みを主催する「港区スポーツふれあい文化健康財団」(以下、「Kissポート財団」)文化芸術部長の宮崎刀史紀(みやざきとしき)さんとの、イベントの背景を巡る話からはじまりました。

そもそも港区は、40を超える美術館・博物館や、30を超える劇場・音楽ホールを擁するなど、文化芸術施設が豊富な地域として知られています。「そのようにきくと、もはや公共サイドが文化芸術を支援する必要などないのではないか、と思われるかもしれません。しかし、そうではなく、公共だからこそできる支援があると思うんです」と宮崎さんは語ります。
その考え方の基盤を成すのが、港区が2024年3月に改定した、今後の区の文化芸術振興の方向性を示す「港区文化芸術振興プラン」です。

2021〜2026年度を計画期間としたこのプランでは、区が目指す将来像を、「多様な人と文化が共生し、文化芸術を通じて皆の幸せをめざす世界に開かれた『文化の港』」という言葉で表現。それを実現する上で進めていくべき施策を、大きく3つ記しています。
1つ目は「年齢・障害の有無・国籍等にかかわらず誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会の充実」。ここには多様な人に向けた鑑賞のサポートや、鑑賞機会のアウトリーチ活動などが含まれます。2つ目は「多様な主体間の協働による文化芸術振興」。そして3つ目が、文化施設の充実などを指す「文化芸術振興施策の推進に向けた基盤整備」です。
このうち、2つ目の施策の具体例として進められているのが、Kissポート財団による「港区文化芸術活動サポート事業」です。この事業では、区内で行われる文化活動や、その主体となる団体に対する助成を行うほか、専門家による活動へのサポートを実施。「ネットワーク会議」は、このサポートを受ける団体のつながりの場にもなっており、今回の「Artpoint Meeting」の会場には、同会議のメンバーも多く参加していました。

活動をサポートする対象について、宮崎さんは、「展示やコンサートのような一時的なイベントにとどまらず、その先の広がりを強く意識している団体を対象としています」とコメント。また、「ただ資金などを支援するのではなく、さまざまな人が交流することで、それぞれが気づきを得られる活動を目指してきました。そのためには、かかわりしろを広げることが必要。今日のイベントは、そうしたつながりを区の範囲を超えてもちたいとの思いから開催しました」と話します。

背景や関心の異なる人たちが「かかわりしろ」を通して交流することで、活動を厚くする文化活動のありかたは、東京アートポイント計画が大切にしてきたことです。佐藤は、そんな「かかわりしろ」についてゲストの話をきく際のポイントとして、①地域のなかで活動や場にかかわる「のりしろ」をどうつくるか? ②それが活動を「続けること」にどうつながるか? ③年代や属性などが「異なる」人とどうかかわるか? の3点を挙げました。
それを受けた宮崎さんは、「のりしろ」のうち、「余白を指す『しろ』も大事だけど、何かと何かをつなげる『のり』も大事。かかわるための仕掛けが重要なのでは」と指摘。会場の参加者に向け、普段の活動のなかで何気なく感じている感覚を、あらためて「かかわりしろ」という言葉で意識してほしいと呼びかけました。
続いて、「居場所であること、そこから広がったこと-高校生ウィークの取り組み」と題し、水戸芸術館現代美術センター(以下、水戸芸)の教育プログラムコーディネーター、中川佳洋さんの話をききました。聞き手は、認定NPO法人STスポット横浜の副理事長・事務局長で、港区文化芸術活動サポート事業の調査員である田中真実(たなかまみ)さんが務めました。

香川出身の中川さんは、大学進学で茨城へ。在学中の2008年から水戸芸にボランティアとしてかかわるようになり、今日のトピックである「高校生ウィーク」のカフェスタッフとして活動します。卒業後は香川の中学教員となりますが、「高校生ウィークのスタッフはみんな温かく、水戸を訪れるたび誰かが迎えてくれて。それで、2022年より水戸芸で働くことにしたんです」と中川さんは言います。

水戸芸は、全国的にも早い時期から教育普及活動やボランティア活動に力を入れた美術館として知られます。その背景には、1990年、主に現代美術を扱う国内2つ目の公立美術館として開館した歴史があります。同館には、当時では珍しく収集よりも企画に重きを置き、しかも展示されるのは「よくわからない」現代美術。「市民の方からは『(イメージしていた)作品がないじゃないか』という声もあり、そのなかで必然的に教育プログラムが求められた」と中川さんは説明します。
現在、同館では多くのプログラムが展開されています。例えば、ボランティアと作品を前に対話しながら鑑賞する「ウィークエンド・ギャラリートーク」、毎月異なる素材とテーマで老若男女がつくることを楽しむ集いの場「造形実験室」、視覚に障害がある人との鑑賞ツアー「session!」、シニア、認知症当事者・家族、ケア施設職員らが交流する「ブリッジカフェ」など。「学校訪問アートプログラム」や、作家の拠点を訪ねる「つくりてくらして」という館外活動もあります。

「高校生ウィーク」はこうしたプログラムのひとつとして、開館直後の1993年から現在まで続く企画です。もともとこの企画は、ハイティーン向けに発売された1000円の年間パスの販売促進のため、市内の高校生に水戸芸を体験してもらおうと、年に一度、学校別に一週間だけ高校生の鑑賞無料期間を設けるというものでした。
ただ、その後、企画の内容は状況に応じて変化していきます。1994年には無料期間が1か月となり、早くも「ウィーク」ではなくなります。1999年頃に、無料鑑賞だけではなく高校生自身が活動できるプログラムをやってみようと、まだあまり普及していなかったデザインソフトや大判プリンターによるポスター制作をする「広報プロジェクト」を開始。活動するなかで他校生徒や美術館スタッフ、ボランティアとのコミュニケーションが楽しいとの声があがり、その流れから2003年にワークショップルーム内に小さなカフェを設けたところ、お客さんとの交流から参加者の活動も拡大。2004年からは、1か月間、カフェが本格的にオープンすることになります。

また、2007年には「高校生ウィーク」内の企画として、「部活動」がはじまります。「3人寄ればブカツの提案ができる」をルールに、若者と大人、アーティストらが自主的な部活動を行うもので、「写真部」「書く。部」「聴く部」などが発足しました。2018年には高校生の入場料が無料となり、企画当初の高校生の無料招待期間という役目はなくなりますが、カフェは継続。コロナ禍による2年の休止を挟みつつ、現在は活動を再開しています。

カフェでは、無料の飲み物のほか、誰かのおすすめの本が並び、音楽がきこえて、来訪者と話したり、展示関連のワークショップに参加することもできます。もちろん、何もしないでボーッと過ごしてもOK。中川さんは2004年の「高校生ウィーク」のチラシにある、「いつもどことなく騒がしい身のまわりの雑音や情報から離れ、(中略)居心地よく過ごせる場所」という一文を取り上げ、「大事にしていることが当時からあまり変わっていない」と語ります。
そんな中川さんが、高校生から大人まで幅広いスタッフがいるカフェを運営するなかで大事にするのが、「まどろみの時間」と呼ぶ、カフェの閉店後の余韻の時間です。「すぐ帰ってもいいし、グダグダといてもいい。この余白の時間が、その人らしさを発揮したり、スタッフが仲良くなる上で重要だと思うんです」と中川さん。そんな時間が失われたコロナ禍を経て、活動を再開した際は、「この場所はお客さんだけでなく、スタッフのための場所でもあるんだと感じました」と振り返りました。

「高校生ウィーク」をはじめとした、水戸芸の一連の教育プログラムは、多くのボランティアによって支えられています。中川さんはこのボランティアという存在について、「いろんな経験や背景をもつ方がいて、かかわる動機も、かかわり方の頻度や濃度も、プログラムの数も人それぞれです。一回離れて、また戻ってくる人もいます。唯一の決まり事は、かかわり方はその人と相談しながら決めるということくらいです」と説明。美術館に多くの人が自主的にかかわる環境をつくる上では、関係の柔軟性が重要であることを示唆しました。
このように、参加者一人ひとりと丁寧で親密な関係を築くことの重要性は、中川さんの話のなかに通奏低音のように流れていました。例えば、田中さんから「活動を長く続ける上で大切にしていることは何か?」ときかれると、「心得というより、単純に高校生やボランティアの方と話すのが楽しい」と中川さん。「こんなにいろんなことを考えている人がいるんだ、その人のなかにこんな考えがあったんだと気づいた」と話し、それは教員と生徒という固定的な関係性になりがちな「教員時代には気づけなかったこと」だと語りました。
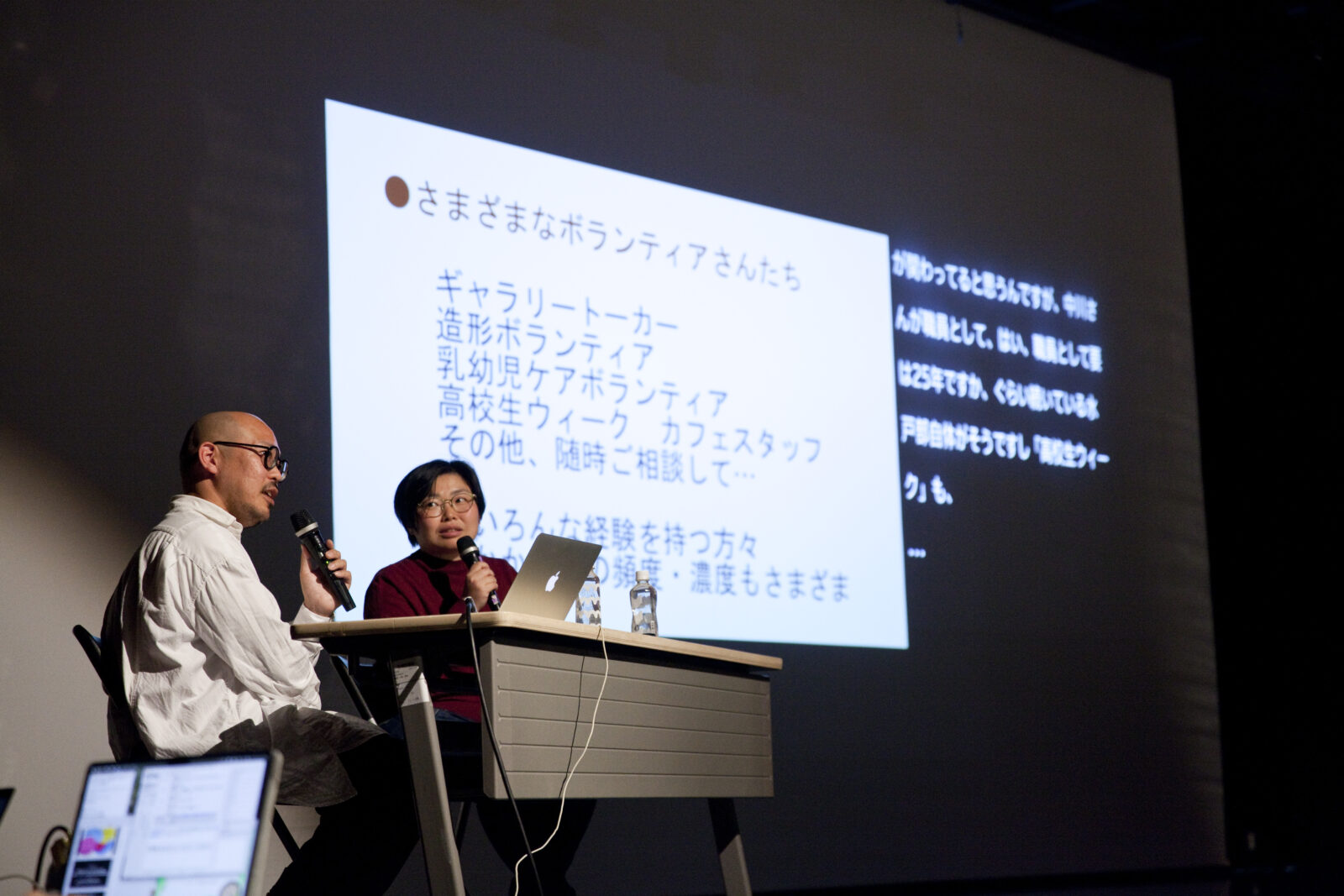
先の「まどろみの時間」に代表される、目的のない曖昧な時間を大切にするのも、個人のなかに生まれる小さな動きを大事にしているから。一方、その自由さは予期せぬ出来事を生む可能性もあります。田中さんから「やりたいことをやるのが基本だが、ダメと言う場合もありますか?」と問われると、「ダメとは言わないが、どうかなと思うことはある。でも、それも相談して決めるしかない。一旦離れる人もいるが、そのあとまた戻ってくるかもその人次第」と、あくまで個別性が大事だと話しました。
高校生や地域の大人、アーティスト、美術館の職員などが職能や立場を超えて集まる水戸芸の教育プログラム。中川さんは最後に、「いろんな人とのかかわりがおもしろいのは、ある人生のプロはその人しかいないから。それぞれに生きる一人としてかかわることを、教育プログラムではやりたい」と、あらためて強調。それをきいた田中さんは、「社会的な属性を離れて一人の人としてかかわる場になっている。そうした場は、実は少ないですよね。だからこそ水戸芸のプログラムはこんなに続いているんだと感じました」とまとめました。