
2024レポート③ 自分のアートプロジェクトに向き合う態度
執筆者 : 嘉原妙、和田真文
2025.03.31

演習「自分のアートプロジェクトをつくる」は、これからの時代に応答するアートプロジェクトのかたちを考えるシリーズ「新たな航路を切り開く」の一環として開催している、ゼミ形式の演習です。ナビゲーターはP3 art and environment統括ディレクターの芹沢高志さん。アートプロジェクトを立ち上げたい方やディレクションに関心のある方を対象としています。
2024年度は10月初旬から翌年2月初旬までの約4ヶ月にわたって行いました。
この演習の様子を、3つの記事でレポートします。
- 2024レポート① 対話を通して自分の問いを見つける
- 2024レポート② 3人のゲストの実践の風景
- 2024レポート③ 自分のアートプロジェクトに向き合う態度
演習「自分のアートプロジェクトをつくる」は、興味や問い、向き合うテーマなど、一人ひとり異なる背景を持つ人々が出会い、対話を通して自分自身の考えや視点に気づき、あらためてその考えや問いを軸に「自分のアートプロジェクト」の企画構想に取り組むプログラムです。対面講座でのディスカッションや受講生それぞれの発表に加え、講座以外の場としてオンラインツールを活用したコミュニケーションの場を設けています。
受講生は、他の受講生やナビゲーター、マネージャーとの対話や意見交換を通して、「自分の考えるアートとは何か」「なぜ、いまこの企画に取り組むのか」「アートプロジェクトを通して何を実現したいのか」といった、自らの問いを深めていきます。
演習は、全8回の対面講座(うち、最終回は2日連続で開催)で、ナビゲーターによる講義のほか、ディスカッション回や中間発表回があり、その間に3回のゲスト回を挟む構成です。今年度のゲストは、梅田哲也さん(アーティスト)、矢野淳さん(株式会社MARBLiNG代表)、阿部航太さん(デザイナー/文化人類学専攻/一般社団法人パンタナル代表)の3名。ゲスト回では、それぞれのゲストの経験を手がかりに、受講生はさまざまな視点からアートやアートプロジェクトの実践のあり方について考えていきます。さらに、各ゲストが、いまこの時代をどのように捉え、何をどのように表現しようとしているのかを知る回となっています。これらの講座を通じて、受講生は自分のなかにある問いを発見し、あらためて向き合っていきます。

2024年10月6日(日)、今年度最初の演習がスタート。例年通り、初回はナビゲーターの芹沢さんから、この演習の目的や内容について説明し、その後、受講生たちの自己紹介を行いました。なぜこの演習に参加したのか、現段階で構想している企画やアイデアについて共有しながら、一人ひとりの興味関心を軸に自己紹介が展開されました。
今年度の受講生もとてもバラエティ豊かな方々でした。海洋環境に興味を持ち、海と人の関わりをテーマに創作活動を進めている方、喪失体験や悲しみをテーマに表現活動を模索している方、日本の伝統音楽や民謡の作曲のデータベース化に取り組もうとされている方など、非常に具体的なテーマを設定し、実際に企画を始動している方もいました。
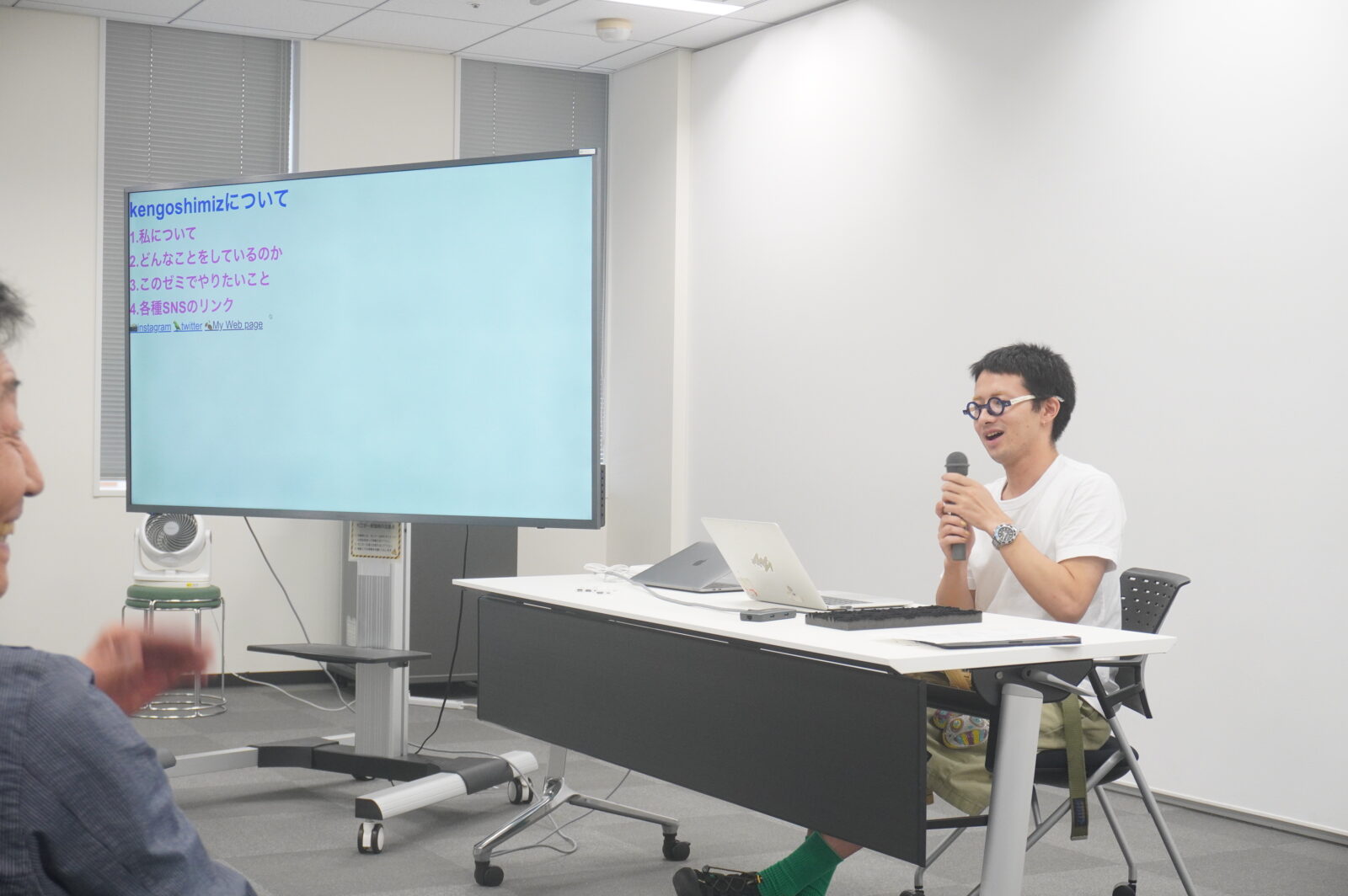
また、福祉事業に携わっている方やアーティストとして活動している方は、それぞれの活動のなかで、あらためて自分自身の取り組みを見直しながら、次の取り組みの一歩を探っている方も。さらに、映画制作や展覧会企画などさまざまな実践を積み重ねている高校生の受講も。

このように世代も興味関心も幅広く、それぞれバックグラウンドが異なる受講生たち。一人ひとりの自己紹介には、アートに対する可能性や期待、そして、まだかたちの見えないことに向き合おうとする際のドキドキと戸惑いの気持ちが滲んでいました。だからこそ、この演習を通して「きっかけを掴みたい」「何ができるのか、何をしたいのか考えたい」という受講生の強い想いが伝わってきました。
10月19日(土)第2回の演習では、ナビゲーターの芹沢さんより、まずは自身のアーティストとの出会いやP3 art and environment設立の経緯、これまで20年以上に渡り手がけられてきた国内の芸術祭について具体的な事例を交えて紹介されました。
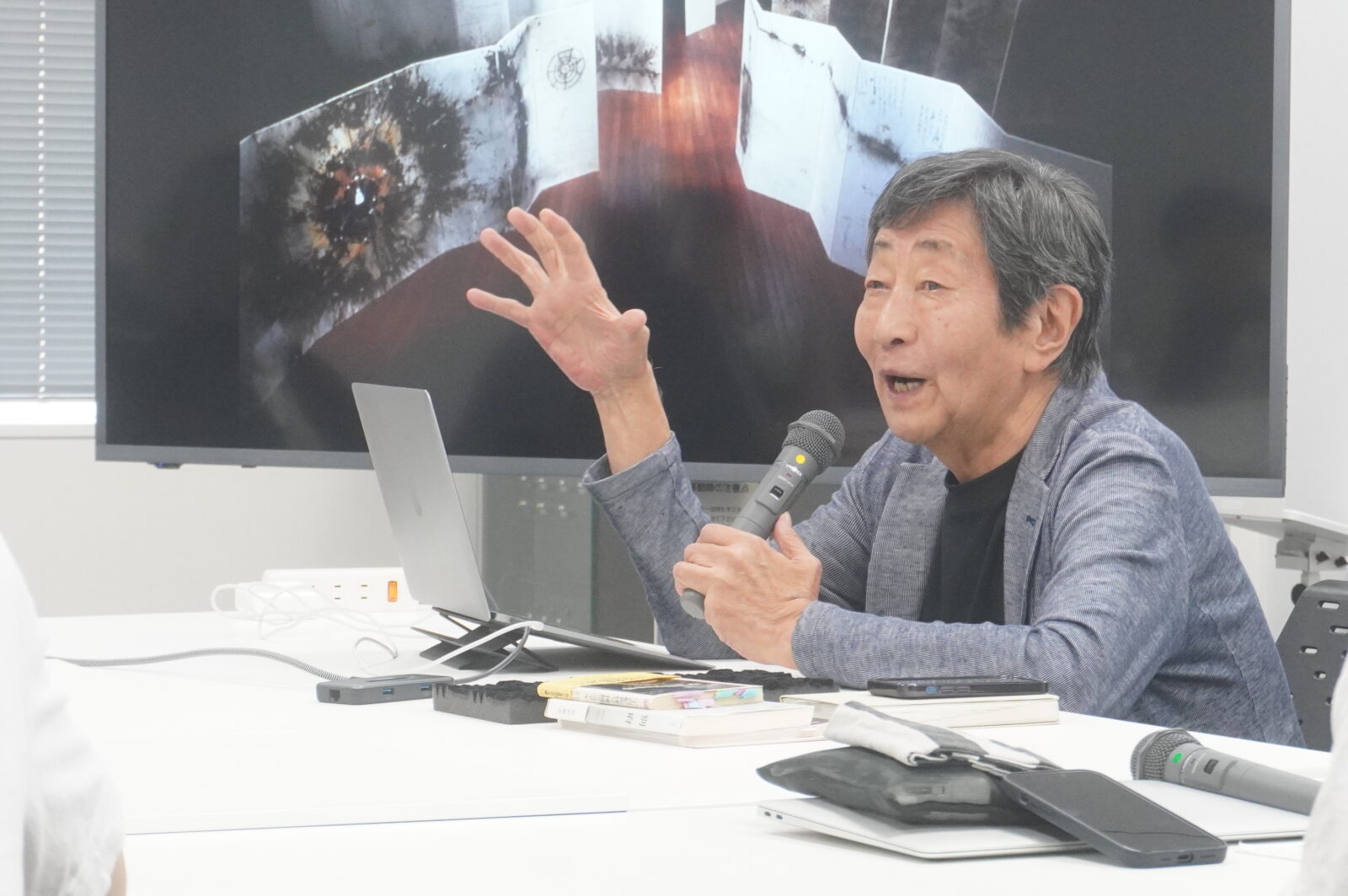
また、1927年にホワイトキューブの概念が生まれ、その後、ランドアートやハプニング、リレーショナルアートなど、アーティストの表現活動の場がストリートへと展開し、現在のアートプロジェクトにもつながっていく系譜についても解説。さらに、「アートはよくわからない」という言説にも触れ「アートは誰にとっても『わからない』という特質を持っていること、アートの前では、わたしたちは常に平等である」という視点が共有されました。

その後、森司(アーツカウンシル東京 東京アートポイント計画ディレクター)による企画構想のためのグループワークが行われました。ワークでは、「アートプロジェクトを企画構想するにあたって、自分の企画のなかで最も大事にしたいのは何か?」という問いかけからはじまり、「その場で、明日にでもすぐできる小さなプロジェクトを考えてみよう」「そのプロジェクトを実現させるために必要な技術と習慣を考えてみよう」といった、企画を考える前段の準備運動のようなワークが展開されました。

アートプロジェクトをつくる、企画を考えると言うと、アーティストをはじめ、さまざまな人がかかわる規模の大きな企画をつい想定しがちですが、「自分の」アートプロジェクトを考える場合、もっと身近なところからはじめてもよいのか、と気づきを得た受講生のみなさん。とはいえ、「自分の」アートプロジェクトとなると、はてさて何からはじめたらいいのかわからなくなってしまう人も多いでしょう。
森は、アートプロジェクトをつくるためには、「習慣と技術」が要になってくると言います。「アートやアートプロジェクトには、こうすれば正解だというルールがありません。自由すぎてわからなくなってしまう。だからこそ、自分にとっての羅針盤が必要です。それが自分自身の習慣と技術です」。繰り返し、繰り返し習慣化されているものがあるからこそ、日常のなかで不意に出会う違和感や機微にハッと気づいたりする。それが企画の出発点である「問い」になっていきます。また、自分が惹かれるアートプロジェクトを見つけた時は、どこが良いと感じるのか、それはどういった方法(技術)で行われているのかを分析し、学び続けることが大切です。

「みなさんが、これから取り組む演習は、自分がやりたいことをやるための『準備』。そして実は、その準備自体がアートプロジェクトとして成り立っていく可能性もあるんですよ」と森は言います。アートプロジェクトのイメージや規模について、受講生も意識をほぐされた時間となったようで、その後も活気のあるディスカッションが各グループで行われていました。
受講生同士で対話し、ゲストやナビゲーターたちとも議論を深めながら、自分のアートプロジェクトのかたちを探る演習は、こうしてスタートしました。