記憶・記録を紡ぐことから、いまはどう映る?―見えないものを想像するために

開催日:2020年2月19日(水)
ゲスト:佐藤洋一(都市史研究/早稲田大学社会科学総合学術院教授)、瀬尾夏美(アーティスト)
モデレーター:上地里佳(アーツカウンシル東京 プログラムオフィサー)
「いまの社会で、これからの実践を立ち上げるための新たな視座を獲得する対話シリーズ」として全4回にわたってひらかれる対話の場「ディスカッション」。各回にそれぞれテーマを設け、独自の切り口や表現でさまざまな実践に取り組むゲストを迎えながら「これからの東京を考えるための回路をつくること」を試みます。
最終回となる第4回のテーマは、「見えないものを想像するために」。ゲストには、記録の少ない敗戦直後の東京の姿を探るため、米軍やアメリカ人によって撮影された写真の収集・調査を行う都市史研究者の佐藤洋一さんと、東日本大震災後、宮城県仙台市を拠点に人々の “土地の記憶”の継承に取り組むアーティスト、瀬尾夏美さんのお二人を迎えます。
「今回のテーマを設定したきっかけとなる出来事に、昨年発生した首里城の火災があります。首里城はかつての琉球王国の象徴として名高い世界遺産ですが、私の地元である沖縄県宮古島といった離島側の歴史をたどってみると、『統治する/される』という関係性があったことが見えてきます。そのことを、火災を機に改めて考えるようになり、これまで見えていた『沖縄』とは違う側面を強く意識するようになったんです。
そこから、いま見ている風景や既知の出来事について視点をずらしたり、他者の記憶やまなざしを加えたりすることで、『いま』を捉えるための新たな回路をつくることにつながるのではないか? という考えに至りました。史実からはこぼれ落ちてしまうものごとを、どのように継承しうるのか。他者のフィルターを通して風景を眺め直したとき、『いま』の捉えかたはどのように変容するのか、といった問いが生まれました」(上地)
モデレーターの上地から、今回のテーマに至るまでの経緯が語られた後、ゲストお二人の活動を共有しながら、「記憶」や「記録」の継承という行為について考えました。
東京の歴史を「写真」から紐解く:佐藤洋一

「戦後の東京はどのような都市空間だったのか?」というテーマをもとに、東京の戦後写真を収集し、調査研究を行う佐藤洋一さん。もともと都市史を専攻されていた佐藤さんは90年代から写真の収集を開始し、戦後の東京の姿を網羅できる包括的な写真アーカイブズを制作するため、活動を続けられているそうです。収集しているのは、主に米軍やアメリカ人個人によって撮影された写真。近年では約9か月間にわたって全米各地の所蔵機関を巡り、調査の旅を実施されたといいます。こうした活動の経緯には、一体どのような背景があるのでしょうか。
「僕が学生の頃はバブルの真っただ中で、東京のまちの表情やかたち、匂いすらも目まぐるしく変わっていく状況がありました。その傍ら、ずっと東京で過ごしてきた祖父母からは、戦後直後のまちに関する話を聞く機会が多くあった。彼らの記憶のよりどころとなっている場所が大きく変わっていく様子を目の当たりにしたことで、戦後の『東京』というまちの姿をあらためて捉え直してみようと思ったことが、きっかけのひとつにあります」(佐藤)
しかし、いざ調べようとしたときに、なかなか体系的な資料が見つからない状況だったという佐藤さん。調べていくうちに、アメリカに戦後日本で撮影された写真や文書、地図などの貴重な資料が多くあることを知り、アメリカでの写真収集をはじめられたといいます。

そこから膨大な数の写真を調査していくうちに、日本とアメリカそれぞれで撮影された写真から「アメリカから見た“Tokyo”と日本人にとっての“東京”の差異も見えてきた」と佐藤さんは話します。
「写真は、実際に『何が写っているのか』ということに加えて、その写真が撮られた背景にはどのような意図があって、どんな行動がなされていたのかという撮影者の行為の記録を読み解いていく手がかりにもなります。視点が違うと、そこに記録されているものも随分と違うことが分かる。まだ見つけられていない潜在的な史料を掘り出し、写真の背景も語れる体系的なアーカイブを公開できれば、さまざまなイメージを見つけ出すこともできるし、戦後日本のイメージがどのように形成されてきたのかを問い直すこともできる。そして私たちの自己認識や歴史認識もきっと深まるはずだと思っています」(佐藤)
想起するための「身体」をつくる:瀬尾夏美

東北を中心に土地の人々の語りと風景の継承に取り組む、アーティストの瀬尾夏美さん。東日本大震災を機に岩手県陸前高田市に移住し、現在は宮城県仙台市を拠点に絵や文章の制作、ワークショップにプロジェクト運営など、さまざまな領域で表現活動を続けています。「震災後に東北へ移り住み、たくさんの人々の語りや、震災によって変わりゆくまちの風景に出会った。それらを記録し、残していく方法はないかと考えるようになったんです」と、活動の経緯を語ります。
「継承していく、というテーマの対象において、私がとくに関心を持っているのは、人々の『語り得ない』もの。人に出会うと必ず『語り』に出合うのですが、さまざまな環境や状況、人間関係のなかで、誰もが『語りづらい』こと、まだ言葉としてあらわれてこない『語り得なさ』を抱えています。そうした、いわゆる“記録”からは取りこぼされ残されていかないもの、でもきっとそこにあったはずの想いや感情、風景の記憶を記述していきたいと考えています」(瀬尾)
そう話す瀬尾さんの活動は、語りを引き出していくために必要な「対話の場づくり」からはじまるといいます。「自分と語り手の関係性のなかで一緒に『物語』を編んでいくような作業」と説明する作品《遠い火|山の終戦》の一端が、ここで語られます。
「震災の経験と併せて、戦争体験の話もしてくださる方に出会うことが多くありました。けれど、自分はそのときの時代背景が分からない。『話を聞く』ことがままならない状態であることに気づいた。そこで実践したのが、彼らの記憶に残る現在の風景を、自分の身体で歩き直すということ。とても単純な行為ですが、その場所に実際に行き想像をめぐらせることで、少しずつ想起できるようになっていくんです」(瀬尾)
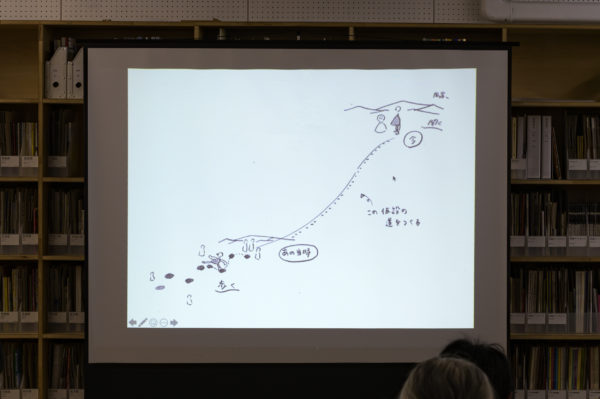
個人の語りの背景にある歴史を知り、風景を歩き直し、丁寧に向き合う時間をつくる。そうすることで「話を聞くことのできる身体」をつくっていったという瀬尾さん。その話に通ずるかたちで、映像作家の小森はるかさんとともに制作された《二重のまち/交代地のうたを編む》でのエピソードについても触れられました。
「この作品の発端は、復興工事で陸前高田のまちが嵩上げされ、新しいまちができたこと。土地に住む人々はかつてのまちの痕跡を失ったことで、次第にまちの思い出を語らなくなることがありました。その過去のまちと現在のまちをつなぐ手だてとなる何かをつくろうと思い、未来のまちの物語『二重のまち』を描いた。本作はその物語を、まちに滞在しながら4人の旅人に朗読してもらう、小さな”継承”のはじまりを記録した映像作品です。まちに訪れた旅人たちは、最初はただ目の前に存在する風景しか見えない。けれど、その土地の人と出会い、対話を重ねていくなかで、過去の風景を想起する準備ができていったんです。作品制作が終わり日常に戻った彼らが『まちのレイヤーを想像する身体に変わった』と話していたのが、とても印象的でした」(瀬尾)
「時間」の層を、意識する

それぞれの活動紹介を経て、ディスカッションへと移ります。まず、瀬尾さんのお話を受けて、過去−現在−未来という「時間軸」への意識について話題が挙がりました。
上地(以下、U):瀬尾さんの《二重のまち/交代地のうたを編む》は、2031年という未来の物語を通じ、旅人たちとまちの人のあいだで新たな語りや関係が生まれているのが印象的でした。この「時間軸」に対して瀬尾さんはどのような意識を持たれているのでしょうか。
瀬尾さん(以下、SE):どちらかというと私は、いま「同時代」に生きている人たちの話を聞き、残していくためにどうしていくべきかということに関心を持っています。なので、この作品も同時代的な試みとしてあるんです。被災者/非被災者という、震災に対してそれぞれ違う想いや背景を抱えた彼らが、個人と個人として出会うことができれば、より手触りのある形で互いのことを想像しようとしながら、じっくりと考える時間や語る時間が生まれるはず。いま現在の地点から、まちの「語り」と「風景」を共有していくことで、土地の人と外の人をつなげていくようなことができないか? 語りの往復のあいだに、このまちでの体験を継承できないか? と考え、同時代に生きる彼らをつなげられる道をつくるようなイメージを持っていました。
佐藤さん(以下、SA): 《二重のまち/交代地のうたを編む》は僕も拝見し、とても感動しました。基本的に自分の活動にある時間軸は、「今」と「過去」をどうつなげるかという直線的なもの。けれど、瀬尾さんの作品には、新しく生まれた「上のまち」と、かつてあった「下のまち」というレイヤーがあり、その二つのレイヤーを舞台にした未来の物語がまちの人に語られることで、時間軸が交錯し、いまの私たちを照らし出している。さらに、その物語がその場所で語られる映像を、いまの私たちが観ているという非常に多層的な構造の物語になっていますよね。記憶を継承していくためには時間の層を行き来できるような「物語」としての強度が非常に重要なんだと感じました。
いま目の前にしている対象のなかには、どのような時間が積み重ねられてきたのか。そのレイヤーを意識することが、「見えないものを想像する」「記憶や記録を紡ぐ」ためには重要なのかもしれません。そこから、さらに話が続いていきます。
U:「時間のレイヤーをまなざす」という視点を得る方法として、瀬尾さんは他者から受け取った物語の風景を自身の身体で「歩き直す」ことを通して実践されていました。同様に佐藤さんも、実際に写真が撮影された場所を訪ねて行くということをされていますよね。
SA:そうですね。写真を収集した後の調査として、それらの写真が撮影された場所にカメラを持って行き、同じ焦点距離と構図で同じように撮影する、ということも実践しています。すると、いろんな発見があるんです。たとえばこの構図で視点がこの位置であるということは、きっと石段に座って撮影したのだろうという確信ができる。撮影者の行動背景や興味関心、シチュエーションなどが見えてくるんです。撮影者の視点をなぞりながら想像を重ねていくことは、深い理解のために必要なことだと思います。
「フィクション」がもたらすもの
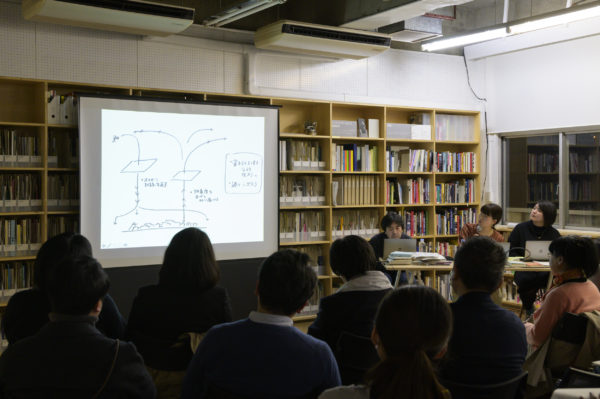
ディスカッションの後半では、参加者からの質問も交えながら進行していきます。ここで大きなテーマとして語られたのは、継承方法としての「フィクション」の役割について。参加者から挙がった「記憶・記録を継承していくことは、『フィクション』を通すことでしか成し得ないのか?」という質問をもとに、思考をめぐらせていきます。
U:何かを継承していくとき、そこにはいろいろな手法や幅があると思います。佐藤さんのように資料を集め、「事実」を網羅的にアーカイブすることで受け継いでいく方法もあれば、瀬尾さんのように他者の語りを自らの身体に引き寄せ、「フィクション」として別のかたちで表現することも、ひとつの継承のあり方です。お二人はその継承方法において、何か意識されていることはあるのでしょうか。
これを受け、瀬尾さんは「どんな作業でもどこかに編集を介するものなので、『フィクション』というものの境界をどこに設定するかにもよりますが…」と前置きしつつ、スライドに自身が描いた図解を映しながら解説していきます。
SE:アーカイブを残していく手法には、大きく分けて2種類の方向性があると思っています。それは、記録を「土地に返す」ことと「抽象度を上げて外に届ける」こと。前者は主に研究や資料保管として土着的に活用され、後者はいわゆるフィクションとして大衆に向かってひらかれていく。どちらもまちの資料を集め、分析推測をするという作業は同じですが、向かっていく方向や範囲が違うんです。私自身は、アーティストという立場で後者の手法を使い、「語り」や「風景」など、その土地固有にあるものの抽象度を上げることで、外部へとつなぐ回路をつくるようなことをしています。
さらに、どちらの方向も重要でありながら一長一短があると話す瀬尾さん。「土地に返しすぎると外部の人が介入しづらくもなりますが、その土地の人が記録物をまなざし続けるなかで自ずと“土地の物語”ができ、コミュニティも強くなっていくし、現物が残る可能性は高くなると思う」といい、こう続けます。
SE:一方で抽象度を上げる方法は、その真逆のことを引き起こします。土地との結びつきは弱くなるけれど、「語り」が変容しフィクショナルであるがゆえに広域に受け入れられやすい。そしてそれは、そのまち固有の物語としてではなく、別の土地の物語にもなり得る。ある出来事や記憶の“痕跡”が残りつづけていく可能性が広がっていきます。
SA:すごく分かります。その話でいうと、僕の活動は「土地を記録に返す」立場ですよね。今お話しされたとおり、土着化しすぎることで外部の人たちが触れにくくなるというのは往々にしてあることです。ときには、死蔵されてしまうこともある。そこはひとつの課題でもあります。
SE:なのでどちらかに完全に振り切るのではなく、分担しながらそのあいだの領域で協働できるような何かをつくれれば良いですよね。私にとっては、アーカイブが形成されていくあいだのプロセスが一番豊かな状況で、実は「フィクション」になるちょっと前の部分が重要なように思っています。《二重のまち/交代地のうたを編む》のプロジェクトも、外からの旅人がまちの人から話を聞き、完全には理解しきれないのだけど、そこで受け渡されたことを、もぞもぞとした心地のなかでゆっくりと自分の身体へ受け入れていく状況があった。そのあいだで起きているようなことが、フィクショナルとリアルな部分のつなぎ目として作用し、多くの人と出会える可能性を持っているような気がしました。
想像を重ねていく
さまざまな変遷を経たまちの風景、自分とは違う背景を抱えた他者の記憶。それらは、どこまでいっても「語り得ない/語り尽くせない」ものを抱え、時間の経過とともに改変されたり、忘れ去られ消えていくものでもあったりします。そうしたものを未来へと残そうとしたとき、私たちはどのようなかたちで継承していくことができるのでしょうか。
人々の「記録」や「記憶」を継承していく佐藤さん、瀬尾さんの実践はそれぞれに違う手法ではありますが、どちらにも共通しているのは、過去から現在、そして未来へと積み重ねられていく“時間のレイヤー”をまなざすこと。そして目の前の対象と丁寧に向き合い、繰り返し想像を重ねていくこと。そうしたものごとへ向かう態度が何よりも大切なのだと、お二人の対話から感じられました。見えないもの、分からないものを前提に抱えながら、その態度を持って多くの“想起の種”を掘り起こし、いま現在という地点につなげ育てていく。何かを継承していくという行為は、そんな風にさまざまなかたちで他者へと受け渡しながら、新たな物語を紡いでいくようなものなのかもしれません。
執筆:花見堂直恵
撮影:齋藤 彰英
運営:NPO法人Art Bridge Institute

