「拠点」とは何か? 秋田、神津島、神戸の事例を通して考える(APM#14 後編)
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19
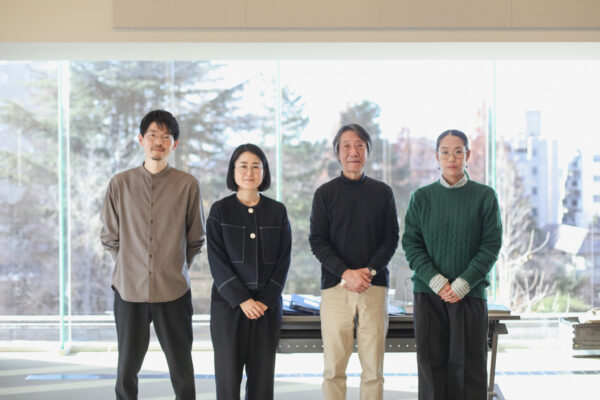

2023.09.07
執筆者 : 杉原環樹

「“わたしたち”の文化をつくる─成果の見方、支える仕組み─」後半のディスカッションの様子。
アートプロジェクトにかかわるゲストとともに、活動のためのアイデアや視点を深める東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。第12回は、「 “わたしたち”の文化をつくる─成果の見方、支える仕組み─」と題し、あらためて「アートプロジェクト」という営みそのものに着目。こうした活動が必要とされる土台や、判断が難しいその「成果」についての考え方を、国内外の事例と併せて考えました。
当日の模様を、ライターの杉原環樹が伝えます。
(執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:小野悠介*1-2、5、7-11枚目)
レポート前編はこちら>
英国と静岡の例から考える、アートプロジェクトの「成果」と「社会的意義」(前編)
「英国アーツカウンシル(Arts Council of Great Britain、以下ACGB)とコミュニティ・アートに関する小林瑠音さんの発表に続き、鈴木一郎太さんが発表を行いました。
20代をアーティストとしてロンドンで過ごしたあと、出身地の静岡県浜松市で障害のある人たちの表現活動をサポートする「NPO法人クリエイティブサポートレッツ」(以下、レッツ)など、表現と社会をつなぐ活動に従事、3年前から「アーツカウンシルしずおか」に勤める鈴木さん。「生活者が立ち上げるアートプロジェクトがグッとくる理由」と題し、公的な機関で文化芸術にかかわる立場から、その活動の社会的役割について話したいと述べました。

まず鈴木さんが紹介したのが「プロジェクタビリティ」の活動です。「プロジェクト」とそれを「推進する力(アビリティ)」を組み合わせた造語を冠するこの取り組みは、静岡文化芸術大学が中心となって2013年にスタートし、3年間にわたり行った研究事業です。浜松市内で活動する生活者による14のプロジェクトにヒアリングを行い、うち5つを詳細に調査。関連展示も行いながら、プロジェクトがおもしろくなるための要素を分析しました。
2013年には、市内の書店跡地で14のプロジェクトを紹介する「Projectability~この街で起きていることはとどうしておもしろいのか~」展を開催。鈴木さんは、このときアルミホイルの葉で床を埋め尽くし、来場者が歩くと自然に道や順路ができる仕掛け(会場構成:403 architecture[dajiba])を施したことに触れ、「道ができる過程が視覚化されたことは、プロジェクトという営みを展示する上で印象的だった」と語りました。

活動の2〜3年目は、プロジェクトの調査活動に注力。プロジェクトのおもしろさを評価するための指標の抽出を試みました。そのなかで、取り組みが魅力的になるための要素を大きく「横断する力」「開く力」「問う力」「工夫する力」の4つに分類。さらに、そのそれぞれにより細かいポイントを設定していきました。
鈴木:例えば、『横断する力』は自身が動いて異なる領域をつなげる力なのに対し、『開く力』は自分たちのもとに来る異なる存在との出会い方に力点があります。また、『問う力』は社会や自身の活動を客観的に分析し、いい意味で悶々と自問自答する状態にあるかを指し、『工夫する力』は予算など限りある資源のなかで楽しみながらやりくりする力を指します。こうした要素をもつプロジェクトは魅力的であることが多い状況が見えてきました。

続けて鈴木さんは、プロジェクトと生活者の関係に注目しました。
鈴木さんは、静岡のような地方都市でまちおこしやプロジェクトに関心をもつ人は、「個人的な思いや生活に密着したところから取り組みを立ち上げ、仕事ではなく生活者として活動にかかわっている場合が多い」と指摘。そして、この「生活者」の意識こそがさまざまな意味で重要だと話します。なぜならそこでは、良くも悪くも個人の資質によって活動が左右される傾向があるからです。
鈴木:例えば先の『開く力』のような他者を受け入れる能力は、人によってはごく自然に備わっているものでしょう。ただ、それが職業的な能力であるという意識がないと、ときに何もかもを受け入れてしまい、何の活動かわからなくなってしまうこともある。また、『問う力』も、個人の思いが強すぎると暴走が起きてしまいがちです。そこで重要なのは、そうした生活者個人の資質や動機を土台にしつつも、そこに補足として客観的な視点を載せてあげること。そうすると活動が社会化され、プロジェクトで行う意義が出てくると思います。
さらに鈴木さんは、生活者が目の前の切実な状況から創造性を発揮した例を、そのままでは食べられない「こんにゃく芋」を、人々が工夫して食べられる「こんにゃく」に加工したという「こんにゃく創世の仮説」になぞらえて紹介。その生活者の試行錯誤に対し、周囲には批判する人や後押しする人、専門的な知識を与えた人もいたはずと述べ、プロジェクトで起きることを身近な例で説明しました。
偶然発見された食べ物とは違い、こんにゃくのような加工品には明らかに人々の試行錯誤の跡があります。鈴木さんは、「こうしたトライ&エラーを厭わない姿勢こそが、予定調和を崩し、周囲の人の創造性を刺激する」と述べ、自分自身がはじめた試みを社会化して他者と共有する上では、試行錯誤の態度が鍵になると指摘。そうしてある人の行動が他者を刺激するところに、鈴木さんの生活者への関心があると話しました。

鈴木さんによる生活者の創造性の話は、小林さんが話したコミュニティ・アートの話題と多くの点で共通していました。
鈴木さんは、一般に創造性がアーティストの特殊能力のように言われたりする状況に違和感があると語り、生活者がこんにゃくをつくったように、「創造性は誰にでもある」と話します。そして創造性の表れは必ずしも「作品」のかたちをとるとは限りません。例えば、時間のやりくりや事業のつくり方、会話の仕方がクリエイティブな人がいるように、それぞれの人が社会にアプローチするなかで、すべての市民の創造性は既に表現されています。これはまさに、英国のコミュニティ・アートが問い直した、芸術と「わたしたち」の距離感をめぐる視点でしょう。
鈴木:こうしたなかで、僕自身は限られた文化芸術というより、いろんな人の創造性がいかされる道を探っていきたいと思っています。ただ、誰がそれを後押しするのか? 美術や舞台や音楽などには業界がありますが、市民の創造性を育むためのお金は、公的な資金を投じるよりほかないのではないか。そこに、アートプロジェクトの公的な役割があるのだと思います。
最後に鈴木さんは、そうしたプロジェクトを動かす上で重要となる「つなぎ役」について話をしました。
個人の思いからはじまるがゆえに、ときに属人的になったり、客観性に欠けていたり、閉じたものになりがちな生活者によるプロジェクト。そこで重要なのは、地域にあるほかの企業や団体、個人と連携していくことであり、そのときに求められるのが、文化芸術と、地域や産業、まちづくりに関する知見をある程度幅広くもっており、両者をつなぎ合わせることのできる存在です。
ただし、個人がそれらに満遍なく精通することは現実的ではないかもしれません。そこで鈴木さんは、文化芸術側のことをよく知るアートディレクターやマネージャーと、市民や産業側のことをよく知る「住民プロデューサー」という、二種類のつなぎ役がいることがベストではないかと提案します。実際、静岡では「住民プロデューサー」という存在をプロジェクトのなかに位置づけており、支援を通じてその育成を進めていると言います。

「生活感覚とクリエイティビティの組み合わせは、その接続の仕方でさまざまな活用の可能性を広げられるはず」と鈴木さん。その発表には、多くのプロジェクトをそばで見てきたからこその、実感のある、じんわりと響いてくるような視点が盛り込まれていました。
イベントの後半では、小林さんと鈴木さん、最初に話した佐藤李青に加え、東京アートポイント計画プログラムオフィサーの大内伸輔が参加。東京アートポイント計画のこれまでの取り組みを解説したのち、会場の声も拾いながら、前半の内容も踏まえたディスカッションが行われました。

その冒頭では、鈴木さんの発表の最後に言及された「住民プロデューサー」など、芸術文化と社会のつなぎ役となる存在への質問や発言が集まりました。
アーツカウンシルしずおかの住民プロデューサーは、主に「マイクロ・アート・ワーケーション」(以下、MAW)という事業のなかで与えられる役割です。MAWは全国から公募した「旅人」と呼ばれるクリエイティブ人材(アーティストやキュレーター、アートディレクターなど)と、地域住民や地域団体をマッチングし、その交流を支援する事業。このなかで、現地に滞在する旅人を迎え入れるホスト役が住民プロデューサーとしての役割を担います。
その担い手は半数以上がまちづくりにかかわる人たち。鈴木さんは、「かれらは芸術文化の専門家ではないけど、まちの事情に精通している。旅人との交流を通し、その可能性をまちでいかしてもらえたら」と、まちのプロがアーティストらと出会う重要性を話しました。
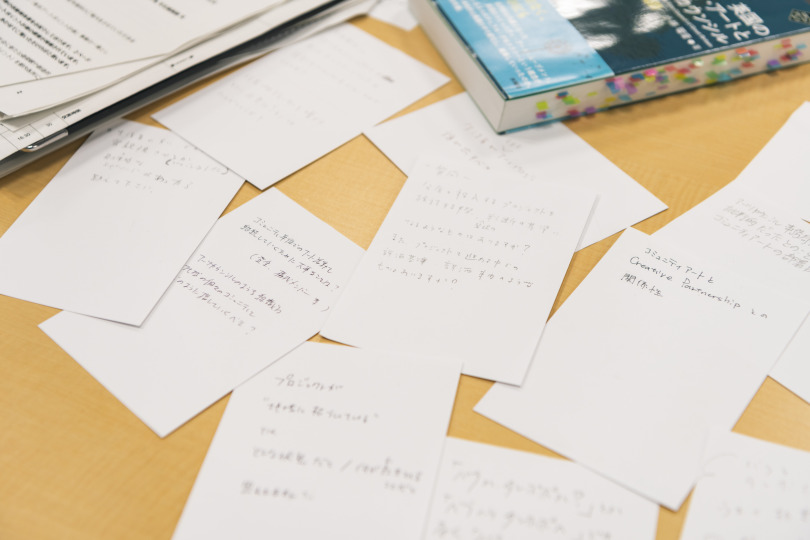
これをきいた小林さんは、英国のコミュニティ・アーティストたちにも、さまざまな領域や関係者の間に立ってそれらを媒介する意識があったと話をつなげます。こうした存在を表す言葉が、「アニマトゥール animateur」です。これは、もともと1970年代のフランスで政策的に後押しされた、異なる領域をつなぐ「職業」のこと。それが文化芸術の分野にも応用され、英国にも伝播し、「カタリストcatalyst」(媒介者)という呼称でも広がりました。
小林:実際、わたしが話をきいたかつてのコミュニティ・アーティストたちには、自分はアーティストではなくてプロデュサーやディレクターのような立場だったと話す人が多いんです。もちろんプロの芸術家としてかかわる人たちも多かったのですが、いずれの場合にもコミュニティ・アーティストの役割を説明するときに『アニマトゥール』や『カタリスト』という言葉が頻繁に使用された。それも注目すべきことだなと思います。
さらに小林さんは、鈴木さんが発表で指摘したように、個人の領域として閉じたものになりがちな地域プロジェクトにおいて、こうしたつなぎ役が社会との接点を調整することの重要性を指摘します。それに対して鈴木さんも、「コミュティをひらくとよく言うけど、コミュニティは閉じているから居心地がいい。でも、閉じたままでもいけない。つなぎ役の人たちには、その開閉の塩梅をとるという感覚が必要」とコメント。プロジェクトのよいあり方と社会性を担保する上での、つなぎ役の大切さが共有されていました。
質問のなかには、小林さんが話したACGBに触れるものもありました。なかでも興味深かったのは、「数本のバラか、路傍のタンポポか」という二項対立的な問いに対し、その中間をとるようなものはなかったのか、というもの。

これに対して小林さんは、バラとタンポポという比喩は、英国の文化政策において頻繁に使用されてきた重要な表現だが、大前提として、何がバラで何がタンポポなのかという定義の問題も含め、個人的には違和感があるとしつつも、ここで重要なのは、文化政策についての議論を促す基準として、このふたつのフラグ(旗)を立てたことだ、と返します。
小林:これらのフラグが立ったことで、例えば、いまはバラとタンポポが7:3になっているから少しタンポポの方に力を入れようといったかたちで、領域間のバランスを調整する意識が高まった。もちろん両者が共存する状態が理想だが、こうした、誰もがイメージしやすいモチーフを使いながら政策を議論し、自分たちの立ち位置を確認することができるようになった点が、まず大きかったと思います。
加えて小林さんは、近年の英国ではそうした中間的な取り組みも行われているとし、一例として2002年から開始された「クリエイティブ・パートナーシップ」という教育プログラムを挙げました。これは、学校がアーティストや建築家、科学者らと連携を結び、その人たちを学校に派遣するなどして、こどもたちの芸術性や創造性につなげようというものです。
このように、現代の英国で非常に重視されている「アウトリーチ」の概念が広く浸透した背景のひとつには、直接的ではないものの、かつてのコミュニティ・アートの影響があると小林さん。特筆すべき事例として、テート美術館の館長として英国におけるアウトリーチ活動の発展に大きく貢献し、現在はアーツカウンシル・イングランドの会長を務めているニコラス・セロータ氏が、実は駆け出しの時代に、ロンドンのイーストエンドで開催されたコミュニティ・アート・フェスティバルにかかわっていたという点を挙げました。半世紀近く前の活動の影響がじわじわと、さまざまに現在の文化政策につながっているのです。
最後に、今日の話を踏まえて、登壇者たちはどんなことを考えたのでしょうか?
鈴木さんは小林さんのバラとタンポポのフラグの話が印象的で、「振り返るとアーツカウンシルしずおかではタンポポに振り切った活動をしてきた」と言います。その理由には、設置が検討されていた頃の第3期ふじのくに文化振興基本計画で、「みる」「つくる」 「ささえる」の3つの基本方針が掲げられていたことがあるそうです。

鈴木:ワーキンググループに参加したとき、静岡ではこの3つに関して非常に多くの取り組みが行われていました。でも、バラ的な芸術を支えることも重要だけど、いまは文化が社会を支えるという視点が大事なんだと思ったんです。そこで、うちではタンポポ的な活動を重点的に行ってきたのですが、これも永続的なものではない。固定的な理想ではなく、状況を見ながら常に活動のかたちを変えていくのが自然なんだと思いました。
これに大内もうなずき、「活動がマンネリ化するより、変わっていくことが大事。プロジェクトで育んだ要素をもった人がいろんな場所に散らばって、それぞれの場所で変化しながら活動していくのがおもしろいと思う」と共感。それは東京アートポイント計画でも感じることだと言い、そうした種をもつ人が増えていけば、「文化をつくる人が増えていく」と話しました。
また佐藤は、鈴木さんのこんにゃくの例に触れ、「こんにゃくをつくる人だけでなく、それを売る人や活用する人もいる。プロジェクトでも、直接的な担い手だけでなく、そこにかかわる幅広い関係者を対象にした成果の見方が必要だと感じた」と感想を述べました。
最後に小林さんは、ACGBを研究する立場から、この日会場の廊下に並べられていた東京アートポイント計画の発行した数多くの冊子に触れ、「このように、よくわからなくてモヤモヤした気持ちを言語化して共有する取り組みは素晴らしい。世界一丁寧なアーツカウンシルだと思う」とコメント。その上でこの資料を海外のアーツカウンシル関係者にも紹介していきたいと感じたと話し、「多言語化によって海外からの評価を得る道もぜひ検討してほしい」と述べました。

異なる時代や地域の取り組みを通して、東京アートポイント計画や市民によるアートプロジェクトの価値について考えた今回のイベント。そこには事情は異なれど、共通する文化政策的な論点や市井の人々の思い、求められる姿勢があったように感じます。そしてとりわけACGBの例が示しているのは、暫定的であっても自分たちの価値観を言語にし、残していくことの大切さであり、それが時を経てもつ意義があるということでした。
今回のイベントで紡がれた視点は、今後の東京アートポイント計画にどのように反映されていくのでしょうか? 今後も見続けたいと思います。
レポート前編はこちら>
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19
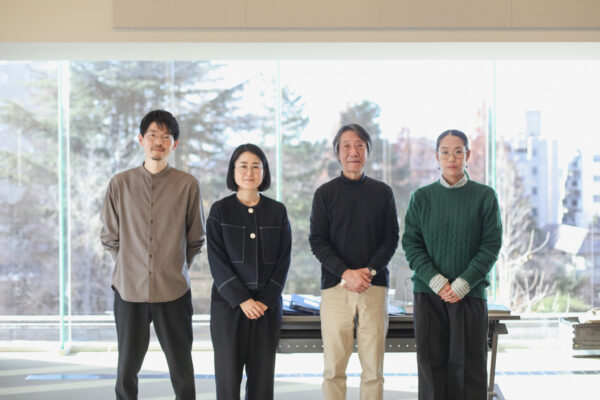
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹
2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹
2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹
2023.09.07
