「拠点」とは何か? 秋田、神津島、神戸の事例を通して考える(APM#14 後編)
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19
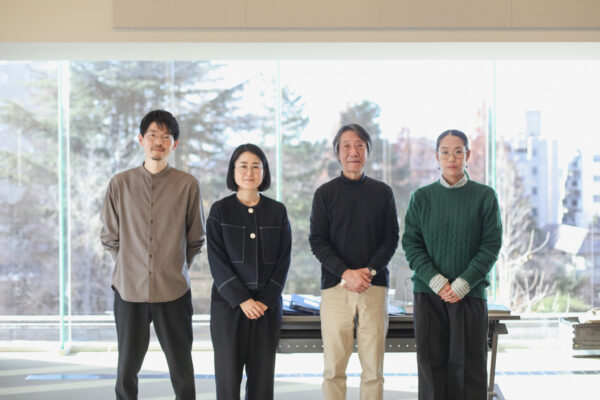

2024.02.15
執筆者 : 杉原環樹

「Artpoint Meeting #13 災害の“間”をたがやす」後半のディスカッションの様子。
毎回、アートプロジェクトにかかわるひとつのテーマを設定し、ゲストとの対話を通して思考と問いを深めてきた東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。その第13回が、2023年10月22日、東京都・江東区の東京都現代美術館で開催されました。
今回のテーマは、「災害の“間”をたがやす」。災害のあとの時間を「災後(さいご)」と呼びますが、各地でさまざまな自然災害が発生し、気候変動の危機が叫ばれる現在、わたしたちが生きているのは災害と災害の間、すなわち「災間(さいかん)」の時間なのではないか。そのとき、わたしたちは今後の災害に備え、あるいは過去のダメージから回復していくよすがとして、この災間の時間をどのように過ごしていけばいいのか。今回はそうした問いを、二人のゲストと考えました。
一人目は、京都大学防災研究所教授の牧紀男(まきのりお)さん。牧さんは、防災や復興を学問的に研究すると同時に、東日本大震災後、岩手県災害対策本部で情報処理の支援を行うなど、被災地の支援活動にも注力してきました。もう一人は、アーティストの瀬尾夏美(せおなつみ)さん。東日本大震災を機に東北に移り住み、およそ10年活動してきた瀬尾さんは、近年、各地の被災地に残る記録や記憶をつなぐことを目指すプロジェクト「カロクリサイクル」も展開しています。
異なる立場から、災害と、被災地に生きる人たちの姿を見つめてきた二人の言葉が交わされたイベント当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。
(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1-3、8、9、11-13枚目)
レポート前編はこちら>
災禍の経験を共有するために、文化ができること(前編)
牧さんよりバトンを受け取り、続けて登壇した瀬尾さんは、自身のこの10年ほどの活動を振り返りつつ、そのなかで考えてきた「被災者の声をきくこと」について語りました。

東日本大震災があった2011年3月、瀬尾さんは東京藝術大学の学生でした。震災後、「地続きの場所で起きている災禍に対して何かできないか」と、同級生で映像作家の小森はるかさんとともにボランティアで岩手県の陸前高田を訪問。その土地が好きになり、翌年二人で移住し、3年を過ごします。その後、2015年には仙台に拠点を移し、「土地と協働しながら記録をつくる組織」である一般社団法人NOOK(のおく)を設立。東北を中心に、被災地の変化やそこに生きる人たちの声を追ってきました。そして2022年からは故郷の東京に戻り、江東区を拠点に、後述する「カロクリサイクル」などのプロジェクトを展開しています。
自身の活動は、絵や文の制作を行う個人としてのアーティスト活動、小森さんとのユニット活動、NOOKの活動の3つに分かれるといいますが、どれにも共通するのは「他者の言葉を書く(≒記録する)こと」だと話します。またその方法論として、「語りの発生する場所そのものをつくり、そこで生まれた言葉を記録し、描きなおす」点も共通します。
話をきく対象としては、被災者のような特別な体験をした人も多いのですが、それだけではありません。なかには「被災者」とはっきり括ることが難しい人や、震災から10年目の東京で震災の記憶が薄れることにモヤモヤしている人もいます。

そうしたなか、特化してきたのが「災禍の語りをきくこと」です。きっかけとなったのは、東日本大震災から3週間後の4月3日、訪れた陸前高田で、大学時代の友人の親戚である女性の話をきいたことでした。その女性の家は海を望む高台にありましたが、庭まで津波が到達し、下にあった家々は被害に遭ってしまいます。そこで彼女はこう語りました。
「わたしもいっぱい友達亡くしてしまったの。でも津波のあとはね、涙も何も出なぐなってしまった。それでもこのごろやっと落ち着いたら、あーって悲しみが出てくんの。して、なんでわたしが生き残っちゃったのかなあって、思うの」
「でもみんなの世話をしてればね、いくらか気も紛れるから。うちはこうしてね、水も出るし電気も出るから、みなさんにかえって申し訳ないくらいなの」
女性の語りには、自身の感情の吐露とともに、周囲への思いも含まれていました。そして女性は瀬尾さんに、「いまの話を誰かに伝えてね」と言ったといいます。瀬尾さんは、被災経験の語り手の多くが言うこの言葉を「真に受けて」、活動を行ってきました。
さらに、彼女の話をきくなかで瀬尾さんが感じたのは、「東京にいた自分は震災と距離があると感じていたけれど、被災地にも、亡くなった人や津波に流された人もいれば、現地にいながら深刻な現場に立ち会わなかった人もいる」ということでした。言葉では当事者と非当事者と単純に分けられるけれど、現実には、その中間にグラデーションが広がっている。こうした気づきのなかで瀬尾さんは、「当事者/非当事者と分けていくと、自分よりも被害を受けた人がいると感じて、誰も語れなくなってしまう。だから、当事者だけが語るのではなく、このグラデーションをみんなでつないで、一番の当事者である亡くなった人のことを忘れないように語り続けることが大事」だと感じたと話しました。
当事者か非当事者かという区別を超え、ともに語る場をつくる上で、瀬尾さんはアーティストである自身のポジションを、「体験者(語り手)や災禍のあった現地と、非体験者をつなぐ旅人(聞き手)」だと表現します。そして、そうした自身の活動は、「体験者や現地と出会うこと」「そこできいたことや見たことを記録すること」「展覧会や制作を通じてそれを受け渡し、共有すること」のサイクルであると説明しました。

瀬尾さんが小森さんと制作した作品『波のした、土のうえ』(2014年)も、そうしたサイクルのなかでつくられたものです。嵩上(かさあ)げ工事がはじまり、かつて暮らした地面を埋め立ててしまうことに対して強い喪失感があった時期に、地域住民と一緒に制作した3編の映像からなる作品で、二人は同作を含めた展覧会をつくり、全国10か所を巡回、対話の場をひらいてきました。そのなかには阪神・淡路大震災の被災地である神戸もあり、見た人から神戸と陸前高田の共通点が挙がったり、当時を知らない若者が陸前高田を通して神戸の経験を知ったりと、新たなつながりが生まれる機会ともなりました。

一方、陸前高田の嵩上げ工事が終わり、風景が街らしさを取り戻したことで、津波が話題に挙がる機会が減っていました。また、展示の巡回中、震災時にこどもで、その後大人になった世代から、当時のことを知りたいと言われることも増えていました。映画『二重のまち/交代地のうたを編む』(2019年、以下『二重のまち』)は、そうした声を受けて「語り継ぎ」の機会を設けたプロジェクトから生まれた作品です。

このプロジェクトでは、公募で集まった被災地ではない場所に住む四人の若者が、陸前高田に15日間滞在して街の人の話をきき、それを自分なりの言葉で再び被災者に伝えるという複雑なプロセスが取られました。いわば、他者の体験を自分で受け止め、継承していく体験であり、牧さんはその「ぐるぐるした」語りのサイクルに、非当事者が当事者の体験を引き受ける上で大切な「翻訳」を感じたのでした。
こうした活動を行うなかで、瀬尾さんの認識を揺さぶる出来事が起きました。2019年10月に発生した台風19号による、宮城県丸森町(まるもりちょう)の土砂災害です。瀬尾さんはこの町に、民話の記録を50年間続けてきた「みやぎ民話の会」の活動を手伝うかたちで出会い、その後は個人的に訪れ、戦争の語りをきいたり、現地で絵を描いたりしてきました。そんな自分が描いていた町が土砂に埋まってしまったことに、瀬尾さんは大きな衝撃を受けます。そして、「自分は『災害』というと東日本大震災ばかりを頭に浮かべていたけれど、それ以外の災害や場所のことが見えていなかったと感じた」と話します。

丸森町で土砂災害が起こった背景には、戦後の開発で山の管理ができなくなったことや、自然エネルギーへの転換で山にソーラーパネルが建てられたこと、沿岸部の埋め立てで土砂が採られたことなど複数の原因がありました。けれど、町内でも被害を受けたエリアが局所的だったため、災害から2年後の2021年には、当時のことを話題にする機会が少なくなっていました。そうしたなか丸森町で何かできないかと考えた瀬尾さんや小森さんは、こうした町の状況を町民たちと話す機会をつくれないかと考えます。そうした活動の結果生まれたのが、『台風に名前をつける』(2021年、以下『台風』)という映像作品です。

もともと民話が盛んな地域である丸森町には、明治3年に起きた台風災害に基づく「サトージ嵐」という話が残されていました。これは、サトージという大泥棒を処刑したあとに災害が起きたことを受け、その台風を「サトージ嵐」と名づけた物語です。この民話を参照しながら、瀬尾さんたちは六人の町民と2019年の台風に名前をつけようとします。
「Artpoint Meeting #13」の当日は、25分にわたる同作を全編上映しました。映像のなかでは、さまざまな背景をもつ六人の町民が車座になり、土砂崩れが起きた日やその後の体験、山が弱くなった原因をそれぞれの知見から語ります。映像の中盤、今回の災害で友人を亡くした女性が、この経験を忘れないように台風の名前をつけようと提案。昔の土砂崩れの呼び名「じゃく抜け」から、名前は「じゃく抜け台風」に決定します。そして、家を失った参加者が、集団移住先でこの体験を伝えていこうと語り合うシーンで映像は終了。映像からは、個人の経験が、語りを通して周囲に共有されていく、豊かな対話の姿が感じられました。
二人の発表のあとは、冒頭にマイクを握った佐藤李青も加えた三人で、会場からの質問も交えながらトークセッションを行いました。

瀬尾さんと小森さんの映像を見た牧さんは、「二人の映像のファン」と語り、その魅力を「説教臭くないところ」と言います。「我々はどうしても教訓を言いたくなるけど、二人の作品はそうではない。それが災禍を伝える上で大事なんだと思う」。そして、こうした対話の場をつくる上で心がけたことについて、瀬尾さんに尋ねました。
これに対して瀬尾さんは、陸前高田に移住した頃から、基本的に報道で拾われないことをいかに拾うかを意識しているとし、『台風』においてそれは丸森町の人々の知性的な面だった、と話します。「丸森では、避難所の時点で、みんなで知識を共有して話すことをしていました。被災者=困っている人というイメージになりがちだけど、自分たちで論理的に解決策を話すことができる人たちであることを映像に残したかったんです」。
また、自然な対話の場をつくるうえで、多様な知見をもつ人たちを集めたことや、みやぎ民話の会でも活動する住民の女性に進行を頼んだこと、「台風に名前をつけたうえで、何を伝えて残したいかまで話そう」とだけ決め、当日、瀬尾さん自身は板書役に徹したことなどの工夫を説明。そして、丸森が民話の盛んな地域であることも、この語りの豊かさにつながっていると話しました。
このような、語りを通じてイメージを共有することに慣れた丸森の特性は、現地を離れた東京都写真美術館(以下、「写美」)で活動の紹介をする展示(「記憶は地に沁み、風を越え 日本の新進作家 vol. 18」、2021年)を行った際にもいかされたと瀬尾さん。ここから話題は、ある土地の災害をべつの場所で伝える上での工夫へと移りました。

瀬尾さんは、写美での展示にあたり、「丸森の土砂災害が首都圏とつながっていると示すことを心がけた」と話します。丸森に被害をもたらした台風19号では、首都圏の被害も不安視されていました。「メディアでもすごく東京の被害を心配していたけど、実際に被災したのは地方の山間地や川沿いの地域でした。同じ規模の台風が通っても、都市では被害が出にくい。それは地方より、防災インフラが充実しているということですよね。一方で、都市部のために山間地にソーラーパネルが設置され、開発に伴う木々の伐採が進んで土砂災害を引き起こした。それらをあわせて見せることで、つながりを見せたいと思いました」。
一方の牧さんは、さまざまな被災地を見てきた立場から、それぞれの土地には独自の個性があることに触れ、瀬尾さんたちの作品の魅力はそうした土地の性質を上手くいかしている点にあると言います。瀬尾さんは発表のなかで、海に近い陸前高田と山間の丸森の住民を比較し、前者は個人的な語りが上手く、後者は知識の共有が上手いと感じたと話していました。この実感から、陸前高田での『二重のまち』では個人の語りが、丸森での『台風』ではコミュニティの語りに焦点が当てられています。牧さんは、こうした旅人の土地を見る目利き的な力も、外部の人に災害を伝える上で重要な働きをしていると語りました。
トークのなかでは、時間と語りの関係をめぐる話題も出ました。
瀬尾さんは震災から1年も経たない頃、地元コミュニティにはまだ話すべきことがあるのに、非当事者には既に震災の話に対する「お腹いっぱい」感があったと振り返ります。他方、当時こどもだった世代があとから震災の話をききたがるように、時間が経つことで非当事者の関心が高まることもある。このように、土地の内と外、当事者と非当事者の関心のタイムラインは常に変化しつつズレているものですが、「それらが触れ合ったときに、いい出会いが生まれることもある」と瀬尾さん。だからこそ、その変化の見定めが大切だ、と語りました。
さらに瀬尾さんが「地元の人も時間が経ったからこそ喋れる場合がある」と話すと、牧さんもこれに頷き、「災害の経験は物理的な経験だが、その後の語りは自分のなかで常に変わっていく。唯一の真実があるわけではなく、感じ方や考え方が変わっていく。逆に言うと、変わることで人は生きていける」と、人にとっての変化の重要性を指摘。「自分の経験を客観視して喋ることができたとき、ようやく“復興”になるが、機会をもらうことでようやく喋れる人もいる。だから、喋る機会や場があることが大事」と話しました。

セッションの終盤は、今回のトークの背景でもある文化や表現の可能性に触れるような発言も飛び交いました。
絵や物語や映像などさまざまな手段で制作する瀬尾さんですが、「メディア」についての問題意識を問われると、自身のなかで考え方が変わった出来事に、2014年にみやぎ民話の会に出会ったことがあると答えました。このとき瀬尾さんにとって印象的だったのが、同会の代表の小野和子さんが、民話を語る人たちは、どんなに不思議なお話でも「あったること」(ほんとうにあったこと)として語り、きいているんだと教えてくれたことでした。
さらに民話の継承は、物語の基点となる出来事を体験したか否かにかかわらず行われます。例えばある人が、他人に語らざるを得ないような強烈な体験をする。そしてその話をきいた別の人も、これは誰かに伝えるべきだと感じてまた他者に話す。ここで重要なのは、それが完全に同一の物語として伝わることではなく、みんなが自分ごととして語る点です。
このような民話の伝承の姿を知ることから、瀬尾さんは、フィクションが媒介することによって、当事者と非当事者の区分を超え、みんなが語りのなかに入っていけると感じたと話します。そして、表現者としての自身の仕事とは「その余白をつくること」だと言い、2015年からはじめた物語づくりも、出来事を正確に伝えることを目的としているのではなく、「みんなが共有できる語りのための火種をつくっているようなイメージ」だと説明しました。

そんな瀬尾さんの話をきいた牧さんは、「瀬尾さんのナラティブ(物語)の捉え方は、防災の世界では新しく感じる」と話します。というのも、「防災の世界では当事者性、“わたしの語り”を重視してきたからです」と牧さん。「でも瀬尾さんは、誰かの物語をその本人だけではなく、誰もが話せるものにすることを大切にしている。それが出来事を昔話として伝えるということで、新鮮で素晴らしい」と、その実践の可能性を評価しました。
こうした感想を受け、瀬尾さんは陸前高田に初めて入った頃を再度振り返り、「震災体験は傷の話だが、そこには笑いがあったり、一緒に泣いて励ましあったりもする。語らずにはいられないことを中心に、人が集まって話し合う。そのことの切実さやうれしさがわたしのなかの基本にある」とコメント。そして最後に、災禍の語りに興味をもちつつ躊躇する人たちに向け、「何ができるのかと考えるより、話をきき、語る場に入った方が気持ちも楽になるし、楽しさもある。その語りの輪にみんなも入ってほしいと思う」と呼びかけました。

異なる立場から、災害をめぐる語りや被災地の人々の姿を見つめてきた二人が言葉を交わした今回のトーク。二人の発表や対話からは、「災害」や「防災」、あるいは「当事者/非当事者」のような、わたしたちが普段何気なく使う言葉の手前で立ち止まり、その内実や境界をあらためて考える大切さが感じられました。そして、それはまた、異なる人生を歩む人たちと経験を共有するための「翻訳」や「余白」の重要性、それらを生み出す上での文化や表現の可能性を浮かび上がらせる時間ともなりました。
レポート前編はこちら>
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19
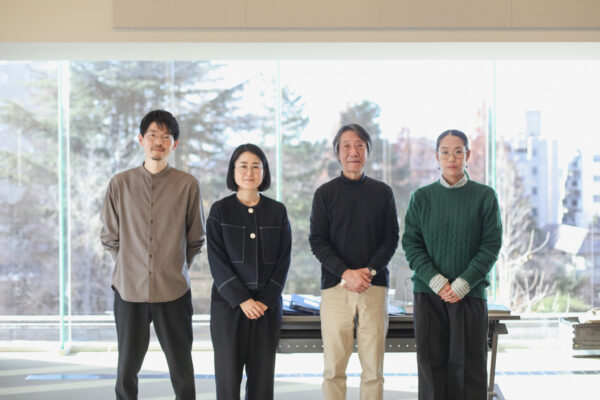
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹
2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹
2023.09.07

執筆者 : 杉原環樹
2023.09.07
