
2024レポート③ 自分のアートプロジェクトに向き合う態度
執筆者 : 嘉原妙、和田真文
2025.03.31

演習「自分のアートプロジェクトをつくる」は、これからの時代に応答するアートプロジェクトのかたちを考えるシリーズ「新たな航路を切り開く」の一環として開催している、ゼミ形式の演習です。ナビゲーターはP3 art and environment統括ディレクターの芹沢高志さん。アートプロジェクトを立ち上げたい方やディレクションに関心のある方を対象としています。
2024年度は10月初旬から翌年2月初旬までの約4ヶ月にわたって行いました。
この演習の様子を、3つの記事でレポートします。
- 2024レポート① 対話を通して自分の問いを見つける
- 2024レポート② 3人のゲストの実践の風景
- 2024レポート③ 自分のアートプロジェクトに向き合う態度
演習では、受講生それぞれがまず自分のなかの問いをつかまえ、それをどのようにアートプロジェクトとしてかたちにしていくのかを考えていきます。そのために、受講生同士のディスカッションやナビゲーターによる講義のほか、3名のゲストを招き、ゲストによるトークとその後のディスカッションの回を設けています。
今年度のゲストは、梅田哲也さん(アーティスト)、矢野淳さん(株式会社MARBLiNG代表)、阿部航太さん(デザイナー/文化人類学専攻/一般社団法人パンタナル代表)の3名。
それぞれのゲスト回を紹介します。
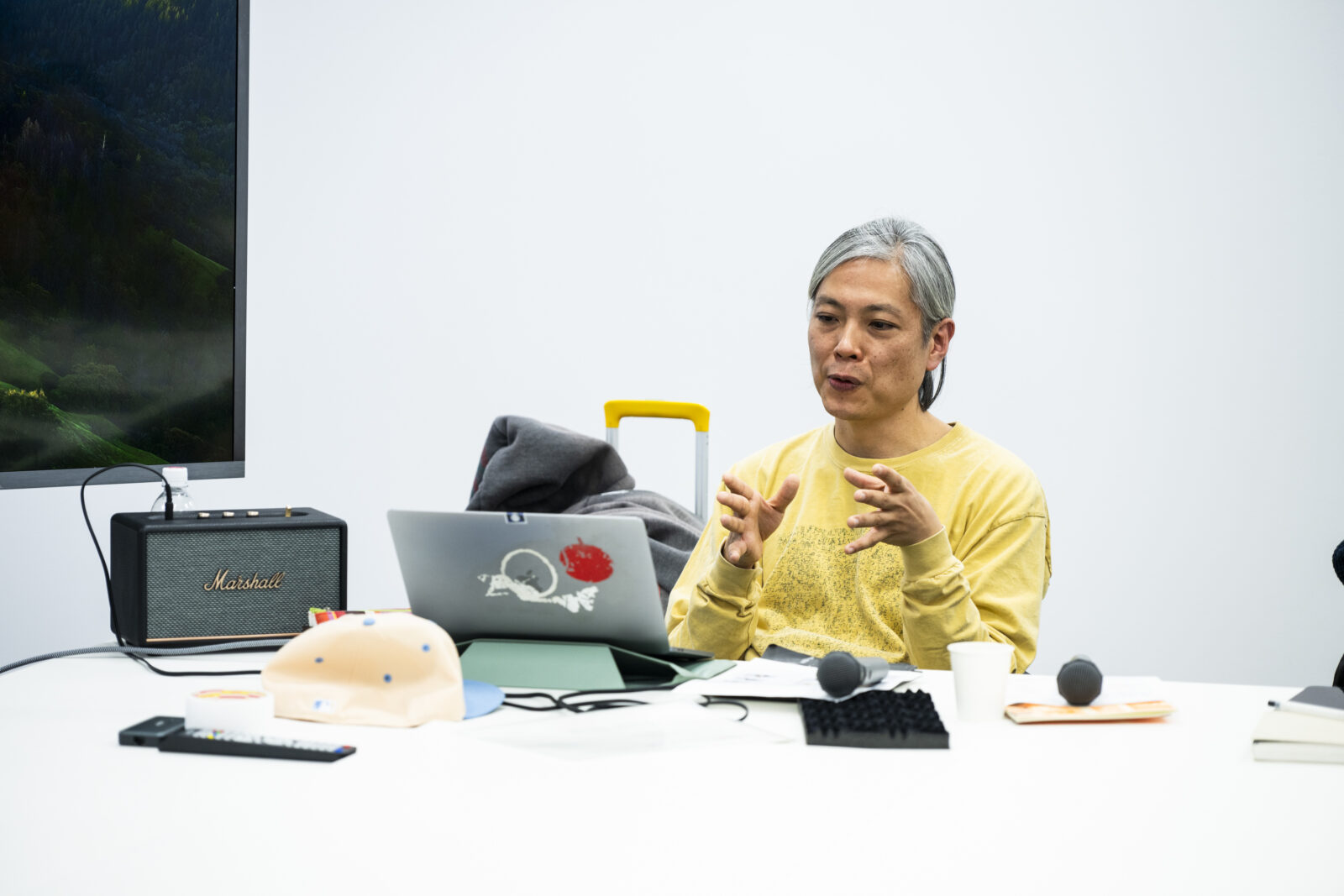
11月9日(土)は、梅田哲也さん(アーティスト)をゲストにお招きしました。建物の構造や周囲の環境から着想を得て、日常で手にする身近な素材や現地にあるものと、音や水、重力などの物理現象や自然環境を組み合わせた作品を多数発表してきた梅田さん。近年では《O回》(さいたま国際芸術祭2020)や「梅田哲也展 wait this is my favorite part 待ってここ好きなとこなんだ」(ワタリウム美術館、2024)など、案内人に連れていかれるようにして観客が会場を回遊し、観客もいつのまにかパフォーマンスの一部になっているといった演劇的な手法も取り入れています。
前回の演習で「アートプロジェクトの構想を考えるためには日頃の小さな習慣の積み重ねが大事」とアドバイスをもらった受講生たち。梅田さんが生み出すさまざまな仕掛けやアイデアは、どのような習慣からやってくるのか、何を考えているのかと、スタートから質問が尽きない回となりました。
梅田さんの作品が展示される場は、美術館から廃墟、はたまた船の上までと多様です。発表される形態も、展示、パフォーマンス、公演、ライブなど幅広く手がけられています。しかし、梅田さんにとっては、場所がどこであっても、それぞれの作品で自分がやっていることそのものはあまり変わらないと言います。どちらかと言えば、「環境と素材が変わっていく」感覚を持っているとのこと。
そのなかで梅田さんがどうしても気になる・手放せないと言うのが、「もの」。芸術祭などに招聘されたとき、作品展示後には建物が解体されてしまう、廃棄されてしまうと聞くと、つい大きなガラスの水球などでも持ち帰ってしまうため、ぞろぞろとものが増え、移動するときには大所帯の家族になったような感覚があるそう。持ち帰られた素材は、別の場所で展示されたり、そのうち居場所が見つかってそこに置かれるようになるものもあると言います。

梅田さんの作品では、展示物であっても、元からそこに素材が置かれていたかのような馴染み方をしているものがあったり、演出上で配置された人なのか、たまたま通りがかった人なのか、境目がわからなくなるようなことがあったりします。梅田さん曰く「何もつくってないねと言われることがあるが、そう思われたら最高。でも、場づくりはちゃんとやっているんです」とのこと。場と向き合いながらつくっていく。場ができてくると、そこにいる観客たちが動きだし、その動きがまた別の動きにつながっていく。観客がパフォーマンスのなかに含まれていくような回遊型の作品の場合は特に、そうした動きのつながりを、まるでスコアを書くようにしてつくっているそうです。
自分がその場所で作品を展示したい、関わりたいという強い動機を探すため、何度も場所に足を運んでさまざまな人と知り合い、話し、関連書籍を一通り読み漁る。その小さなディテールを積み重ねていくことが、作品制作につながっていると梅田さんは言います。海外で展示をする際も、何をするかが決まっていなくてもとにかく音が出せる準備だけはして行って、その場で音を披露してみると、その流れでライブをする話が持ちかけられることもあるそう。そうやってまず動くことから次の動きにつながっていきます。一方で、美術館など規定がある場所では、そのレギュレーションといかに向き合い、ハッキングしていくかという話も。アートだからこそできることの可能性についても言及されました。

受講生からは「作品を通して鑑賞者に伝えたいことは?」などの質問がありました。梅田さんは「その場所にその作品が置かれた時、どういう振る舞いをするかを考えることはあるものの、(想定外のできごとも含め)鑑賞者と一緒につくるという意識でいる」と答えました。
また、「人と話すことが苦手」といったコミュニケーションに関する質問には、「すごく得意なことがあるわけではないがその場にいると雰囲気が明るくなるような人、一極集中型ではない、アートとは無関係に思える友人と一緒にやってみたら?」という提案も。梅田さんの答えに共通していたのは、目の前で起きようとしていることに目を凝らし、想像しようとする姿勢。アートプロジェクトの現場では、どんなに対策を考えていても思いも寄らないことが多々起こるもの。受講生たちは梅田さんのお話からそこに踏み出すヒントをもらったのではないでしょうか。

11月30日(土)は、福島県飯舘村で「図図倉庫(ズットソーコ)」という文化拠点を運営する矢野淳さんをゲストにお迎えしました。東京出身の矢野さんは、東日本大震災後に物理学者のお父さまが福島県飯舘村でNPOを設立したことをきっかけに、高校生の頃、まだ帰宅困難指示が解除される以前から飯舘村に通われていました。飯舘村は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により全村避難を経験した場所です。「震災以前と風景はほとんど変わらないのに、人だけが居ない不思議な光景だった」と当時の飯舘村の様子を矢野さんは振り返ります。
その後、大学卒業を機に東京と飯舘村の二拠点生活をスタートした矢野さん。飯舘村の地域再生に携わるなかで、元飯舘村地域おこし協力隊の松本奈々さんと出会い、2021年に合同会社MARBLiNGを設立(現在は株式会社)。同年、飯舘村のホームセンター跡地にある1,000平米の建屋を飯舘村の資源を活用してリノベーションし「図図倉庫」をオープンしました。現在、図図倉庫は、シェアオフィスやテナントとして、企業、研究者、移住者など多くの人が集い、新たな実験ができる場として開かれ、トレーラーカフェやイベントの開催などさまざまな人が楽しめる場所となっています。
「飯舘村は、震災以前からあった高齢化や過疎化といった地域課題に加え、震災後の原発事故による環境課題を抱えています。それは、ある意味で『世界最先端の課題』がある村だと捉え直すことができるのではないか。そうすることで、世界中の人々が飯舘村に関わってくれるのではないか。そんなふうに、飯舘村の課題を捉え直していこうというのがわたしたちの活動です」と矢野さんは語ります。

なかでも近年取り組まれている図図倉庫の常設展示「環境世界を旅する」とツアープログラム「環世界探索紀行」は、その飯舘村の課題の捉え直しをアートや演劇などの表現の手法を用いた興味深いものでした。常設展示では、150億年前の宇宙誕生から飯舘村の現在に至るまでの経緯を壮大な物語のように絵で表現し、実際に村民や研究者が収集した飯舘村の土のサンプルとともに、原発事故により大地に降り注いだ放射性物質がどのような状態にあるのかを模型などで示したり、放射線、放射能、放射性物質とは何か、またその半減期についてわかりやすく図式化されるなど、訪れた人が想像を膨らませて考えていけるような工夫がなされていました。
「環世界探索紀行」のツアープログラムは、飯舘村を「いきる博物館」と位置付け、演劇的な手法を用いて、この地域の風土や歴史、文化、人と出会うというもので、道先案内人が同行し、立ち寄る各所でさまざまな出会いの入り口を開いてくれます。参加者は「探索者」として、飯舘村の各所を訪れながら、ときには素粒子や天体、生き物、この土地の人々の視点を想像しながら、目には見えないけれど、飯舘村に積層する記憶や過去・現在・未来の時間の地層を発見し、感じ、考えていくというものです。

矢野さんは「デザインは翻訳作業で、アートは “わたしからは世界はこう見えるよ” ということを表現するものだ」と言います。「例えば、放射線のことなどニュースで見たりするけれど、よくわからないですよね。でもそうしたわからないものを、研究者とデザイナーが協働したり、演劇やアートといった表現を通して示すことで、“飯舘村の人や研究者、図図倉庫のわたしたちは世界をこう捉えているよ” ということを伝えていけるんじゃないか。こうした活動を通して、じゃあ自分は世界をどう見ているのだろう?と、訪れた人が考えるきっかけになったらいいなと思っています」
その他にも「農×デザイン塾」という企画を通して新たなお店づくりや産業創出に取り組むなど、環境づくりを軸に幅広い活動を展開している図図倉庫の取り組みに圧倒された受講生のみなさん。質疑応答では、「世界最先端の課題だと、いつ実感したのか?」「図図倉庫の要素や使い方はどのように計画したのか?」などの質問が出ました。
それに対して矢野さんは、村民へのヒアリングを実施していた際、ある女性から震災以前の暮らしが果たして本当に幸せだったと言えるかわからない、という本音に触れたエピソードを踏まえ、「この場所なら私自身も暮らしたい、と思える場をつくることが大事だと思った」と語りました。また、「飯舘村は、どんどん変化していて、いま必要な要素がもしかしたら来年にはいらなくなることも。だから、常に可変し続ける場なんですね。『つながりを再生する秘密基地』と位置付けている理由も、図図倉庫(ズットソーコ)という名前も、家具なども移動式にしているので空間の隅に寄せれば倉庫に戻るという意味もあるんです」と矢野さんは語ります。その答えからも、環境の変化に柔軟に応答しながら活動しようとする姿勢が伝わってくるものでした。
矢野さんの取り組みや視点に共通しているのは、人の持つ知的好奇心や探究心を信じて「自分なりにやっていく」ということ。「自分のアートプロジェクト」の企画構想を進める受講生にとっても、改めて「自分なりにやる」とはどういうことなのかを考えるヒントが詰まった時間でした。

12月22日(日)は、デザイナーの阿部航太さんをゲストにお迎えしました。阿部さんは現在、高知県土佐市在住。日本で技能実習生として生活する外国人と地域住民との交流づくりを目指す「わくせいプロジェクト in 土佐市」を展開するほか、東京アートポイント計画の共催事業であり、海外に(も)ルーツをもつ人々とともに映像制作を中心としたワークショップを行うプロジェクト「KINOミーティング」を運営しています。阿部さんの肩書きには「文化人類学専攻」の単語が。一見、「デザイナー」との関連性がよくわからないようにも思えますが、お話しを伺ううち、阿部さんの現在に至るまで道のりと指標となる考え方に深く結びついていることがわかってきました。
埼玉県の新興住宅地で育った阿部さん。イギリスの美大に進学後、日本でグラフィックデザインの仕事に携わりました。大阪で太陽の塔(岡本太郎作)の先に建つショッピングモールのデザインを担当したときに、土地の文脈から離れ、商業的なデザインのみを追求する姿勢に疑問を覚えたことをきっかけに、独立。当時出会った、鈴木裕之『恋する文化人類学者 結婚を通して異文化を理解する』(世界思想社、2015)を通し、文化人類学の視点に惹かれ、縁あってブラジルに向かいました。
文化人類学の魅力は「自分が一生触れられない考え方・別の見方があって、いまよりもっと自由に生きられると感じるところ」だという阿部さん。その阿部さんがブラジルで衝撃を受けたのが、まちなかの壁面に描かれたグラフィティでした。現地で心惹かれた瞬間にアクションカメラで撮りためたグラフィティの魅力をどうにか誰かに伝えたいと、グラフィティアーティストへのインタビューや街の風景を含めた漫画を制作し、リソグラフで印刷した本を制作し出版。さらには帰国後、漫画ではこの面白さを伝えきれていないと考え、撮りためた映像をもとに映画を制作。また、4万字にもわたる映画パンフレットを自ら取材・制作しました。アーティストがグラフィティをまちなかに置いていく行為を公共空間をデザインする行為として捉えること、そしてその構造をビジュアルコミュニケーションを用いて伝えることを通して、“デザインの文脈で文化人類学をする”ことを考えていったのだそう。

グラフィティアーティストへの取材や多様な人々が行き交うブラジルの都市で生活するなかで生まれたのが、「どうしたら自分とは異なるバックグラウンドの人と関わっていけるのか?」という疑問でした。ここを起点に阿部さんの活動は、「KINOミーティング」や「わくせいプロジェクト in 土佐市」へと展開していきます。
「KINOミーティング」は、“海外に(も)ルーツをもつ人たち”を対象に、映像制作のワークショップを展開するアートプロジェクト。阿部さんはプロデュースと企画運営を担当しています。異なるルーツをもつ参加者たちがグループを組み、写真や映像、音声を用いて自分たちのルーツを辿っていきます。撮影など参加者の役割を固定せず、ローテーションさせていくことでプロジェクトとしてのバランスを保っているそうです。KINOミーティングは、公開されているアーカイブも豊富。あとから振り返る作業ができる大切さを考え、「誰が書いたか、誰がどう見たか」を意識して記録に残しています。
「わくせいプロジェクト in 土佐市」は、阿部さんが高知県土佐市に地域おこし協力隊として移住しスタートさせました。技能実習生と地域をつなぐこのプロジェクトは、10年計画の想定。あいさつからはじまって、少しずつ距離を縮められる「場」をつくっています。スパイスやハーブなど多国籍食材を扱うスーパーマーケットを入り口に、イベントやワークショップもできるコミュニティスペース、地域の中高生・大学生を対象としたデザインの学校など、多機能スペースとして運営をはじめました。2025年度からは、地域おこし協力隊としての任務は期限を迎え、いよいよフリーランスとしての取り組みがスタートします。

今年度の受講生のなかには、地域おこし協力隊として演劇の手法を用いたアートプロジェクトを構想する方や、翻訳やまちに住む日本語を母語としない方、海外にルーツをもつ方とのアートプロジェクトに興味をもつ方など、阿部さんの活動と興味範囲が重なる方もいて、どのように地縁のない地域に入り込むか、日本に住む外国人とどのように知り合えば良いのかなどの質問があがりました。まずは既にあるコミュニティやイベントなどに足を運んで、気軽な気持ちで出会ってみること、属性やリサーチで得た知識よりも、その人、個人に出会うという意識を大事にすること、そして何よりも「自分がおもしろい」と思ってはじめた、その原点を忘れないこと。阿部さんの答えは、演習のなかで繰り返し問われる「なぜ自分がそれをやりたいと思うのか」にも通じるものでした。



撮影:齋藤彰英