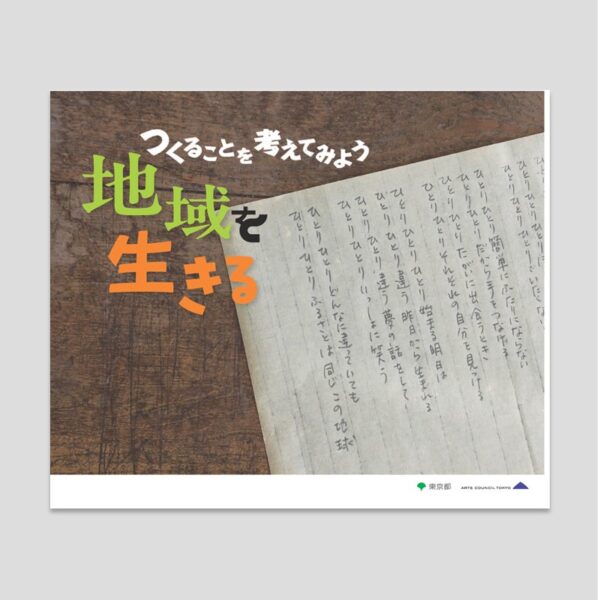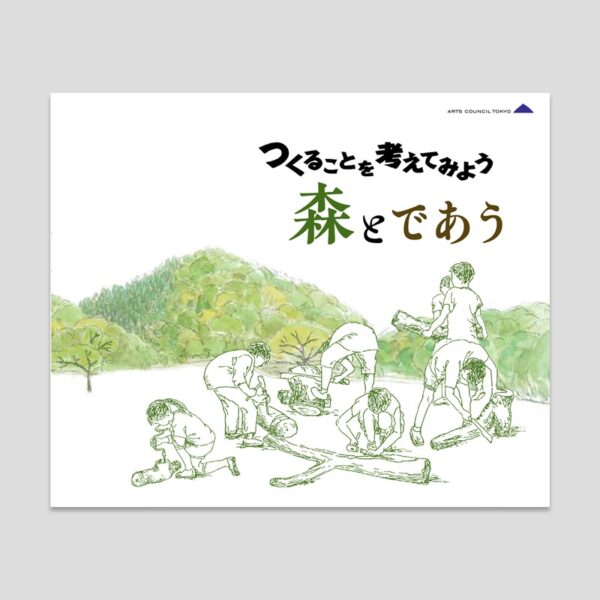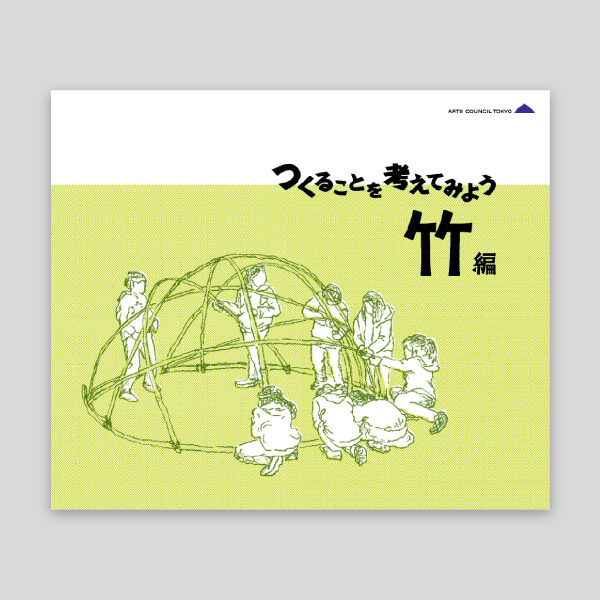- 共催事業
一人ひとりが自分の暮らす足元を見つめ直す
多摩地域の文化的、歴史的特性を踏まえ、その「地勢」を探ることを通して、一人ひとりが自分の暮らす足元を見つめ直すプロジェクト。2011年〜2020年度に東京アートポイント計画と共催したNPO法人アートフル・アクションがその経験とネットワークを生かし、小学校などの教育機関や福祉施設で働く人たち、地域で暮らす人たちとの実践の場づくりを行う。それによって個々人の抱える切実な社会課題に向き合うために人々が協働するネットワークの基盤づくりを進めている。





実績
多摩の未来の地勢図では、「ざいしらべ 図工―技術と素材について考える」「ゆずりはをたずねてみる―社会的養護に関わる人たちとともに」「多摩の未来の地勢図をともに描く」の3つのプログラムを主に行っている。
「ざいしらべ」では、多摩地域の小学校の図工専科教員を対象に、大きな木の根や竹、紅花など個人では手に入れにくい自然素材や大型素材を提供し、伝統的な技術や技法、ICTに関するワークショップなどを通じて、授業での表現や造形の拡張を促すきっかけをつくっている。2021年度には、本プログラムで培ってきた素材や道具を保管するための収蔵庫を東村山市立南台小学校に設置。さらに、多摩地区図画工作研究会とも連携し、技術が持つ広がりや役割、歴史的な背景についても知見を深めている。2023年度には14校と連携し、竹や広葉樹といった素材、布の染めや筆づくりの技法に触れる授業を実施したほか、アーティスト・五十嵐靖晃が奥多摩町立氷川小学校に滞在し、こどもや住民と交流しながら作品制作を行った。2024年度は、小学校を地域にひらく試みとして奥多摩町立氷川小学校の総合学習の授業において、造形作家・下中菜穂とともに獅子舞などの文化や自然を調べ、こどもたちが地域の歴史や慣習についての理解を深め、発表するプログラムに取り組んだ。また、昭島市立光華小学校では、アーティスト・弓指寛治が約1か月半滞在し、地域のリサーチやこどもたちとのかかわりから作品づくりを実施。そして、こうした取り組みをもとに関係者などへのインタビューを行い、冊子にまとめ多摩地域の教育機関への配布も行った。
「ゆずりはをたずねてみる」では、困難を抱えたこどもたちと向き合い、日々の業務に多忙な支援者のケアに取り組んでいる。社会福祉法人二葉むさしが丘学園のグループホームのスタッフを中心に、音楽やダンス、こころと体をほぐすためのエクササイズを通して、肩から力を抜き、隣り合う人々とゆるやかに出会い、日々を重ねる場づくりを実施。2021年度からは出張ワークショップを重ね、施設間の交流プログラム構築の可能性を探り、2023年度には「演劇を通して“ケア”を考える連続ワークショップ」へとプログラムを拡張。2024年度はその継続企画として、アートのもつ創造性や身体性からケアする・されることへの根源的な問いを探求する連続ワークショップや対話の場をひらいた。
「多摩の未来の地勢図をともに描く」は、多摩地域の文化的、歴史的特性などをふまえ、いま自分が住んでいる足元を見つめ直し、現代の暮らしや社会課題に向き合うための方法を模索する連続ワークショップ。2021年度は「辺境としての東京を外から見る」をテーマに、フィールドワークと水俣、ハンセン病に関するレクチャーを開催した。2022年度は「あわいを歩く」をテーマに、参加者が実際にフィールドを歩き、考えることで議論を深めていくワークショップを行った。2023年度には「多摩の未来の地勢図をともに描く2023 ーre.* 生きることの表現」として、「シャトー2F(にーえふ)」を作業場としてひらき、ゲストを招いたワークショップや、映画の上映会など自主企画を実施した。ほかにも、暮らしのなかでの小さな問いをもちよる「たましらべ」では、スタッフや各プログラムの参加者が定期的に集まったり、大学の研究機関に訪問するなど、考えを深める場をひらいている。
関連記事
日々のなかの「微弱なもの」を、自分の体で感じるために――宮下美穂「多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting」インタビュー〈前篇〉
日々のなかの「微弱なもの」を、自分の体で感じるために――宮下美穂「多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting」インタビュー〈後篇〉