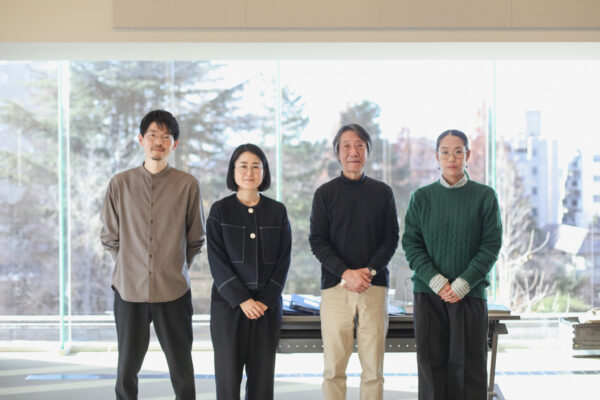
「拠点」とは何か? 秋田、神津島、神戸の事例を通して考える(APM#14 後編)
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19

武蔵野プレイスにて開催された「Artpoint Meeting #14 わたしたちの “拠点” をつくる:ひらきかた と つづけかた」会場の様子。
アートプロジェクトにかかわる一つのテーマをめぐり、毎回、幅広いゲストと対話を重ねてきた東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。2023年12月17日、その第14回が、東京都・武蔵野市の「武蔵野プレイス」にて開催されました。
今回のテーマは、「わたしたちの “拠点” をつくる:ひらきかた と つづけかた」。東京アートポイント計画で実施されるアートプロジェクトにおいても、重要なものとして耳にする機会の多い「拠点」というキーワード。しかし、そのあり方や運営の方針は、プロジェクトの目指すものや活動地域などによってさまざまに異なります。
この日は、そんな、よくよく考えると捉えどころのない「拠点」というものについて、「秋田市文化創造館」に携わるNPO法人アーツセンターあきた事務局長の三富章恵(みとみゆきえ)さん、神津島で展開されているアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」事務局の飯島知代(いいじまともよ)さん、そして、神戸の地で約30年にわたり活動を行っている「C.A.P.[芸術と計画会議]」ディレクターの下田展久(しもだのぶひさ)さんという3名のゲストに、それぞれの考え方を伺いました。
当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。
(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:仲田絵美*1-5、9、13、14枚目)
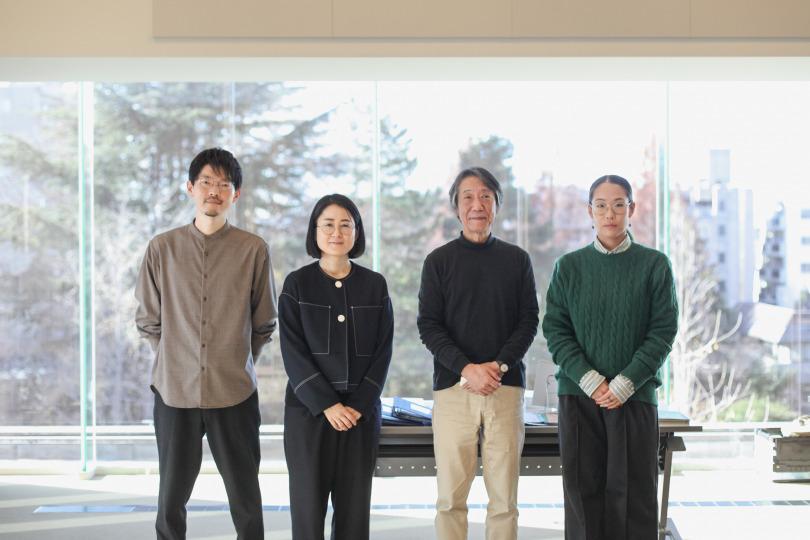
この日はまず、プログラムオフィサーの櫻井駿介が、東京アートポイント計画の簡単な説明とともに、「拠点」というテーマを設定した問題意識について話しました。
2009年にはじまった東京アートポイント計画では、2023年度までに56団体と共催し、45のアートプロジェクトを行ってきました。例えば、市民と協力してまちなかに活動のための場所をひらいたり、多文化をテーマにした映像ワークショップを行ったり、手話を通じて生まれてきた文化に目を向けたコミュニティ形成を目指したり。その活動は、派手で一時的なイベントではなく、わたしたちの暮らしのすぐ隣にあるようなささやかなものが多いことが特徴です。
アーツカウンシル東京の「文化創造拠点の形成」事業として位置づけられている東京アートポイント計画では、そのような「新たな価値観や創造的な活動を生み出す『拠点』をまちなかにつくること」で、「わたしたちの暮らしのなかに、個人が豊かに生きるためのよりよい関係や仕組み、コミュニティを育む」ことを目指してきた、と櫻井は整理します。

また、実現に長い時間がかかるこうした取り組みを続ける上で、東京アートポイント計画では、プロジェクトのプロセスや、持続的な事務局(運営チーム)づくり、さらに周辺地域や地域住民との接点づくりにも力を注いできました。こうしたなかで、多くのプロジェクトに必要とされるのが、「拠点」と呼ばれるものになります。
しかし、あらためて「拠点」とは何でしょうか? そのイメージを掴むために、櫻井はこれと類似する「場所」や「場」という言葉とを比較しました。それによれば、「場所」とは具体的な大きさや広さ、位置をもつ空間の「条件」のことで、「場」とは、その上で何かが生まれたり、行き交ったりする「状態」のことです。これに対して「拠点」は、それを起点に何かがはじまったり、集まったりする一種の「仕掛け」ではないかと櫻井は言います。

東京アートポイント計画では近年、さまざまなプロジェクトにおいて、こうした拠点をめぐる動きが活発化しています。例えば、災禍の記録のネットワークづくりを行う「カロクリサイクル」というプロジェクトは、2023年9月に江東区・大島(おおじま)の団地の一角にコミュニティ交流拠点「Studio 04」をオープン。一方、ろう者を中心としたプロジェクト「めとてラボ」は、台東区・谷中(やなか)にろう者も安心して過ごせるワーキング・プレイスとして「5005」という拠点を立ち上げました。
ここで重要なのは、かれらの拠点が、その立地や仕組みにおいて、活動の目指す方向と相補的(そうほてき)であるという点です。だとすれば、「拠点」は必ずしも物理的な空間を伴う必要もないかもしれません。東京アートポイント計画では、こうした拠点の多面性を捉えようと、今年、プロジェクトの担い手が二組ずつ「拠点」をテーマに対話を重ねる映像シリーズを制作・公開しました(拠点運営を考える対談シリーズ「Knock!!拠点を訪ねて」)。今回の「Artpoint Meeting」は、こうした一連の流れを受け、「拠点づくりの周りにあることを考えたい」との思いから組まれたと、櫻井は説明しました。
つづく「地域のなかで、拠点をひらく」と題したクロストークには、ゲストの三富章恵さんと飯島知代さんが登場。それぞれのかかわる施設やプロジェクトを紹介しました。
三富さんが事務局長を務めるNPO法人アーツセンターあきたは、2021年3月に秋田市の市街地にオープンした「秋田市文化創造館」(以下、「創造館」)の運営を行っています。この建物はもともと1967年に開館した秋田県立美術館でしたが、2013年に閉館。その後、愛着をもつ地元の声を受け、市が土地を借り受け、活用を模索してきた施設でした。

2018年にまとめられたその利活用調査報告書では、施設の今後の方針として「まち全体の文化力を涵養(かんよう)」「未来の地域社会に向けた感性を創造」「新たなまちの魅力とにぎわいを創出」「市民のまちへの愛着と誇りを醸成」の4つが決定。さらに、JR秋田駅から徒歩圏内のほかの文化施設が基本的に「鑑賞」のための場所であるのに対し、創造館では、「市民が新しいことをつくっていく場所」にするという方向性がまとめられていきました。

2018年からその計画づくりに参加した三富さんは、当時を振り返り、「当初は劣勢からのスタートだった」と話します。もとが県美の建物であること、NPO自体も秋田公立美術大学が母体であることなどもあり、どうしても「美術の施設」との印象が強かったのです。創造館ではその状況に対し、施設の機能を狭義の美術に絞るのではなく、「アーティストと実験する『創造実験』」「新しい知識や視点に出会う『機会の提供』」「アイデアを実践してみる『創造支援』」などとゆるやかに設定。さらに、積極的に建物の外に出ることを通して、「まちに“新しい活動”を育む」ことを目指してきたと、三富さんは言います。
2021年の開館後も、創造館では多様な人に関心をもってもらうための工夫をさまざまに施してきました。例えば、食や農業といった身近なテーマの企画をしたり、地域のイベントと連携したり、視覚的な情報発信に力を入れたり。また、主催事業だけでなく、共催や貸館事業にも取り組んでいますが、驚きなのが1平米を1時間=5円で借りられること。この破格の賃料から、施設には市民からの使用に関する幅広い相談が届きますが、スタッフ間には「できるだけ可能性を否定せず、どんな相談にも耳を傾けよう」という姿勢が共有されているといいます。その結果、創造館では、野菜づくりや料理、広場でのキャンプやヴァイオリンの演奏、こどもの遊び場としての利用、対話の機会の創出など、実に多様な活動が行われてきました。


そこに行けば、誰かが何かをつくっている姿に出会える場所として、着実に市民に親しまれているように見える創造館。一方、三富さんは今後の目標として、潜在的な利用者に施設を知ってもらうことや、運営を持続する人材の確保や育成が挙げられると話しました。
もう一人のゲストの飯島さんは、伊豆諸島に浮かぶ神津島で、2018年から東京アートポイント計画の共催事業として「HAPPY TURN/神津島」(以下、「HAPPY TURN」)というプロジェクトを展開しています。

東京都心から大型客船で約12時間を要する人口約1800人の神津島では、多くの出身者が大人になると島を出ていきます。そして、そうした人が島にUターンすることを、島の方言では慣習的に「しまってくる」とネガティブに表現していました。HAPPY TURNはそんな状況に対して、島に戻ることを「ハッピー」に捉え直したり、かかわる人たちがそれぞれの暮らしのなかで「幸せ」を再考したりする契機をつくる活動を目指してきました。
そんなHAPPY TURNが最初に取り組んだのが、地域の拠点づくりです。その土台は、10年近く空家だった元中華料理屋。メンバーはまず、空間デザインも行うクリエイターユニット「岩沢兄弟」の協力も得ながら、掃除大会を行いました。業者に頼むのではなく、張り紙で島民にも助けを求めながら、自分たちで拠点を整え、ひらいていったのです。

おもしろいのは、その拠点の用途を意図的に曖昧にしたこと。作業を手伝いに来たり、見に来たりした島民から「何をつくっているの?」ときかれても、明確な答えを避け、「わからないことをそのままにすることを頑張った」と飯島さん。この名づけの回避により、「何をしたいのかわからない」という理由で「くると」から離れる人もいましたが、他方でその用途のなさが、遊び場を探すこどもたちや、島に居場所をもたない移住者たちを惹きつけることに。こうしてHAPPY TURNの活動開始からのおよそ3年間は、ひたすら拠点づくりに注がれました。
現在は週に3日間、午後に拠点を開放。スタッフには子育て中の人も多く、「くると」は島で重要な親子のコミュニティになっているといいます。そうした活動のなかでは、運営の方針や場のあり方をめぐり、飯島さんと、代表の中村圭(なかむらけい)さんとの間で意見の相違が起きることも。何事もきちんと整えたい性格だという飯島さんは、以前、島で不要になった部材や道具を何でも「くると」に拾ってきてしまう中村さんの行動にやきもきしていましたが、その雑然さをこどもたちが楽しむ姿を見て、「この場所のルールを誰かが決めていいのだろうか、と疑問に思うようになりました。いまでは少し気になることがあっても、答えを保留してまずは話し合うようにしている」と心境の変化を語りました。

「くると」では、2020年から本格的にアーティストプログラムも開始。アーティストの山本愛子さんや大西健太郎さん、音楽ユニットのテニスコーツ、アートコレクティブのオル太らを招聘して、島に現代アートや先鋭的な音楽のエッセンスを導入しはじめています。一方、こうした一種のハレの活動と並行して、「部活」と称した大人向けの活動も展開。ウクレレ部、おどり部、筋トレ部などの小さな活動を通じて、島の大人と拠点の日常的な接点も増やしています。飯島さんは「活動をはじめたころは『アート』というだけで驚かれていたが、こうした活動を通して最近は少しずつ島に馴染んできた」と振り返りました。

その後は、冒頭に話をした櫻井も交え、三富さんと飯島さんがお互いの話をきいた感想を述べ合いました。

「くると」の活動を初めて詳しく知ったという三富さんは、「よくわからない場所であることを大切にする」姿勢が印象に残ったとし、「創造館も何の施設かわからないと言われることが多いが、わたしたちは説明しすぎていると反省した」とコメント。そして、飯島さんが最後に語った「馴染んできた」とは具体的にどういうことか、と問いを投げました。
これに飯島さんは、島民には当初、その場所へのかかわり方がわからず、近づき難い感情があったものの、こどもが集まったことを機に、大人の間でも「くると」が「あってもいい場所」という認識に変わっていったと返しました。櫻井もこれに続け、神津島には不動産屋がなく、島外からの人は島への入り方がわからないこと、そうしたなかで「くると」が移住希望者にとっての重要な情報収集の場や、移住者にとっての居場所の一つになっていることなどを補足しました。

2人からは、拠点のスタッフに関する話題が多く挙がりました。飯島さんは、「くると」よりも規模の大きい創造館で、スタッフ間にどのような姿勢の共有があるのか興味があるとし、発表にあった「市民からの使用に関する相談の可能性を否定しない」という姿勢が印象的と話しました。
三富さんは、創造館のスタッフには美大の卒業生や県外でアートプロジェクトを経験してきた人も多いことから、「基本的に、禁止することへの抵抗感は共有していると思う」と語ります。そうしたなか、最近もバナナの栽培を広めたいという男性がもち込んできたバナナの苗木を育てることになったというエピソードや、館内のいたるところに作品を展示したいともち込まれた絵画作品を、そのまま施設利用として受けてしまうと利用料の負担が大きくなりすぎるため、一部はトンチのように「展覧会誘導のためのポスター」として掲出し、利用者にかかる負担を軽減したエピソードなどを披露。市民にひらくことで思いもよらないような相談やアイデアがもち込まれるが、「いまは何とかそれらを実現しようと考えることが楽しくて仕方ない」と語りました。
ただ、禁止事項やルールを決めないことにも限度はあるはずです。櫻井から拠点の運用にあたり何らかのマニュアルはあるのかと問われた三富さんは、「マニュアルがあったらどれだけ楽か。ただ、それをつくった時点で創造館のよさは終わる。初めてのケースに対しては毎回内部で話し合って決めている」と回答。これに飯島さんも、「『くると』も同じ。困ったときはその場で判断せず、スタッフ間で相談している」と続けます。そしてその一例として、最近「くると」のなかでこどもたちがYouTubeなどの動画サイトを見ることの是非についての議論があったと紹介。話し合いの結果、「サッカーや野球が禁止されたことで公園がつまらなくなったように、動画サイトも一方的に禁止すべきではない」と、判断を保留していると語りました。
このパートの最後には、櫻井から「拠点を運営する上で『アート』に委ねているものは何か?」という質問も挙がりました。もともとアート畑出身ではないという飯島さんは、「いろんな活動を経て、最近ようやくアートってこういうことかな?というニュアンスがわかってきた」とし、「アートの見方や考え方を使うことで優しくなれるというか、アートプロジェクトだからこそ触れられる領域があると感じている」と話します。そして、その一つの可能性は、「資本主義のなかでこぼれ落ちるものを拾うようなことができる点にあるのではないか」と指摘しました。

一方の三富さんは、たびたび語られるアートとデザインの比較論に言及。ゴールを設定する後者に対して、前者は未来にオープンである点が特徴だとし、「そうしたアートの性質が創造館と親和性が高い部分だと思う」と語ります。ただし、根強い「アートの施設」という印象を払拭するため、なるべく「アート」という言葉を使わないようにしてきたこれまでの経緯も振り返り、櫻井の問いには時間をかけて考えていきたいと話しました。
レポート後編へ>
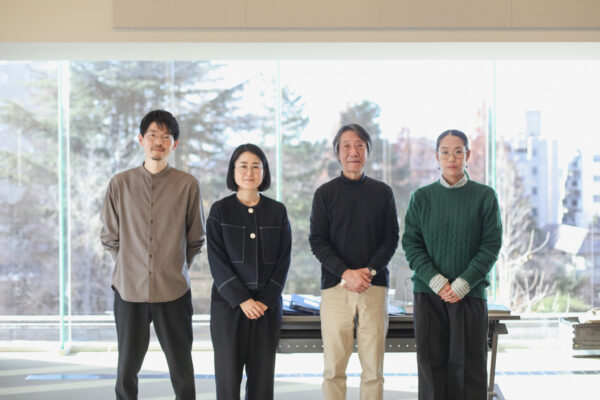
執筆者 : 杉原環樹
2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹
2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹
2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹
2023.09.07

執筆者 : 杉原環樹
2023.09.07