“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)
執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28


2021.12.28
執筆者 : 氏家里菜

災禍の現場に立つには、いったい、どんな態度や技術、方法がありうるのか? 災害復興の現場に多様なかかわりかたをしてきたゲストに話を伺うディスカッションシリーズの第4回目回は、阪神・淡路大震災の経験から学び、伝える活動をしているNPO法人ふたば/ふたば学舎・震災学習ラボ室長の山住勝利さんをお迎えし、災禍の経験を継承し、伝えることを議論しました。
このレポートでは、前半に山住さんのレクチャー(聞き手:宮本匠)、後半はナビゲーター2人(宮本、佐藤李青)や参加者を交えた議論をまとめました。
今回のテーマである「出来事を伝えるためにはどうすればいいのだろうか」ということに対する答えとして、ハンナ・アレントの『人間の条件』から、次のことばを、まとめとして使いたい。
まず見られ、聞かれ、記憶され、次いで変形され、いわば物化されて、詩の言葉、書かれたページや印刷された本、絵画や彫刻、あらゆる種類の記録、文書、記念碑など、要するに物にならなければ、そのリアリティを失う。
(ハンナ・アレント『人間の条件』(志水速雄訳)、ちくま学芸文庫、1994年)
自らの体験や考えを外に出すこと、すなわち「活動と言論」を通して「人間関係や人間事象の網の目を構成する」ことを話したいと思っている。
ふたば学舎は、神戸市長田区二葉町にあり、すぐ南側には長田港という港がある。建物は元々、1929年に設立された神戸市立二葉小学校だった。それが少子化により他校と合併し、いまは駒ケ林小学校になっている。校舎は地元の方々からどうしても残しておいてほしいという希望があり、それを神戸市がうけて、2010年から神戸市立地域人材支援センター(2016年、ふたば学舎に名称変更)となっている。ふたば学舎はコミュニティ施設で、コスプレ撮影会や、ヨガ教室、料理教室、まちの文化祭や夏祭りなど、色々なイベントや貸室利用が行われている。
私はここの指定管理者である「NPO法人ふたば」に属しており、担当しているのが「震災体験学習」という事業である。
阪神・淡路大震災の記憶と教訓をベースとしているのだが、もし26年前の阪神・淡路大震災での色々な問題が現代において解消しているのなら、伝えることもないだろうと思う。寺田寅彦の「津浪と人間」にもこれまで何度も災害が起こったので、もう防ぐことができるだろうと思うが、そうなっていないということが書かれている。例えば、2日前に東京と埼玉で震度5強の地震があったが、ブロック塀が倒れるというニュースがあった。阪神・淡路大震災のときにはブロック塀が倒れて何人かが亡くなり、2016年の熊本地震でもブロック塀が倒れて20代の若い方が亡くなり、2018年の大阪北部地震でも小学生が亡くなった。そういうことから考えても阪神・淡路大震災から26年経っていても、未然に防ぐことができていないことがまだまだ残っている。阪神・淡路大震災での記憶と教訓はまだまだ伝えていかなければならない。

ふたば学舎での震災学習は体験型の学習で、対象は全国の小学生、中学生、高校生、大学生で、学校へ出前講座に行くこともある。内容は語り部の体験談や避難所体験など、いろいろなメニューを組み合わせて行っている。
震災体験学習の流れとして次のようなものがある。
1、阪神・淡路大震災での二葉小学校周辺の被災状況の説明
震災学習の避難所体験で使われるふたば学舎の部屋は、実際に避難者が避難していた講堂である。その場所で阪神・淡路大震災のときの二葉小学校周辺の被災状況を説明し、それと同じような巨大地震に遭い、ここに避難したという想定で子供たちに参加してもらう。
そしてまず、
小学校のすぐ東隣には大正筋商店街という商店街があり、地震後に起きた火事で全焼し、上のアーケードだけが残っていた。小学校の北部もかなり広い範囲で火災が起きた。周辺はブルーシートがかけられている家が多く、全壊もしくは半壊だった。二葉小学校への避難者数は1月17日に1,170人であった。月日が経つと避難者数は減り8月に避難所が解消された。
というような説明を行う。
2、実際に避難者として考えてみる
被災状況を説明したうえで、参加する子供たちには4~5人のグループに分かれてもらい、そのグループを一つの家族に見立て、自分はどういう役割を担うのか決めてもらう。例えば、80歳の男性でいまは病気がある設定にしたり、犬や猫などのペットになったりする。そして阪神・淡路大震災と同等の巨大地震に遭った避難者になったと想像して、避難所で起こる具体的な問題を考えてもらう。
3、避難スペースづくり
グループに分かれて段ボールを使った避難スペースづくりをする。どういう寝心地であるのか、どういう問題が起きるのかを発表してもらう。
4、語り部さんの話
阪神・淡路大震災で被災経験がある人に話をしてもらう。例えば、震災当時は高校生で、今は長田港で漁師をしている方など、地元のたくさんの方に語り部として協力をしてもらっている。
5、炊き出し体験
お昼の時間には炊き出しボランティアが来たという想定で、ふたば学舎の炊き出しスタッフがつくったカレーを出す。子供たちは自分たちがつくった紙食器にポリ袋をかぶせて、そこにカレーを盛って食べるということをしている。
6、災害現場の知恵学習
神戸市の消防士をしていた方に、もし怪我した人がいたときに、どういう風に搬送したらいいのかといったことなどを災害現場の知恵の学習として学んでもらう。
7、まち歩き
グループごとにガイドを1人つけて、ふたば学舎周辺のまち歩きをする。周辺は再開発できれいなビル群になっているので、実際に阪神・淡路大震災のときの写真と見比べながら、どのくらい復興しているかということを考えてもらう。
このように震災体験学習では、「BASED ON TRUE STORIES(BOTS)」ということで被災の実話にもとづいて、参加者はその実話をなぞりながら被災者を模倣し、震災の記録と教訓を学ぶということを行っている。ストーリー仕立てにすると、共感力が高まるということが考えられる。


震災学習で伝えようとしていることを抽象化して言えば、「人、モノの関係の網」の様相ということになる。モノの関係とは、主に生産関係を示す。大きな災害に遭うと人やモノのいろいろな関係の網が切断されて、自分の生きている環境のなかの様々な関係性が崩れていく。そういうことを具体的に伝えたうえで、色々な関係が崩れるとどうなるかを子供たちに考えてもらう。
関係の網が切断されるということをコロナ禍でいうと、去年ジョルジョ・アガンベンという哲学者が書いたもの(『私たちはどこにいるのか?』高桑和巳訳、青土社、2021年)が話題になり、批判も浴びていた。アガンベンの文章のなかで、人間は精神的な生の経験と生物学的な生の経験が2つ合わさって分離できない状況であるが、コロナ禍においては生物学的な「剥き出しの生」に縮減され、生活のなかでつながりのあった様々な関係が切れ、孤立していくということが書かれている。
コロナで亡くなった人が葬儀されずに燃やされてしまうように、どんどん関係が切断されて「剝き出しの生」の状態になっていく。こういったことが阪神・淡路大震災の被災者にも大いにあった。被災者が「剝き出しの生」に向き合う状態になると、例えば仮設住宅で孤独死を迎えるということが起こる。あるいは逆に関係性を再構築して生活再建していく人がいる。
またその関係性の再構築という部分で見れば、「災害ユートピア」というのも一時的なつながりの発生という風に考えられる。二葉小学校が避難所になったときも、一時的なつながりができて、災害ユートピア的な場面があったようだ。二葉小学校の先生がまとめた記録集(神戸市立二葉小学校『震災3年の記録 やさしさわすれないで』、1998年)に次のような記録があった。
1月21日(5日目)23時。
トイレ用水、運搬順調に進む。何十人もの方で陽気なバケツリレー。避難者の団結を高めるきっかけとして、大きな役割を果たす。
トイレ用の水は、二葉小学校では長田港から海水を運んできていた。
こういう風に一時的にせよ、何らかのつながりが発生していたということが分かる。こういうことも震災学習のなかで紹介している。そして、震災学習では避難所生活で生じる関係の消失に焦点を当てて、そこから未来の防災、減災を考えるきっかけにしている。
また、26年前の避難所での生活はこんなものだったとか、災害弱者の人はこうなったということを伝えることによって、震災の記憶を継承し、最終的には疑似体験を通して自分事としての震災の記憶を参加者自身がつくるというかたちにしている。
ところで、震災学習には「学習」とついているように教育的な側面があるが、その点はレフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキーというロシアの心理学者の考え方を参考にしている。ヴィゴツキーによると、「生徒が自らを教育する」、「教師の役割は教育的な社会環境の組織者」であるという。ヴィゴツキーの有名な概念で、「最近接発達領域」がある。これは、子供たちの発達に段階があり、その伸びしろ分を「最近接発達領域」といい、そこを他者が支援して伸ばしていくという考え方である。
ふたば学舎での震災学習ではその考えをどのように取り入れているかというと、参加する子供たちにはどういう他者になるかを自分たちで決めてもらう。その時に子供は自分で考える「内なる他者」みたいなもの、つまり「他者性を欠いた他者」を設定することが多い。それは自分の理解範囲のなかの他者を自分の外にいる他者と捉えているためであり、教える側としては阪神・淡路大震災ではこんな人がいたと具体的な他者、自分の思い通りにならない他者の行動と心理をできるだけ教えるということをしている。こうした部分がヴィゴツキーのいう「最近接発達領域」ではないかと考えている。
ここで、参加した中学生の感想を紹介したい。
・ 震災が来たらその時に考えればいいと思っていたので、とても考えが変わる体験だったなと思いました。
・ 避難所体験では実際に体験して問題点などが分かり、語り部さんの話では体験したことを聞き、様子や食料の少なさがとても伝わってきました。
・ すごくこの体験は役立つし、全然興味がなかったけど、この体験学習で興味がわいてきて、これから気を付けないといけないと思った。
・ カレーがおいしかった。
また、思いがけない感想をもらったことがある。旅行会社の添乗員の方で熊本地震の3年くらいまえに震災体験学習に添乗して来られており、熊本地震の際にはボランティアに行かれた。そのときにここでの震災体験学習が役立ったとおっしゃっていた。
・避難所になった学校にボランティアに行くと指揮を執る人がおらず、マニュアルもなく、ガムテープなどの資材を渡されただけだった。何とかしようと思いホワイトボードを使って指示事項をまとめる中で、ふたば学舎でこういうことをしたなと思い出した。
思いがけずこういう方にも伝わっていることにとても驚いた。
一方、個々の被災体験にかかわるもので、伝達できないのではないかと思うことがある。個々の被災者の体験というのは、まとめればこうなるみたいに簡単に言えるものではない。情緒が混ざっているので、なかなか難しい。それゆえに「伝達不可能性」みたいなものがあるのではないかと考えられる。
渥美公秀の文章(「阪神・淡路大震災の「記憶」を伝える」『災禍をめぐる記憶と語り』ナカニシヤ出版、2021年)のなかで、阪神・淡路大震災を体験した人の記憶を体験していない人に伝えることについて書かれていた。人はそれぞれ悲しみを経験している。それを経験していない人が、経験している人の悲しみに共感することは難しいが、自分が持っている悲しみをもとにして「共感の不可能性」に共感できるのではないか。そういうことを通して阪神・淡路大震災の「<かなしさ>を守る」という。
これは最近だと、ブレイディみかこの著作(『他者の靴を履く』、文藝春秋、2021年)に出てくる、「他者に対するエンパシー=共感」というものに絡んでくることかなと思う。単純にかわいそうだねということでない。相手の気持ちを熟慮し共感する。シンパシーでなく「エンパシー」であるということである。
例えば、記憶の伝達による共感が生まれたことによって、阪神・淡路大震災を経験していない人が、震災の記憶を伝えていくという活動がされている。「1.17希望の架け橋」という10代~20代の若いグループが、阪神・淡路大震災を体験した人の記憶を体験していない人に伝えることをやりはじめている。こういう風に若い人が阪神・淡路大震災の記憶を伝えようとしているのを見ると、今後も阪神・淡路大震災の記憶は忘れられず伝えられていくのかなと思う。
私にとっては、自身の体験の伝達が難しいことがある。
私は阪神・淡路大震災のときに神戸市須磨区で地震に遭い、家が全壊し1階で寝ていた母が亡くなった。その後、色々なところを転々とした。もともと住んでいたところからかなり離れた仮設住宅に父と入ったが、地震から約1年後に父が母を追うように亡くなってしまった。ふたば学舎のある新長田に関する震災前の父との記憶は、幼少時に大正筋商店街にあった映画館でドリフの映画を見たり、帽子屋さんで野球帽を買ってもらったり、会話もしないで父の自転車の後ろに乗ってぶらぶらしたというものだ。父は無口な人だったため、震災前も後も会話などことばのやりとりがほぼないまま、亡くなってしまった。
このような自分自身の体験をどういう風にことばにできるのか考えたときに、何を言っても崩れてしまうということがあった。
震災後に読んだホフマンスタールの「チャンドス卿の手紙」には「わたしの症状といえば、つまりこうなのです。なにかを別のものと関連づけて考えたり話したりする能力がまったくなくなってしまったのです」という「ゲシュタルト崩壊」のようなことが書かれていた。「ゲシュタルト崩壊」とは次の中島敦のことばのようなことだ。
一つの文字を長く見詰めている中に、いつしか文字が解体して、意味の無い一つ一つの線の交錯としか見えなくなって来る。そういった形が崩れてくる。
(中島敦「文字禍」『山月記・李陵 他9篇』岩波文庫、2012年)
自分自身の震災の記憶に対することばの使いかたに関しても、同じような感じがある。いまでも生きている現実味がないところがあって、なんでこうなっているのかなということがよくある。そういったことから、震災の記憶を伝えるというのは難しいし、できないのではないかと思っている。
先の二作品に言及する古田徹也の本では
およそ何事かを経験し、またそれを振り返り、他者に伝える際に、人は言葉を用いないことができない。言語は自己とその外部をつなぐ不可欠の媒体(メディア)であり、ものを考え、それを伝えるために欠かせない手段(メディア)である。しかし、その肝心の言語が本質的に不完全なものでしかない。言葉は本来、線や音の集合に過ぎない。
(『言葉の塊の哲学』講談社選書メチエ、2018年)
と書かれている。ことばの不完全性についてなるほどと実感する。
他の哲学者で言うと、確か井上忠がことばには「繭化作用」、すなわち厳しい現実から守る繭の役目があると語っている。震災の記憶を表象するときに、ことばの繭化作用が働かずに、崩れていくということが個人的にある。きっと他にも被災した方で、家族が亡くなったり、家が全部なくなったり、あるいは大変な障がいを負ったりしたことによって、震災の記憶を上手く外に表すことが難しい方が多くいるのではないかと思っている。
さらに古田の著書には、ウィトゲンシュタインによる「ゲシュタルト構築」について触れられている。その構築において、「しっくりこないという感覚を介して、文字のアスペクト(相貌、表情)の変化へ」導かれる。しっくりとこないがゆえに、しっくりくる言葉を探すとか、違うもの、置き換えられるものを探していくということを通して、「ゲシュタルト崩壊」を逆に構築していくということだ。ただし、決まりきった常套句みたいなものを使っていくと、逆に記憶というものは忘れられる。そういうことから「言葉を選び取る責任」が生じるというのだ。
「ゲシュタルト崩壊」に対して私自身は、記憶を「異化」する、違うものにしてみるのはどうだろうかと考えたことがある。「異化」というのは、ことばのあり様を異なるものに化けさせるということである。
実際に2014年にふたば学舎で「被災の語り歌」を企画した。震災の記億を「異化」しようという試みで、阪神・淡路大震災の時に色々な歌をつくった人がいるのではないかと募集してみた。というのも私自身、震災の2年後に曲をつくったことがあったからだ。歌募集で集まった7つの曲をシンガーソングライターの石田裕之さんに演奏してもらい、2015年にCD『被災の語り歌』をつくった。うち5曲は石田さんに歌ってもらって、他の2曲は、英語でやると記憶の異なった側面が見えてくるのではないかと思い、被災者の短い言葉を英語に訳しての朗読になっている。それら2曲では、ふたば学舎で英会話教室をしていたアメリカ人の先生に朗読してもらい、バック演奏を石田さんにしてもらっている。
『被災の語り歌』はいくつかコンサートをして色んな人に聞いてもらい、CDを購入してもらった。売り上げは全額東日本大震災の寄付にした。
https://www.youtube.com/embed/t_kHVZewBzU?feature=oembed
震災アーカイブ=「被災の語り歌」 I Call Your Name -1995.1.17-
さらに、伝達ができなかったとしても、なぜ記憶を伝えるのかということを戦争体験の伝承を参考に考えたい。小松左京の「戦争はなかった」という短編(東浩紀編『小松左京セレクション1』角川文庫、2016年に収録)がある。太平洋戦争のときに中学生だった「彼」が、お酒を飲んでいるところで仲間に戦争のことを言っても通じず、どうなっているのだろうかという短編である。
「彼」は次のように言う。「現在の日常に変化がなければ過去の戦争の有無はどうでもいい」、ただそうだとしても「たとえ表面的にはまったく同じ「現在」が出現していたとしても、その世界はどこか根本的に、重要なものを欠落させているのではないか?」。
同じように、「阪神・淡路大震災の記憶がなかったらどうなるのか」とか、「記憶からなくなってもいいのか」と、私自身考えさせられるのだが、過去がないといまの重要な部分が抜けてしまうと思う。
安田武の『戦争体験―一九七〇年への遺書』(ちくま学芸文庫、2021年)には興味深いことが書かれている。安田は「戦争体験ということはほとんど絶望的である」とか「聞きたくなければ聞かなくてもいいのではないか」と考えはするが、それでも「戦争体験にこだわらなければいけない」と言うのだ。なぜかというと彼自身が、昭和20年8月15日から3日間続く戦闘のなかで、自分ではなく後ろにいたBがソ連軍に狙撃され戦死、あるいは神戸第三中学校時代の友人が消息不明という個人的な体験をしていて、戦争体験に固執せざるをえなくなっていたからである。
何故、伝達不可能かも知れぬ地点、まったく有効でないかも知れぬ方法を持って、はじめてはいけないのだろうか。そもそも、伝達が不能ではないかと断念せざるをえないような体験、存在自体が無効かも知れないと絶望せざるをえないような体験、−−〈挫折〉があった筈である。
伝達不可能にもかかわらず、その地点からはじめよということだろうか。それがなぜできるのか。やはり記憶の継承行為へのこだわりがあるからではないだろうか。
そうしたことを考えているなかで、昔読んだ大澤真幸の「もうひとつの〈自由〉―思考のヒント―」(有坂誠人編『MD現代文小論文』朝日出版社、1998年に収録)を再読した。そこでは、阪神・淡路大震災の「偶有性」、すなわち、あったかもしれないし、なかったかもしれないということについて述べられていえる。例えば阪神・淡路大震災のときは、すぐ隣にいた家族が亡くなるという体験をした人、タンスが真横ではなく真上に倒れていたら亡くなっていた人、それはすなわち、死ななかったけれど、自分が死んでいたかもしれないという経験をした人が多くいた。私自身もそうだった。そうした経験におけるどちらに転ぶかわからない様を「偶有性」ととらえて、震災の極限的な状態は「偶有性」を示すというのだ。そういった極限状態の経験が、表象不可能だとしてもその偶有性ゆえにか、震災についてなにか伝えないといけないと思うきっかけになっているのではないかとも考えられる。
震災の記憶、特に個々の被災の記憶を伝達することは難しい。不可能なことかもしれない。それでも伝達しようと思ったら、冒頭のアレントの引用にあるように、何らかのかたちで外に出さない限り消え去っていくだろう。言葉がなかなか見つからなくても、震災の記憶にこだわってしっくりくる言葉が出てくるのを待ち、なんとか記憶を伝えるということが被災者の責任というものになるのかもしれない。
宮本:「ゲシュタルト」というのがひとつのキーワードなのかなと思います。「ゲシュタルト」というのは色んな分野で色んな意味で使われていますが、いくつかのものをひとつのまとまりとして全体として認識する力とか、あるいはその部分の集まりに大枠として意味を与えるみたいな意味で使うと思います。でもそういうイメージだけじゃなくて、実は「ゲシュタルト化」するということは「物語にする」ということとも言い換えることができる。いくつかの出来事をひとまとまりの物語にして語るということです。
例えばコロナ禍になって最初は人と会えずに寂しかったけれども、家族との時間が増えて家族と過ごす時間の意味を見直しました。これはひとつの出来事で、家族との時間を見直したという大枠の意味付けのなかで、それまでの出来事が意味づけられていくわけですよね。
もっと言うと実は私というのもひとつの「ゲシュタルト」として構成されている。それが山住さんのお話にあったように、災害みたいな突然の悲劇によっていままでの日常が断ち切られる。人とモノの関係の網が断ち切られると、自分自身のこれまでの人生や、私というものに意味づけを与える大きな枠組みの「ゲシュタルト」が失われて、非常に不安定になってしまう。そこからどうやって「ゲシュタルト」を再構築できるかというのが、山住さんの最後のお話だったのかなと思います。
また、「偶有性」ということばを山住さんが紹介してくださいました。「可能ではあるけど必然ではない」と説明したりもします。災害に遭ったときには、他でもない私がこんな目に合わないといけないのかという思いをみんなするわけですよね。そんなつらい経験をするというときに、そこにはなんの必然性もないわけです。
大澤真幸さんが「偶有性」ということばを神戸の経験から引き出されたときに、彼が何を言いたいかというと、「ゲシュタルトが失われる」とか、「偶有的な経験をする」というのは辛いことなのだが、しかしそこにも見出すべき点があるということです。
亡くなっていたのは自分だったかもしれないという偶有的な状況に置かれている人は、自分というモノの「アイデンティティ」や自分という「モノの範囲」があいまいになっている。これは見方を変えるとエンパシーのような、まさに自分以外の人の感覚に否応なく引き寄せられるようなところが人間にはあるのだということです。
普段は人間が色んな人の身になったり、共感したり、それを通じて連帯をしたり、協力しあったりということが難しいようにみられる。だけど実は、震災のような極限の状態に置かれた人たちがどのようになるかということを見れば、人間というのがそもそも、共感してしまったり、「サバイバーズギルト」のように罪の意識を感じたりと、引き受ける必要のないことにまで責任を感じられるくらい、非常に他者に共感する力があるのだと理解できる。これが大澤さんの「偶有性」という言葉で見出されていることです。
これを踏まえると、ゲシュタルトが失われた状態からゲシュタルトを再構築するというときに、その再構築されたゲシュタルトというのは場合によっては、少し違っている可能性があり、そこがすごく大事なんじゃないかというのが、大澤さんの言いたいことなのかなと思う。
実際に他者に共感してしまうようなことを震災学習として記録し、伝承するということのなかでどうやってできるだろうかというのが、今日山住さんから伺ったお話のなかで、すごく大事なところなのかなと思いました。山住さんいかがでしょうか?
山住:「ゲシュタルト崩壊」や「自己の同一性が崩れる」というときに、それでも被災者にとっては震災というものにこだわらざるをえないというところがあると思います。
アレントは『人間の条件』で、人間の生活を「労働」、「仕事」、「活動」で分けています。特にアレントが強調しているのは、「活動と言語による社会との関係」です。そのために、言語を使って外に出さないといけない。そうしない限り、自分が持っている記憶が消えていく。例えば自分自身しか持っていないような家族の記憶に関しても、何か言葉や映像として外に出さないと、ないものになってしまう。そこには亡くなった人への責任も生じてくるのではないかなと思います。
一方で記憶をうちに飲み込んでしまう、忘却してしまう人たちも沢山いると思うので、そこはどうしたものかなと思ったりします。そういった難しいことに人間の持つ他者に対する共感力が働きかけられるという可能性もあるのではないかと思ったりもします。
宮本:冒頭に結論ということで、ご紹介くださったアレントの言葉はすごく印象的で、一見あの文字だけ読むと僕たちの常識的な感覚とは逆のこと言っていますよね。
僕らの常識的な感覚だと、生のリアルな体験があって、それが印刷されたり、写真になったり映像になると生の体験が目減りして、リアリティが伝えられなくなるのではないかという感覚があると思います。
でもアレントが言っていることはむしろ逆で、「物化されないとリアリティを失う」ということです。彼女はユダヤ系の政治学者で、ホロコーストということを大きな問題としてあるから、なかったことにされるということへの抵抗があって、ああいう言葉を残しているのかなと思います。
佐藤:山住さんは、26年経っても伝えることがまだ残っているということを仰っていましたが、時間が経つなかで伝えかたが変わることもあるのでしょうか?
山住:26年経つと、阪神・淡路大震災を経験した人の記憶も薄くなっていたりするので、その時の記憶を伝えることは年数がたつごとにどんどん難しくなっています。
ただ、新しい災害が起こったときに阪神・淡路大震災と比べて変わってないことが見つかり、それを伝えることができるということがある。具体的には避難所の状態、トイレが汚いとか、そういった「変わっていないこと」を、新しく起きた震災と比べて思い返して伝えたりしています。
語り部の方の語りが年を追うごとに変化している点は、東日本大震災のことや西日本豪雨など、ニュースで防災の知識みたいなものを身に着けて、そのことをお話されるようになってきているというところです。私としては、ご自身の経験されたことを伝えてほしいのですが、そういったことを付け加えたり、色々伝える内容が変わってきているということはあります。
佐藤:それが良いのか悪いのか、語り手の伝える技術が上がってしまうということですね。NPOの活動としては、ふたば学舎という建物全体を運営されていて、震災のことを伝える活動はその一部分ということなのですか?
山住:そうですね。指定管理者として「NPO法人ふたば」が神戸市から委託を受けていて、震災学習事業ともうひとつのメインとしては「人材育成事業」という将来の地域リーダーを育成するというのがあります。あとは、貸館事業ですね。
佐藤:この伝える活動は、山住さんとあと何名かでされているのでしょうか?
山住:私がメインで、実際に震災学習を行うときにはスタッフ何名かに協力してもらっています。スタッフは同じ年代の方々で、ずっと一緒に活動を続けています。また、語り部の方は、20数名登録して頂いています。
宮本:ふたば学舎での取り組みの特徴的なところは、実際に当時避難所になったというところに身を置いて震災体験学習ができるところだと思います。また、語り部の方で当時高校生だった方がふたば学舎でお話してくださるように、自分がいる学校で当時のことを知っている人が語り部としてお話してくれて、当時の写真も見る。そして体験をするという、「その場に身を置く」というところがふたば学舎の取り組みの重要なところだと思います。山住さんからご覧になって、そういう特徴があることで参加している学生の反応や変化はありますか?
山住:この学校自体が避難所になっていたということで、震災遺構みたいなオーラがあるのかもしれない。そのなかで震災学習を子供たちにしてもらうので、「過去にこのようなことがここであった」とか、「26年前はこんなところだった」と驚かれることはあります。かなりリアリティを持って体験してもらえていると思います。
宮本:参加者にとって、すぐには言葉にならない、でもそこに身を置いたことで生じる独特な経験が、「当時はこうだった」というお話にプラスして持ち帰ってらっしゃるのではないかという気がしますよね。

山住:何年か前に岡山の中学生を対象にした震災学習をした後に、ある女子生徒から「自分は西日本豪雨で避難所に行き、実際はこうだった」と言われた。もう一度フラッシュバックさせることはなかったか心配にはなったが、やっぱり自分自身が経験したことと重ねて、リアリティを感じてもらえたというのはうれしかったです。
佐藤:ことばの伝えかただけでなく、伝える環境も大事であることを改めて考えさせられました。伝えかたとして、歌の活動もあったと思いますが、どうして音楽だったのでしょうか?
山住:震災の記憶を身体を通したことばみたいなもので伝えられないかな思っています。
伝達の理想形としては大滝詠一さんの「君は天然色」という曲があります。作詞をした松本隆さんの亡くなった妹さんを追悼するような内容の歌で、冒頭の歌詞に「唇つんととがらせて」とあります。歌ってみると、その通りに唇をつんと、とがらせてしまう。その瞬間に歌っている人は、亡くなった妹さんになる。身体から出されることばを通して亡くなった人になるということを、震災学習でも自分がことばや身体を動かして被災者になるとか模倣してみるということができたら、そして、それをことばでつくれたら理想だなと考えています。
宮本:ことばを通してしか僕たちは経験を記録したり、誰かと共有したりできない。でも、ことばは不完全だというお話もありました。ことばでできることと、ことばでできないことを別々のものとして扱いがちですが、実はそうじゃない。
身体性を介したことばは、ことばにならないものも、ことばにくっついていて、それを上手く生かしてあげれば、文字だけ抽出したときにはできないようなことができるのだろうなと思う。同じ語り部のことばでも、ふたば学舎で聞くのと、別の場所で聞くのと、冊子にして読むのとでは全然違うのでしょうし、そういう風に工夫すればいいのかと気づかされました。
辻(参加者):最初に、人とモノ、関係の網のお話がありました。それと同じように、記憶というモノとか経験というモノも、あの日のあれが美味しかったとか、意外な人が助けてくれたみたいな断片的な記憶と繋がっていると思います。でも、そういった震災すべてを語ることはできない断片的な記憶を総称するものはなく「体験談」という言葉でくくられてしまう。「体験談」という一言だけでは語れないものがあると思います。
例えば、ブレイクアウトルームでのディスカッションで、こんなお話がありました。「身近な人を亡くした。その人がカレーをつくってくれるのが得意な人だったから、震災の後カレーを食べなくなった。自分にとって、震災はカレーだった。でもなぜかは言えない」という経験が、もしかしたら山住さんが紹介してくださった「カレーがおいしかった」という震災学習への参加者のコメントの背景にあったかもしれない、と。
震災の経験というものを、誰かの強烈な体験談によって知るものでなく、もう少し断片的で色んな記憶が集まっていくことで理解していくこと。たどり着かないといけないものというよりは、ことばや記憶が積み重なっていけるものとして受け止めることが出来ればいいのではないかなと思います。もう少し、「人に優しい不完全さ」みたいなものが記憶にも影響されてもいいのかなと感じました。
山住:体験談として、はじまりがあり、上手く終わるというかたちで話すことはなかなか難しいですよね。その一方で、震災のつぶやきみたいなものを集めることをされている団体もあるので、震災の記憶を記録するという方法のひとつとして、つぶやきを集める、Twitterで集めるといったこともあると思います。
宮本:どうしても震災のことを語るということは、色々つらい体験をしたから、それが繰り返されないように、どういう教訓を引き出せるかという面があります。それはそれで重要ですが、教訓みたいな視点で見ると、そこからこぼれるような出来事や断片も沢山ある。
これはゲシュタルトを必ずしも、もう一度構築しなければいけないという話ではない。「しっくりくる言葉がない」という状態のなかで、それでも言葉を探すということはゲシュタルトはやや崩壊したままだけど、それを無理にひとまとまりにしなくてもいいじゃないかという路線なのかと思ったのですが、それは誤解ないですか?
山住:そうですね。必ずしもゲシュタルトを再構築しないといけないわけではないと思います。
宮本:山住さんからヴィゴツキーの「最近接発達領域」のお話がありました。教える人から学ぶ人へひとまとめのパッケージをどれくらい伝えられているかではなく、関係の網のなかで一緒に学び、伸びしろにアプローチしていくのが学習なのだというのが彼の学習観だと思います。
そういう考えかたを大切にして、参加者の方と一緒に学ぶために、経験者である山住さんがお手伝いして参加型の学習をされているということでしたが、学習のなかで子供たちと具体的にどういうやりとりをされているのでしょうか?
山住:はじめに子供たちに想定を考えてもらうのですが、そこで考えることは自分がこれまで接してきた人など、自分の理解の範囲のなかでの他者理解だと思います。そこに、こちらから阪神・淡路大震災の避難所では「こういう人がいた」とか、子供たちが想像していなかった人のことを伝えて、それを自分の考えの伸びしろに生かしてもらい、他者理解を発展させることをしています。
また「こういう人がいた」と言っても伝えるほうもその人のことを完全に理解しているわけではないので、お互いに想像力を働かして、こういう風に考えていたんじゃないかなとか、子供たちに発表してもらうときにやりとりをするかたちにしています。
佐藤:それはかかわる側も変わっていくということですよね。自分が持っているものを伝達するというよりも、そこからの反応によって自分自身も変わってしまうような。
山住:そうですね。新しい発見はあったりしますね。
佐藤:その発見が時間の経つごとに、変化していくこともありますか?
山住:それはありますね。役割を考えてもらうときに結構多いのは、家族構成が母親一人、子供一人のような母子家庭です。阪神・淡路大震災のときは4人家族がよくある家族構成だったが、違う構成の家族を提示してきたりするので、そこは変化を感じますし、こちらの対応も色々考えて、調整させてもらうということがあります。
あとは子供たちが使っているメディアが変わってきていて、阪神・淡路大震災のときはスマホがなかったので、どういう風に災害時の情報を入手するかというところは変わっていますね。
宮本:災害の経験を伝える活動は、色々な人が色々な場所でされていると思いますが、多くはできるだけ当時あったことを克明にそのままにいかに伝えるか、それが分かってもらえないときにいかに分かってもらうかというような、伝える側の枠組みはあんまり変わらないケースのほうが多いと思います。
ふたば学舎の取り組みは山住さんも一緒に学びながら、お互いの他者性を突き合わせながら変化していくという、本当に特徴的な震災学習館だと思いますね。
小川(事務局):例えば「阪神・淡路大震災追悼式典」のような、公的な物語にはどのような意義があるのでしょうか。大きな物語、モニュメンタルなものと山住さんはどういう風に向かい合っているのかを教えていただければと思います。
山住:追悼行事は、毎年行われることに大きな意義があると思っています。やっぱり阪神・淡路大震災も26年になるので、どんどん忘れられていくだろうし、神戸市内でも震災を経験している人が4割を切っているので、そういう意味でも、何らかの追悼行事は必要だと思います。公的なものなので、ある人は嫌だと思うことはあっても、大きな枠組みのなかで記憶を残すことは大きな意義があるかなと思っています。
宮本:どうしてもああいう公的なものは意味やメッセージを与えてしまいますよね。意味とかメッセージが力になるという人もいるかもしれないし、山住さんが仰った伝達不可能性のように、どうしても自分のなかでしっくりこないような経験がこういう大きな出来事には必ずあると思います。そうすると大きな物語からこぼれていくものがありますよね。
佐藤:公的なモニュメンタルなものによって、社会的に想起することは時間が経つほど必要になってくる。同時に、時間が経つことは、本当はそうじゃないこと、いままで語れなかったことが沢山出てくるタイミングになることでもある。それは大きな枠組みでは、語りづらいことかもしれない。そういう意味で、ひとりひとりの経験を語ることができる場が、時間を経ても、複数あるかも重要だと思います。
宮本:そう思います。災間で毎年のように水害起きる状況になると、例えば7月、8月、9月は無数の何とか水害から何年みたいな日があります。
例えば東日本大震災の時に起きた紀伊半島水害は、「水害から何年」のような報道はローカルメディア以外にはないです。神戸や東北のように非常に大きな災害で、全国ニュースのなかで1年に1回とはいえ社会全体として振り返る機会がある災害と、もはや何年経ったという振り返りさえされないような災害を比べると、1年に1回公的な物語が与えられることによって「いやいやそうじゃない」と言える災害と、そういう機会がないばかりに、そうじゃないということもなかなか思い出しにくくなる災害が、これから増えていくのだろうなと思います。ポジティブネガティブ両方ありますが、公的な物語やモニュメンタルな振り返りはあったほうがいいと思います。そしてこれから少なくなっていく可能性が高いので、そういうときにどういう工夫ができるかが大切ですね。
山住:色々な行事で過去の忘れ去られそうな災害の記憶を残すということも重要ですが、他にも色々なメディアがあると思います。
例えば、宮崎駿監督の「風立ちぬ」を見て関東大震災を思い起こすということがあります。映画、音楽といったアートは、災害の記憶を残していくについてはすごく強力なものかなと思っています。
佐藤:確かに、モニュメンタルなタイミングになると、忘れないとか忘れないためにどうすればいいかということが号令のようになるタイミングだと思います。ここで議論しているような作品とかメモリアルな施設のような、思い出すための装置みたいなものが社会に多様にあって、距離が遠くても何か思い出すべきタイミングが沢山生まれてくるというのがきっと望ましいのだろうなと思います。
執筆:氏家里菜
日時:2021年10月9日(土)14:00~17:00
場所:オンライン(Zoom)での実施
執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28

執筆者 : 宮本匠
2022.01.28
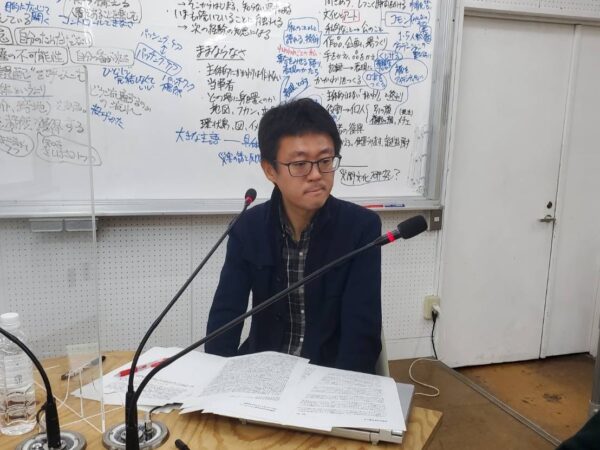
執筆者 : 高森順子
2022.01.28

執筆者 : 高森順子
2022.01.19

執筆者 : 高森順子
2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 高森順子
2021.09.07

執筆者 : 高森順子
2021.08.18
