
“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)
執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28

2021年7月から12月にかけて全6回で開催したディスカッション「災間の社会を生きる術(すべ/アート)を探る」。本プログラムのナビゲーター・高森順子(愛知淑徳大学助教/阪神大震災を記録しつづける会事務局長)がディスカッションを振り返りました。ゲストや参加者との議論を通して見えてきた、災間を生きるための態度やふるまいとは?
約半年間のディスカッションシリーズで取り上げられた実践(ないしは、表現と名指された実践)は、「実践」という言葉があらわすように、静的な状態ではなく、動的で変化に富んだ「出来事」だった、といえるだろう。ゲストに迎えた吉椿雅道さんの、被災地の土着知を生かすための「いるだけ」支援(第2回)、瀬尾夏美さんが「最も美しい表現」であると見出した「おばちゃんたちの花畑」(第3回)、山住勝利さんの、伝わらなくても伝える、という姿勢からつくられた「被災の語り歌」(第4回)、坂本顕子さんが、先入観なしに「美しい」と感じることから知ってほしいとキュレーションした《願いの貝》(第5回)。たとえば《願いの貝》のように、いまも肉眼でモノとして見ることができるものもあれば、「おばちゃんたちの花畑」のように、かつては見ることができたけれども、いまは見られないものもある。「被災の語り歌」は、YouTubeで何度も同じ収録を視聴することができるが、一回きりの生演奏というかたちもありうる。「いるだけ」支援に至っては、これまでもこれからも生生流転していくものであるから、固定して見ることはできない。
《願いの貝》は、ある女性が浜辺で拾い集めた大量の貝殻を、作品として美術館に展示したものだ。しかし、《願いの貝》はモノではなく、出来事である。このシリーズに参加した方々、そして、レポートを見届けてくださった方々には、この言葉は腑に落ちるのではないか。それでも、いやいや、貝殻はモノでしょう、と思う方は、この二つの言い回しを見てほしい。
「貝殻、美術館にありましたよ」
「貝殻、美術館でありましたよ」
どちらも不自然な言い回しには響かないのではないか。二つの言い回しの違いは、格助詞の「に」と「で」である。格助詞「に」は、モノの場所を示す。一方、格助詞「で」は、出来事の場所を示す。坂本さんの語りを聞いた、ないしは読んだ私たちが、モノであるはずの貝殻に出来事の格助詞がついても違和感を感じないのは、坂本さんの語りをとおして、私たちは貝殻を《願いの貝》という「出来事」として、その一端を知ることができたからではないか。この、本来ならば文法的に間違っているはずの言葉が受け入れられることについて、言語学者の定延利之(2008)は、状態を体験する、言い換えれば、状態を「生きる」ことで、状態は「出来事」になるため、それが文法をも揺るがすという。
情報を知識として語るのではなく、出来事を体験として語る。このシリーズで登場した実践は、「彼の」「彼女の」話ではなく、「わたしたちの」話として共有された。一方で、これらの実践をめぐる語りを知らない人びとは、それらがモノではなく出来事であるがゆえに、見えにくく、捉えがたい。《願いの貝》を再び引くならば、文字通り、それは貝殻である。陳列された貝殻のうちのひとつを手にとり、もともとあった浜辺に置いたならば、それは風景と同化し、見失われるだろう。貝殻は、「これはなんですか」と問われなければ、静的なモノとして捉えられるものである。
それらの貝殻は、坂本さんがキュレーションという技術をもちいて《願いの貝》として美術館に展示すると、モノから出来事へと変貌する。貝殻は、ハンセン病療養所沖縄愛楽園で暮らしている上原ヨシ子さんが、日々、浜辺へ行き、貝殻を拾い続けているという出来事であり、この出来事の積み重ねに至る以前の、ハンセン病の罹患、療養所への入所、パートナーとの出会い、妊娠への憧れ、避けられぬものとしての堕胎、胎児の浜への埋葬という出来事の連なりであり、さらには、彼女の部屋いっぱいの貝殻に美しさが見出され、《願いの貝》という作品として公に差し出されるという出来事の連なりである。貝殻は、《願いの貝》と名付けられ、展示されることで、静的に押し留められた情報から、動的な出来事となる。
このシリーズに参加してくださったみなさんは、意識の濃淡はあれ、歴史化した、ないしは歴史化しつつある情報を、瑞々しい出来事として分かち合うにはどうすればよいのか、関心を持ってこられた。シリーズ最終回の宮本匠さんの言葉を借りれば、「わがこと」ないしは「ひとごと」に切り縮められた出来事を、「われわれごと」としてひらくにはどうすればよいか、思索と実践を重ねてこられたのではないか。以下では、問題を個に帰結せずに、「われわれごと」にするためのヒントとなる、「共話」という概念について述べることで、論を進める。
情報学研究者のドミニク・チェン(2020)は、著書『未来をつくる言葉』において、言語教育学者の水谷信子によって定義された「共話」というコミュニケーションのあり方が、他者と共在できるようなかかわりをつくる鍵になるという。同書には、共話の例として、以下の短いやりとりが挙げらている。
A「今日の天気さぁ」
B「うん、本当に気持ちいいねぇ」
Aの言葉は、文章として完成していない。「今日の天気さぁ」に続く言葉は、「良いねぇ」、「寒いねぇ」、「急に雨になったりしないかな」、はたまた「一日中家にいるからどうでもよくない?」、さらにはもっと違う言葉なのか、Bにはわからない。ただ、このやりとりにおいて大事なのは、「あくまでBがAの意を受け取ろうとしている点」(チェン, 2020, p158)だという。また、その「受け取ろう」という意の表明を、「うん」という相槌からスタートしていることも特徴的だという。共話は、「途中のフレーズを未完成のまま相手に委ねたり、相槌を打たせる隙を与えたりする話法」(同書, p158)であり、「隙」があるからこそ、相槌も頻繁に差し挟まれる。「うん」「へえ」と声に出したり、声は発さずに首肯するといった動作としての相槌は、意志によって抑制するのは困難である。ただ、経験に基づいて意識的に使用することも可能である。そして、いつも通り、やりとりの「隙」に相槌が差し挟まれれば、これが相槌によって支えられていることには気がつかないが、相槌がなくなった途端にやりとりは不自然になり、話し手や聞き手に違和感を生じさせもする (Ekman,1969)。
シリーズ最終回も終わりにさしかかったとき、宮本さんがアメリカ人の友人に逐次通訳をしながら東北の被災地を巡った際に、「匠、訳してないやつがあるぞ、君がさっきから言っている『へえ』はどういう意味だ」と聞かれたことを話してくださった。このやりとりは、「共話」的態度で人びととかかわる宮本さんと、「対話」的態度でそれを聞こうとする海外の友人との、言語行為をめぐる違いがある種の「おかしみ」として現れたエピソードだと思う。「対話」(dialogue)は、定まった主題にたいして、お互いの考えを積み上げて論じるときに適している。一方「共話」(Synlogue)は、フレーズの主語が共有されたり、「隙」に相槌が打たれることで、お互いの差異がやりとりのなかに融け込んでいく(チェン, 2020, p164)。人びとは普段、「共話」か「対話」かは意識せずに、「対話」のなかに「共話」が瞬間的に顕現したり、「共話」から「対話」に発展したりしながら、やりとりをしている。英語圏においては、文の途中で相手にその先を委ねたり、その「隙」に相槌を打ったりする「共話」は、稚拙なコミュニケーションであるとみなす傾向がある一方、日本においてそれは、やりとりを手助けし、関係を円滑にする技術の一つとして根付き、磨かれてきたという(水谷, 1993)。
自己で完結させず、未完成のまま相手に手渡し、そこからともに、その道行きを楽しむ。水谷はそのような「共話」的な態度を「ぬくぬくとこたつでくつろぐよう」なあり方だと表現している。そして、その「共話」的な話し方が、私たちの生活をどんなに支えているか、と指摘する。チェンは、「共話」的態度の力能について、自他の境界を解かし、「わかりあえなさ」を静かに共有するためのコモン(共有地)となると、期待を込める(チェン, 2020, p198)。
私は、このシリーズの途中、死にゆく私の父を画面越しに見つめる日々を過ごした。新型コロナウイルス感染症に罹り、病と対峙する父とともにある方法はないかと模索した。その間、約2ヶ月に亘り、私はこのシリーズのナビゲーターの役割を降りた。理由はどうであれ、社会人としての役割を果たすべきとの考え方もあるだろう。ただ、私は、あの日々を、ままならなさに押し流されるのでもなく、否認に転じて無かったことにもせずに、父と私自身の尊厳を失わずにいられたことに、少し胸を張っている。
声を投げかけること、そして、それを確かに受け取ったと表すこと。このような応答は、災禍によって突然に断ち切られることがある。災間に生きる私たちは、やりとりがいつ断ち切られるかわからない不安や恐怖を抱きつつ、それでもなお、やりとりのなかを生きている。災禍の渦中にあるとき、人は、自らが再び声を出せる日がくるまで、待つしかない。ただ、「待つ」というのはそう簡単ではない。渦中に巻き込まれていることを隠したい、私は渦中にはいない、そもそもここは渦中ではないと思い込みたい。これらの誘惑から、かえってあまりに多くを披瀝してしまったり、思ってもいないことを口にしたり、身を硬くして沈黙を貫いたりしてしまう。焦るほどに、その誘惑は加速する。それは結果として、さらに深い悲嘆の日々を過ごすことを招くかもしれない。そのような引き裂かれのなかにいる私を、佐藤李青さん、宮本匠さん、スタッフや参加者のみなさんは、再び声を出せる時がくるまで待っていてくださった。私は、みなさんが待ってくれているはずだと、信じることができた。そのことは私にとって光だった。
自ら主体的に実践を完結させずに、未完のままに、手渡し、手渡される関係のなかで生きる。「共話」的態度として生きるとは、「私」という主体がゆらぎ、個と個の境界がにじんでいくということだ。そのような主体の「ゆらぎ」と境界の「にじみ」は、これまで抑圧されてきた出来事と、それをめぐる物語を見ることへの回路をつくり、それらを社会の最前へと連れ出す可能性をもつ。美術史家のクレア・ビショップ(2020)は、現代美術館の先進的な事例をもとにして、創造的なキュレーションとは、出来事と出来事を新しい仕方で結びつけ、既に確立している分類法、専門分野、媒介、作法を撹乱し、ダイナミックな再読解へと開いていくものであると述べている。そしてそれは、星座的布置(constellation)と称され、「オルタナティブなものを可視化するための第一の手段」(ビショップ, 2020, p81)となるという。
表現という名の実践が誰かのもとに届き、相槌が打たれ、そこから応答がはじまることに賭けること。賭けに出る手前で、自らの目の前の世界がその「賭け」に出るにふさわしいものだと信じること。実践者にそなわるべき態度とは、そういうものであるし、それは独力でつくるものではなく、ともにつくっていくものだ。私は、このシリーズにかかわることで、災間の社会に生きる態度を知ることができた。
クレア・ビショップ(2020)『ラディカル・ミュゼオロジーーつまり、現代美術館の 「現代」 ってなに?』月曜社.
ドミニク・チェン(2020)『未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために』新潮社.
Paul Ekman and Wallace V. Friesen(1968)”The Repertoire of Nonverbal Behavior; Categories, Origins, and Coding”, Semiotica 1(1), 54-58頁.
水谷信子(1993)「「共話」 から 「対話」 へ」『日本語学』12(4), 4-10頁.
定延利之(2008)『煩悩の文法 体験を語りたがる人びとの欲望が日本語の文法システムをゆさぶる話』ちくま新書.

執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28
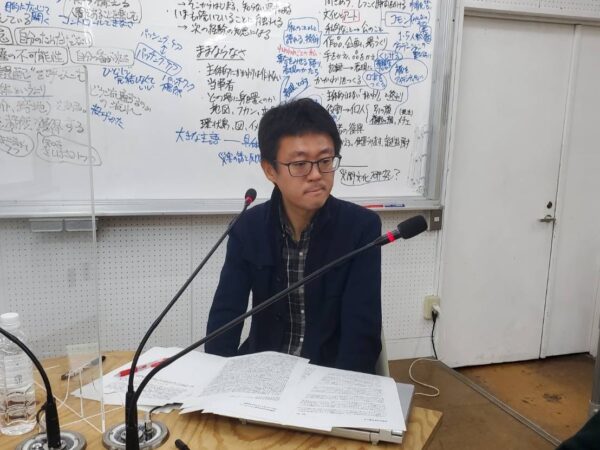
執筆者 : 宮本匠
2022.01.28

執筆者 : 高森順子
2022.01.19

執筆者 : 高森順子
2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 高森順子
2021.09.07

執筆者 : 高森順子
2021.08.18