
“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)
執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28

災禍の現場に立つには、いったい、どんな態度や技術、方法がありうるのか?災害復興の現場に多様なかかわりかたをしてきたゲストに話を伺うディスカッションシリーズの第5回目は、ハンセン病や水俣病、平成28年熊本地震、令和2年7月豪雨などの災禍にたいしてアプローチをしている熊本市現代美術館学芸員の坂本顕子さんをお迎えし、アートの表現とそれを支える仕組みが、その土地の災禍にどのようにかかわるのかを議論しました。
このレポートでは、前半に坂本さんのレクチャー(聞き手:佐藤李青)、後半はナビゲーター3人(宮本匠、高森順子、佐藤)や参加者を交えた議論をまとめました。

当館の学芸員は5人。少ないからこそ、全員なんでもやる、でやってきた。
初代館長は田中幸人さんだが、現在の根幹は二代目の南嶌宏さんがつくった、と私は思っている。立ち上げのときに南嶌さんは学芸課長をつとめており、私は彼に学芸員として拾ってもらった。彼の部下として奔走した日々が、私の財産になっている。課長から館長になられたあと、南嶌さんは女子美術大学へ移り、58歳で早逝。いま教えを乞うことはできないが、これまで教えていただいたことのインパクトは未だ強くある。
南嶌さんは私を含め、学芸員にたいして、養護学校(現在の特別支援学校)、盲学校、聾学校、リデル、ライト両女史記念館(ハンセン病患者の救済に尽力した女性宣教師を顕彰した施設)、ハンセン病療養所、水俣病資料館に行って勉強してこいと指示した。「私、一応美術の学芸員なんだけどなぁ」と思いながらも、いろいろなところに出向いていった。二言目には「聖書を読め」。他にも、「インドに行け、アウシュビッツに行け、作家に会え、足元を見ろ」など、よく言われていたことをいまでも思い出す。熊本という場所で現代美術館をつくるときに、現代美術だけやっていては駄目だと知った。たしかに現代美術は専門としてやるけれど、その土地で過去に何が起きて、いま何をしなければいけないのか、それを見ようとしなさいと南嶌さんは考えていた。
この姿勢を最初にはっきりと打ち出したのが開館記念展「ATTITUDE2002」。毎日床に倒れ込みながら、半泣きでつくった思い出深い展示。マリーナ・アブラモヴィッチ、ジェームズ・タレル、宮島達男、草間彌生さんなどの現代美術の作家たち、お笑いコンビの「いつもここから」、熊本県立熊本養護学校の伊藤隆哉、藤岡祐機、渡邊義紘さんなど、個性溢れる作家たちの作品を展示した。今回はそのなかでも、遠藤邦江さんと太郎君と、ジュン・グエン=ハツシバさんについて詳しく取り上げたい。

遠藤邦江さんは1939年、長崎県生まれ。1953年にハンセン病療養所菊池恵楓園に入所された。「ATTITUDE2002」展は、遠藤さんと息子の太郎君に参加してもらった。遠藤さんと太郎君との出会いは、美術館の根っことつながっていると思う。菊池恵楓園は熊本市の隣の合志市にあり、美術館からは車で25分ほどのところにある。総面積はおよそ18万坪、園の周囲は3.9㎞におよんでおり、日本最大の国立療養所として知られている。居住棟、病院、野球場、教会など、様々な施設が立ちならんでいる。誰でも入ることができるので、近所の方が散歩されている様子もみられる(現在はコロナのため制限中)。
はじめて私が恵楓園に行ったとき、人の一生のすべてが園内で完結することに驚いた。南嶌さんが遠藤さんに注目したのは、テレビのローカル番組で偶然目にしたことがきっかけだった。遠藤さんは、若くして恵楓園に入所され、園のなかでご主人と出会い結婚した。当時は入所者が妊娠することは事実上禁じられ、堕胎も行われていた。遠藤さんもそのことはわかっていたが、女性として一度は妊娠してみたいと思っていた。妊娠した遠藤さんは、堕胎をした。その経験のあと、デパートである人形と出会う。
もともとは女の子として売られていたそうだが、それを気に入った遠藤さんは「太郎君」という男の子として、夫婦で大事にしてきた。太郎君はかわいい顔をしているが、53歳になる(令和3年現在)。そんな太郎君と遠藤さんの日常はとても胸打つもので、南嶌さんはそれを人々に伝えたいと考えた。南嶌さんは「太郎君を美術館にお泊まりさせてください」とお願いして、遠藤さんは了承してくれた。「お泊まり」というのが、南嶌さんらしいな、といまも思う。「展示させてください」とは言わない。南嶌さんは私たち学芸員に、「太郎君が夜一人だと寂しいから、消灯のときには学芸員室に連れて行って、お布団かけて寝かせてやってくれ」と言っていた。私たち学芸員は朝出勤すると、展示室に太郎君を連れて行った。そういう日々を繰り返すなかで、モノとしての展示ではなく、こころを展示するということを学んだ。
菊池恵楓園には金陽会という絵画クラブがある。毎週金曜日にみなで集まり、絵を描くことが心の拠り所にされてきた。そこに訪問した南嶌さんは、それらの作品を「光の絵画」と名付け、以後、「光の絵画展」として展示を続けてきた。
木下今朝義さんは6歳でハンセン病を発症し、17歳のとき菊池恵楓園に移り、2014年に99歳で亡くなるまでそこで過ごした方。小学校に一年間しか通えず、その短い学校生活のなかでも病気のことでいじめられていたという。《遠足》(1996年)は、一度だけ行った遠足を思い出して描いたもの。金陽会で描かれる作品には、寂しさや怒り、疎外などを直接的に想起させるものもある。木下さんのこの絵は一見、牧歌的で穏やかだが、その内に秘められた悲しみを想像すると胸がしめつけられるようだ。
「光の絵画展」として続けてきた展示は、2007年に「ATTITUDE2007」で集大成として結実した。日本全国、そして海外では韓国と台湾のハンセン病療養所を踏破することを目標に調査し展示を行った。
同展のポスターには、青森にある国立療養所松丘保養所の成瀬テルさんの若き日の写真を使用した。テルさんが「ちょっと見て欲しいものがある」と言って、そっと手渡してくれたのがこの写真だった。当時20歳のテルさんが、療養所の出し物のために布団のはぎれなどを使って作られた衣装を纏い、満開の桜の下でポーズをとっている。その写真からは、彼女がハンセン病を患っていることは窺い知れない。写真を撮影したあと、症状が悪化し、重い後遺症が残った。この写真には、光輝く青春そのものが写されているし、それを誰かに見てもらいたいという気持ちがとても理解できた。テルさんに「この写真をポスターに使いましょう、私たちの伝えたいことが詰まっている」というと、照れながらOKしてくれたと言う。

南嶌さんのサブとして、ハンセン病療養所に関わる展示を担当してきた蔵座江美学芸員は、その後2015年に当館を卒業し、現在は一般社団法人ヒューマンライツふくおかの理事として、菊池恵楓園絵画クラブ金陽会の作品調査や保存活動をはじめ、全国のハンセン病療養所で調査・記録活動を続けている。蔵座さんが当館を離れたことで、そのあとをどうやって引き継いでいくか。南嶌さんや蔵座さんの実践を踏まえて、2020年に私が担当した展覧会が「ライフ 生きることは表現すること」だ。

本展は、「弱さとは何か」というテーマで、東京オリンピック・パラリンピックを念頭に置き、11組の現代アーティストからロボット研究者、それを支える人を含めて紹介した。

会場では、ハンセン病療養所沖縄愛楽園の上原ヨシ子さんが集めた《願いの貝》を久しぶりに展示した。この貝殻は、上原さんが堕胎した赤ちゃんを埋めた浜に、何度も訪れては拾い集めたものである。当時、訪問した際に、部屋に並べられた美しい貝殻を「熊本で紹介させてください」とお願いすると、快諾してくださった。熊本に持ってきた後にも、どんどん貝殻が送られてきた。貝殻はいわゆる美術品ではないが、時に作品以上に「語る力」を持っている。
「水俣」というテーマも外すことはできない。開館記念展「ATTITUDE 2002」では、ジュン・グエン=ハツシバさんの映像作品《メモリアル・プロジェクト ナ・トラン、ベトナム—複雑さへ—勇気ある者、好奇心のある者、そして臆病者のために》(2001年)を展示した。ジュンさんは日本とベトナムの両方にルーツを持つ。この映像はベトナムで撮影したもので、海のなかで若者たちがシクロ(自転車タクシー)を漕ぎ進む。苦しくなると、水面に浮かんでは息継ぎをし、さらに潜って漕ぎ進むという動きに、日々の暮らしをなぞらえて表現したものだ。この作品からは、圧倒的な海の美しさと対比して、暮らしの苦しさが迫ってくる。ジュンさんが水俣に対して心を寄せていたのは、急激な経済発展により、ベトナムでも同じような公害問題が起きていたためである。

展示にあたり、熊本で滞在制作した映像作品が、《Memorial Project Minamata: Neither Either nor Neither – A Love Story》だ。水俣と牛深の海で撮影されたこの作品は、「それではないが、無いわけでもない。無いわけではないが、それでもない」という矛盾をはらんだタイトルがつけられている。当時、漁船を借りて、合宿状態で担当の冨澤治子学芸員は撮影を支えた。ジュンさんはその後、ベトナム、水俣、沖縄の三部作を完成させた。
2003年に開館記念展vol.3として行った「九州力 世界美術としての九州」展では、写真家の塩田武史さんを紹介した。塩田さんは法政大学在学中に水俣病に関心を持ち、1970年に水俣に移住し、15年間水俣に住みながら撮影を続けた。

久しぶりに当時の会場写真を見たが、この並べ方は南嶌さんらしいと思った。塩田さんの写真のあいだに、前衛芸術集団「九州派」の田部光子さんの絵画を置いている。本来なら両者は分けて展示した方が見やすい。しかし、鑑賞者が違和を感じるようなでこぼことした配置にすることで、南嶌さんは九州の根っこにマグマのようにたまっている、患者さんや女性たちの叫びを伝えたいと思ったのではないか。
その後、学芸各自のスタンスで、「水俣」に関わっている。学芸員の冨澤さんは、写真家の石内都さんが石牟礼道子さんを撮影した《不知火の指》シリーズを「誉のくまもと」展(2017年)で紹介した。本作は晩年の石牟礼さんの手足をクローズアップして、やわらかな自然光で撮ったもので、幸い、展示のあとに当館で作品を収蔵することができた。
最晩年の石牟礼さんと共鳴していたのが、熊本在住の坂口恭平さん。「建てない建築家」としてデビューし、現在は作家としてさまざまなメディアで表現を行っている。「ライフ」展(2020年)では、「海底の修羅」(作詞:石牟礼道子、作曲:坂口恭平)を、坂口さんが自作のギターを弾きながら歌うライブパフォーマンスを行った。
現在、一押しのアーティストは、写真家の豊田有希さん。当館のギャラリーⅢで開催した「あめつちのことづて」展(2021年)では、時代の波に翻弄されながらも、昔ながらの暮らしを営む芦北町黒岩地区の人々を撮影した約70点の写真を紹介した。豊田さんは、山間地で水俣病に苦しむ人々がいることを報道で知り、黒岩地区に通うようになった。そして現在は移住して写真を撮り続けている。水俣病に関する問題は、いまだ係争中のものもあり、決して過去のことではない。しかし、何かのきっかけがないと、学ぶ機会が訪れないのも事実だ。そんな多様なきっかけを作っていければと思う。
次に、美術館が直面した災害を中心に話をしていきたい。
平成28年(2016年)熊本地震では、当館は免震構造のビルのなかにあったため、一部作品が落ちたりしたが、額に傷がついた程度で甚大な被害はなかった。ただ、問題だったのは空調が止まったこと。別の美術館からお借りしている作品もあったため、それらは空調が効いている県外の倉庫に移すことになり、余震が続くなか、トラックに作品を載せて長崎に持って行った。私たちの館は財団運営のため、行政の決定を待たずに動かすことのできる自己資金が多少あった。それを使って、修繕する業者さんと早めに契約を結び、美術館再開にむけてすぐに動き出すことができた。
印象深かったのは、本震から10日後の2016年4月26日頃から、開館の問い合わせが急増したこと。「なぜいま問い合わせが?」「本当にみんな美術館にくるの?」と疑問があった。当時は、被災して間もないなかで美術館を開けていいのか逡巡した。しかし、桜井武館長は「まちなかがこういう状況だからこそ、早く美術館に光を灯しましょう」と言った。5月11日(本震から24日後)、無料スペースのみ開館した。初日は214人の方々が来られた。「ベビーカー押している方がこられてますよ」とスタッフに聞いた。「余震が怖くて、誰かがいる場所にいたい」と言っているという。そんなニーズがあるのだと思った。他の施設が閉まっており、ジブリなど人気の展覧会もあったため、この年は開館以来、一番の入場者数となった。地震という非日常のなかで、美術館というまた別の非日常の体験をするということが必要な方たちがいるのだということを実感した。

2016年7月16日−9月11日に当館のギャラリーⅢで開催した「丸尾三兄弟 〇O(マルオ)の食卓」展は、天草の若手陶芸家・丸尾三兄弟(金澤佑哉・宏紀・尚宜)が、参加者に1人1枚器を差し上げるかわりに、その人の食卓の写真を撮って送ってもらい、ギャラリー内に展示するというプロジェクト型の展覧会だった。ちょうどまだ、私も車中泊をしているときに、長男の佑哉さんから電話がかかってきた。天草は幸い被害が少なかったが、家庭の器がたくさん割れたのを見て、何かできないかと提案してくれた。

同展では、約500枚の器を配布し、約300枚の「食卓の写真」を、撮影者のコメントも含めて展示した。器にあったどんな料理をつくろうか、どんな写真を撮ろうか、と前向きでクリエイティブな気持ちを生み出すことができたのではないか。また、「ぐっと飲み込んでしまう小さな心の傷」や、「地震の経験を共有していない後ろめたさ」にも目を向ける展示になったのではないか。
豊田有希さんの「あめつちのことづて」展(2021年)では、関連企画として「令和2年7月豪雨REBORNプロジェクト」を実施した。同展の準備中に水害が起き、その水損ネガのレスキュー作業の様子を紹介するものである。
八代市坂本町のアマチュアカメラマン、故・東儀一郎さんらが町の暮らしや風景を写したネガフィルム約200本が水損し、それを知った豊田さんがSNSで協力を呼びかけると、県内の写真仲間や学芸員ら約20人が支援に駆け付け、つなぎ美術館と当館などでクリーニングや保存、デジタル化を進めた。熊本弁で「かせする(加勢する、手伝う)」と言うが、豊田さんを中心に自発的にレスキューの体制ができあがっていった。2020年7月にボランティアグループをつくり、助成金を取得、2021年に展示を開催し、ドネーションブック『REBORN』を作った。
現在、当館は4代目の館長として日比野克彦さんが就任されている。日比野さんが館長になって最初に行ったのが「災害時のアートインフラを考える」というオンラインイベントだった。ここでは、熊本の被災をめぐる知見を共有しようという企図があった。
シンポジウムでは、美術館ともゆかりが深い、地元の下通繁栄会のメンバーで、車椅子ユーザーの長江浩史さんに出演していただいた。熊本地震では、長江さんは小学校で避難所暮らしを余儀なくされ、そこに日比野さんが訪れた。日比野さんはそのとき、段ボールの間仕切りにマジックぺン一本で数字を描いて行ったという。長江さんは当時について、「あのとき、避難所がひとつのまちになった」と言った。そこから「郵便受けつくろう」とか「段ボールってデコってもいいんだ」とか、避難所の空気が変わったのだという。
今回の話を振り返ると、前半は「太郎君」を象徴とするように、作品やモノを通して語り、継承することとは何かと考え、後半は、災害で動き出している人がいるときに、「場としての美術館」にできることは何かという話だったように思う。
高森:印象に残った話がたくさんありました。なかでも、熊本市現代美術館の立ち上げ期をつくられた南嶌宏さんの話がとても印象的でした。南嶌さんと坂本さんとの信頼関係が、南嶌さんが館を離れた後も、亡くなられた後も続いていることがよくわかりました。彼の考えかたを坂本さんが継承されているんですよね。姿勢を学ぶとは何か、受け継ぐとはどういうことかを考えさせられました。
「展示する」という行為は、地域の方々とつながる方法として良いなと改めて感じました。「こういうものがあるんだよ」とか、「これまでこういうことしてきたんだけどどう思う?」と地域の方々に言われたときに、「素敵ですね」と返すような一対一のやりとりが考えられると思うのですが、このやりとりって意外とその先の広がりを考えるのが難しかったりするわけです。そのときに、「私が良いと思ったので、きっと○○さんも良いって言うと思うんです」と言って誰かに紹介するように、自分では収まりきらない良さを見つけてしまったから、もっとその価値を知ってもらいましょう、というかたちで社会にひらくのが「展示する」という行為だと思うんです。地域の人たちと信頼関係を結ぶために、話を聞くというのはとても大切で、もっとも基礎的なことではあるんだけれども、その先の回路として、地域の外の人たちとの回路をつくるために「見せる」というのが、応答の仕方として重要だなと実感しました。
でも、それは単に人やモノが有名になればいいとか、それらの社会的価値が高まればいいとか、そういう次元ではなくて、抱き人形の「太郎君」であれば、それを人形ではなく「太郎君」として扱うとはどういうことかということを、展示という行為を通して「太郎君」への触れかたをスタッフが学んでいくことで、表層的な意味を超えた尊厳を共有することが大切だったと思うんです。そういう人やモノの尊厳を理解することで、はじめてそれらを展示として社会にひらくことができるのだと思いました。また、地域にある「表現」未満のものを、「表現」として見せる、というのが、美術館の大きな役割なのだと感じました。
今日、坂本さんにこれはお伺いしておきたいと思ったことがあります。ナビゲーターの佐藤李青さんが所属するアーツカウンシル東京は「館」をもっていません。このシリーズの第1回で李青さんがお話してくださいましたが、アーツカウンシル東京は、モノではなくコトで見せるであるとか、アーティストの作品ではなくアーティストが地域の人々と結んでいる関係を見せるであるといった手法をとってきたといいます。坂本さんは熊本市現代美術館という「館」をもつところに所属されています。ただ、今日のお話の後半は、李青さんと同じように、モノではなくコトの話が多かったように感じました。前半は、モノを見せる、ないしは、モノから喚起されて生み出されたコトを見せる、というような、どちらであれモノが根っこにあったと思います。一方で後半は、モノの存在が見えにくいようにも感じました。語弊を恐れずに言うなら、そこに危うさのようなものも感じました。コトを起こし続けると、人との関係がどんどん増えてしまって、対応しきれない大変さもでてきます。そんななかで、あえて「館」があるからこそできること、「館」だから大変だけれどもここは大事にしているということがあれば教えていただきたいです。また、「館」のあるなしにかかわらず、共通して大事だと思っていることがあれば教えてもらいたいです。
坂本:うちの館に来ていただくとわかるのですが、当館は、フリーゾーンと企画展示室の2つに大きく分かれています。いわゆる常設展示室というのはなくて、「コト」にあたる部分はフリーゾーンで起こっているのですね。実は、私たちはいっとき、「アーツカウンシルとかアーツセンターみたいになりたい!」と言っていたんです(笑)。モノを守ることと、コトを起こすことの両立はかなりしんどいという感覚がありました。ただ、いま思うのは、両方あるからこその良さを考えたいです。正直なことを言うと、私たちが「館」を手放してしまったら、資金難に陥るでしょう。「館」の運営費というかたちで、物理的に大きなお金が動く。いまはそのなかから、コトの運営費を生み出しています。
そして、モノとコトのあいだに、「人」というのがあると思っています。人は財産ですよね。「現美の人っていいよね」って言われたいんですよ、八方美人かもしれないけれど(笑)。美術館は商店街の真ん中にあるのですが、あいつらがいないとまちが面白くないとか、そういうふうに言ってもらえるような活動をしていきたい。どうしても人数が足りないので、うちは総務のスタッフも事業を持っていたりして、学芸員と事務方という分けかたではない動きかたをしています。当館のプロジェクトにおいては、事務方も最前線で働いています。
高森:すごく現実的な話をさらに聞いてみたいのですが、学芸員さんと事務方さんとの関係がものすごく幸福な関係だったらいいのですが、両者には「学芸員として採用されている私」と、「事務として採用されている私」という思いがあったり、専門的教育を受けている者とそうでない者という違いがありますよね。市民みんながともにあれるような場をつくるということと、その場をつくることに関する専門性を持っているということを、どうやってバランスをとって動かしていらっしゃるのかなと思いました。専門知の扱いかたというんでしょうか。
坂本:私はもともと美術教育をやっていたということもあり、なんでもやるんですよね。教育って何にでもかかわっていますからね。自分も含めて当初は、専門を生かした展覧会をやることが仕事だと思っていた。でも、指定管理者制度が導入され、ここではそれだけじゃだめだ、市民とかかわって何かをなすということをしなきゃいけないよねと、自認するようになるんです。開館からいる学芸員は特に、それを自分たちで選択してきたというのがあります。うちは、学芸員と総務というより、皆「美術館員」という捉えかたなのかなと思います。美術館員全員が、市民とつながる最前線にいます。もちろん、人により強弱はあるけれど、そこは姿勢として大事にしているところで、もし「市民に近い美術館」というジャンルがあれば、割と上位なんじゃないかと自負しています。
歴代の4人の館長は、それぞれ個性が違う。南嶌さんは、「災間」という概念にも通じるような企画をキュレーターとして、展覧会というかたちで応えようしてきたといえます。その次の桜井館長は、見る人がいてこそのミュージアムだという考えかたです。学芸員の自己満足で終わっては駄目で、専門性を生かした仕事をするのは当然として、それをどれだけの人に見てもらうか、そのための工夫をすることが問われていました。桜井館長はアートを広く捉えていて、館長になられたときは60代でしたが、蜷川実花さんやジブリなどもどんどんやる。ブリティッシュ・カウンシル出身ということもあり、幅広い文化を大事にしていらしたように思います。熊本地震記録集として『地震のあとで』という冊子をつくったのですが、地震からまもなくして「美術館を美術館として開けよう」と最初に言ったのは桜井館長だったんです。私は、南嶌さんと桜井さんという2人の館長のもとで働かせてもらったことで、両方のいいところを取り入れていこう、学んでいこうという思いがあります。
高森:モノをもつ場所としての「館」と、人が集う場所としての「館」という両方をどうやって発展させていくか。そして、それを新たな館長とともにどう地域にひらいていくかということを常に考えていらっしゃるんだなと思いました。お話を聞いていて、館長の色合い、影響力がこんなに強いんだというのを初めて知りました。失礼ながら館長というのは「名誉職」なのかなと思っていました(笑)。全然そうじゃないというのは今回とてもよくわかりました。
坂本:歴代の館長は個性派揃いというか、クセが強い(笑)。ユニークですね。
佐藤:こういう話をするとき、どうしても「館」の内か外かとか、プロジェクト型かどうかとか比較してしまうんですけど、本当は役割の違いであって、連携できたらいいなと思うんですよね。坂本さんの話を伺うと、美術館は“いわゆる”美術館というもの以上のものを求められるようになってきたと実感します。市民側からみたら、それが美術館的かどうか、ということより、美術館とのかかわりをどうつくっていけるかが大事なんですよね。アーツカウンシルも美術館も、それぞれに特性があり、役割があるわけですが、「使う」側から見ればアートにアクセスする選択肢に過ぎないともいえる。たしかにアーツカウンシルは「館」をもたないから、地域の人たちとのかかわりづくりのような実践はやりやすいと思います。ただ一方で、常にその実践は見えにくくもあります。さっきの話だと、南嶌さんの姿勢と実践は作品や展示の力によって、遠くに届くわけです。一方でかかわりづくりは、近くの人たちに濃密に届くけれども、遠くには届きづらい。アーツカウンシルの活動がどれくらい遠くの人に届いているのかというのは、いつも問われています。
たとえば展示でかかわりの成果や過程をひらこうとなったときに、自分たちで場所をつくるのか、美術館と連携するかというのでは、届きかたは違うと思うんです。多くは、前者、つまり自分たちで場所をつくろうと、たとえば遊休スペースを使った展示をしたりするわけですが、すでにある美術館で連携してやってみる、というのもあるのではないかと思いました。
“「館」をもたないアーツカウンシル”という共通認識ができてしまうと、いざ「館」との連携になったときに、それならそもそも「館」をもっているところがやればいい話じゃない? となることもある。それが「館」との組みづらさになっているところがあるかもしれないです。もちろん、ただ連携できればいいというわけでもないし、美術館も展示だけが機能ではない。ただ、「館」のあるなしにかかわらず、それがどう機能するのかを見ることが大事なんだと改めて気づかされました。うーん、これまでのいろんなことがフラッシュバックしています(笑)。
高森:私たちは議論するときに、とかく対比しがちですよね。「館」のあるなしという二項対立で議論をたてて、「館」がある側を分析しようとするときは、「館」のなかの実践しか見ない傾向があります。たとえば、アウトリーチと展示を無自覚に対比させたりもするわけです。でも、「館」をもたない側のアーツカウンシル東京だと、「アーツ千代田3331」という建物のなかでやっている実践はなんなんだ、という話にもなります。よくよく考えれば、展示という「館」のなかの実践と捉えているものも、展示物を別の場所からもってくるとか、展示が終わったらそれらを返しに行くとか、そういう外とのつながりがあってはじめて成立するわけですよね。いわばそれは、展示という行為に紐づけられたアウトリーチでもある。議論するときに勝手に分けて捉えてしまうことで、結果として実践が切り縮められて、中身ではなくて型の話になってしまうところがあると思うんです。なにかを理解しようとする、言葉にしようとすると、むやみに対立軸を持ち出してしまうというのをどうやって回避したらいいのかなぁと思いますね。

宮本:お話をきいて、まずは美術館に行きたくなりましたね。熊本地震のときに、「美術館開いてないのか」という声が出たということの意味を一番考えさせられました。坂本さんは、「みんな非日常を求めていたのかもしれない。でも地震も非日常なんだけど」っておっしゃられていましたが。非日常としての災害をどう生き抜くかというときに、非日常としてのアートというのがものすごく大事だったり、場合によっては欠かせないのかなと思いました。そういうときのアートってどういうものだろうかと考えたときに思い出したのが、東日本大震災のときに福島の避難所で見た光景です。僕が手伝いに入ったときには、自分で段ボールを持って行って、それぞれに工夫して間仕切りをしていたんです。表札をつくったり、郵便受けをつくったり、間仕切りの内側に家族の写真を貼ったり。段ボールなので高さはそこまでないので、プライバシーはあまり確保できません。ただ、その避難所は活気があって、ひとつの街のようだったんです。そこに、ある建築家の方が考えられた、紙と段ボールだけで仕切りをつくるユニットがやってきた。それは非常に合理的で、軽いから余震で倒れても大丈夫だし、プライバシーもしっかり確保できるし、おそらく費用もそこまでかからない。そういう意味では、災禍を生き抜くために優れたものだと思います。それが導入されるにあたり、これまでの段ボールを撤去して、ぜんぶそのユニットにしたわけです。そうしたら、途端に会話がなくなって、みんな出てこなくなった。そこで考えさせられたのは、避難された人たちが自分の居場所のために段ボールに工夫を施す、「デコる」っていうのが、すごく大事なことだったのでは、ということでした。長江浩史さんと日比野克彦さんの活動でも共通して出てきたことだと思います。
自分の子供を埋葬した浜辺から貝殻を拾い集めていくであるとか、「〇о(マルオ)の食卓」で器をもらって、それに盛り付けた自分の食事の写真を撮るであるとか、災間を生き抜くために必要なアートには共通する性格があるんじゃないかと思うんです。鶴見俊輔は著書『限界芸術論』で、純粋芸術と大衆芸術の手前にあるもの、芸術と生活の境界にあるものを「限界芸術」と名づけているわけですが、そういう「あいだ」にある限界芸術が豊かになることで、純粋芸術や大衆芸術も豊かになるんだと書いていますよね。災間を生き抜くというときに、エッシャーの絵も見たいし、ジブリ展もみたいし、でも同時に、木下今朝義さんの《遠足》や、石牟礼道子さんの手足を接写した作品《不知火(しらぬい)の指》であるとか、ハンセン病療養所にいらした上原ヨシ子さんが拾い集めたたくさんの貝殻が飾られていたりと、限界芸術がどっしりとあるというのが、李青さんのいう「かかわりをつくるアート」の役割なのかなと思いました。
限界芸術は生活との境界にあるがゆえに、モノとコトがごちゃまぜですよね。プロとアマチュアもごちゃまぜです。僕自身、アール・ブリュットが生理的に大好きなのですが、それがなぜ好きなのか見通せた感じがありました。そういうアートの存在が、災間を生きるときに大事なんだろうなと思いました。熊本市現代美術館は、鶴見俊輔のいうところの3つの芸術が揃っているなと思います。
佐藤:宮本さんのコメントと関連して、参加者の小田嶋さんのご質問で、「いわゆる美術品ではないモノを展示する際、どういった工夫をしているのか詳しく知りたいとあります。そうした展示で、鑑賞者がモノの背景について想像を巡らせる後押しになるような工夫はありますか」とのことですが、坂本さんいかがでしょう。
坂本:それがキュレーションという行為だと思います。南嶌さんのキュレーションってものすごく個性的で、好みが分かれる(笑)。「痺れる!」っていう人もいれば、「なんじゃこりゃ」と思う人もいると思うんです。私はそこまでの個性はないですが、キュレーションした展覧会「ライフ」では、アール・ブリュットとか、ハンセン病とかなるべく先入観なしに、まずは「きれいな貝殻だな」と見てもらいたいと思いました。福祉やあるいは現代美術に興味がある人だけが来るのではなく、たとえて言うなら、書店に行って、たまたま隣に置いてあった自分の関心の外にあったものを手にとるような、そういう場づくりができればいいなと思ったんです。キュレーションでは、観覧者が展覧会の全体を見ていくなかで、どういう心の動きをしていくかを考えていきました。そこで、どの程度の情報量が適切かを考えて、簡潔なキャプションをつけていきました。
監視員さんが、「静かに涙を流されている方がいました」とか、「年配の方が、僕は何も知らなかった、とぽつりと言われていました」とか報告してくださる。私は教育出身だからなのか、美術業界の外にいる人により知ってもらいたいという想いが強くあります。
佐藤:監視員さんたちのかかわりはどのようなものなのですか?
坂本:監視員さんたちはとても勉強熱心です。開館以来いらっしゃる方もいるので、目が肥えています。お客さんの反応がいいと、嬉々として自分のことのように伝えてくれます。
佐藤:事務局の小川さんからの質問ですが、「地域の人々の記憶と、公式記録が対立した場面はありますか。政治的に複雑な経緯をたどった出来事も多くあるように思います」とあります。坂本さんそのあたりいかがでしょうか?
坂本:人権に関わる博物館などでは、様々な視点があるため、常設展示などでも、日々慎重にアップデートされていると思います。当館の展覧会に関していえば、たとえば水俣のことを扱うと「なぜいまこのテーマをやるのか」とご意見をいただくこともあります。当事者の方々との関係が近い場合は特に、事前の調整や説明は欠かせないでしょう。
これは、元スタッフの蔵座さんから聞いて印象に残っているのですが、若い新聞記者が作品の取材にこられて、「絵の取材でほっとしました」と言われたそうなんです。記者だから当然、勉強しなくてはいけないけれど、「そんなことも知らないのか」とか「勉強不足だ」といわれるのでないかと、いつも少し緊張しながら現場に行くそうなのですね。しかし、絵であれば構えずにリラックスして向き合える。それを聞いて、美術って「あいだに入る」ことができるのだと感じました。白か黒かだけではない、グレーの幅が広いのが美術の良いところだと思いました。
佐藤:展示の機能というのは、それすべてで何かを理解するということではなくて、そこからスタートして考えられるところが重要なんだと思います。展覧会でメッセージを伝えるというのは確かにあるんだけれども、その若い新聞記者の方が言うように、別のやりかたでは触れづらかった出来事にたいして、このかたちであれば触れられることがあるんだと思います。それが展示の持つ可能性ですね。あ、小川さんから手が上がってますね。小川さんいかがですか?
小川(事務局):さきほどから坂本さんがキュレーションという行為の重要性についてお話いただいていたと思います。これは現代美術の特性とも関係すると思うのですが、「角を矯(た)める」っていうんでしょうか、何かをうまく収めるというところはあると思うんです。例えば、熊本地震に関する場合だと、九州電力の原発どうするんだということに触れる可能性があると思うんです。現美にかかわっておられる坂口恭平さんはそういうことも触れておられると思うんですけれども、この表現をそのまま出せない、いや出すべきなのかどうなのか、ということがあると思うんです。それをキュレーションを通して出す、ないしは切り取るということについて、制約があると感じていらっしゃるのか、そういう厳しい話が起こっているのかをお聞きしたいです。
坂本:原発を含め、地震災害に関してはそこまでないのですが、人権や、性的表現や、政治性のあるトピックに関しては、水面下で色々な調整があります。法律に反していなければ、基本的には出せるのですが、様々な立場によって受け止め方が違うことを念頭において、企画を進めています。
佐藤:モノに言葉を付与しなくとも、モノそのものが語ってしまう力がありますよね。事前の打ち合わせで、宮本さんがメモリアル施設のモノ展示についてお話されていたことを思い出したのですが、いかがでしょうか?
宮本:先々週に宮城に行ってきたんです。東日本大震災の伝承施設というのがこの2、3年オープンしています。今年になって宮城県のメモリアル施設として「みやぎ東日本大震災津波伝承館」が石巻にできたんです。そこに行ってみたんですが、ここだけでなく、災害関係の施設はみな、モノの展示が少ないんですよね。災害関係の展示と、いわゆるミュージアムの展示を比べると、比べものにならないくらい充実していないと感じます。この最大の理由は、李青さんや坂本さんのような、キュレーション、ディレクションする人がいないからだと思うんです。学芸員がいなんです。行政がコンサルタントとつくって、つくったらそれで終わりなんです。そこからは、ソフト面というかたちで語り部さんたちに丸投げされるというのが現状なんです。展示替えもないし、大きなお金がかけられるわりに、中身が残念であることが多いように思います。「津波伝承館」ではメッセージとして「とにかく逃げてくれ」というのがある。これはもちろん大事だけれど、逃げたあとに何があったのかという展示はほとんどなくて、そこは語り部に聞いてくれ、という設計になっています。それを語り部さんに聞くことはもちろん大事だけれど、東北の場合は伝承施設にiPadがたくさん置いてあって、それを触るといろんな人の語りが見れるというかたちが多いんです。それってすごく良くないな、と思うんです。そこに行かなくても見れるじゃないですか。これってとても脆弱で、このままだとあっという間に語れなくなるときがくるんじゃないかという印象があります。
今回、水俣などの災厄に関わるお話を聞いて改めて思ったのは、社会的に辛い出来事というのは、考えかたの違いとか、プロセスのなかで起きる分断があり、当事者のなかで不幸なひび割れが起きると思うんです。そのときに、これは水俣に関して特に思うんですが、分断を隠したり、無かったことにせずに、分断は分断として認めながら、「それは違うんじゃないか」とお互いに言い合うようにしてやってきたということが大切だと思うんです。それが、運動なり、語り継ぎなりが続いてきたひとつの理由なんじゃないか。水俣という名称を出してくれるなという人、まだまだ裁判なりで主張していくことが必要だという人、それらとは別のかたちでかかわろうとする人、そういう人たちが、「難しいね」、「折り合いをつけようね」ではなくて、言い合ってきたというのがあるのではないかと思います。
佐藤:気仙沼のリアス・アーク美術館の山内(宏泰)さんが、災害を伝承する施設に、観光という目的がくっついたときに、伝承の機能が弱くなるということを展示デザインの視点で指摘されていたことを思い出しました(山内宏泰「博物館展示における震災資料展示の課題と可能性」『国立歴史民俗博物館研究報告 第214集』、2019年)。
現美で坂本さんがつくられた『地震のあとで』という記録集では、写真家の石川直樹さんが撮影された熊本地震後の写真がありますが、これは記録集をつくるという目的があって撮影されたものですか?
坂本:この記録集には3人の写真家が関わっています。石川直樹さんは、被災後の熊本を取材してもらったことがあり、それらの写真は展覧会のカタログにしか載らなかったので、この記録集にも再録しようということになりました。川内倫子さんには、地震前に別の企画で熊本の風景を撮ってもらっていて、それを再録させてもらいました。また、宮井正樹さんは、被害の大きかった西原村在住で、地元の様子を被災者の視点から撮ったものを掲載させていただきました。これまで行ってきた展覧会があったからこそ記録集ができたというのもあるし、展覧会を見ていない人たちにもこれらの写真を見ていただきたいという思いもあり、載せようということになりました。
佐藤:災害があったときに、モノそのものを残すということもあるんだけれど、アーティストのかかわりから作品として残すということもありますね。この写真は美術館に収蔵されていますか。
坂本:川内倫子さんの写真は収蔵されています。
佐藤:今日のお話では、美術館という場所があるから作業ができるとか、モノを扱えるとか、「館」があるからこそできたことがあったと思うんですが、これがもっとあればよかったなと思うことはありますか。
坂本:いっぱいありますけどねー!(笑)。マンパワーがもっとあれば良いなぁとつねづね思いますね。実感したのは、災禍のときに美術館がずっと閉まったままでは駄目なんですよ。私たちが何か次に進もうっていう気持ちになるために、きっと役に立つことができる。熊本地震の被災直後に美術館を開けたとき、塗り絵がすごく人気だったんです。塗り絵って、単純な作業で区切りがつくものじゃないですか。手を動かした分の成果が見えるというか。地震が起こると、はっきりとした区切りがないことが多いです。被災した人たちは、いつまで待たなきゃいけないのかとか、いつ元通りになるのとか、そういう状態に置かれるわけです。そんなときに、塗り絵って、時間をかければ必ず完成できる表現なんですよね。だからなのか、みなさん熱心に取り組んでいらしたんです。災害が起こる前は、そんな力を秘めているものだとは思っていなかったんですが、そういう手を動かす、小さな目標をつくっていく作業は大事なんだなと思いましたね。
佐藤:日比野克彦さんは、災害後に何かに没頭できることが必要だとおっしゃるんですよね。東日本大震災の後にも、すぐに動き出していましたが、さまざまなアクションを通してかかわった人たちが「つくる時間」をもつことを大切にしていた。その時間では、どんな色を塗ろうか、何を描こうかと「少し先」をイメージする。それは被災という現実ではない「現実」を生み出すことにも大事だったのだと思います。さらに、被災すると自分の選択肢を人から提示されるばかりになるから、自分で何かを選んだり、自分の手で何かをつくっていくというのが大事になるとも話されてました。その話を思い起こしましたね。
・・・
まだまだ話が尽きないところで、あっという間の3時間となりました。
このレクチャーのあと、坂本さんのおっしゃっていた「全員美術館員」がよくわかる記事を見つけました。Web美術手帖の記事「学芸員は名前が出せない?美術館の(奇妙な)現状を探る」によると、日本の美術館は、展覧会を担当した学芸員の名前を出さない慣習があり、それを問題視する意見も出ているといいます。記事の最後には、そのような慣習の変化の兆しのひとつとして「熊本市現代美術館では、館長以下、総務スタッフまで氏名を公開」していることが挙げられていました。このことも、熊本市現代美術館の「全員美術館員」という姿勢が現れていると感じました。
次回はいよいよ最終回。ナビゲーターの3人が、参加者のみなさんのレポートを共有しつつ「災間の社会を生きる術(すべ/アート)」について議論します。それでは次回もよろしくお願いいたします。
執筆:高森順子
日時:2021年10月31日(土)14:00~17:00
場所:オンライン(Zoom)での実施

執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28
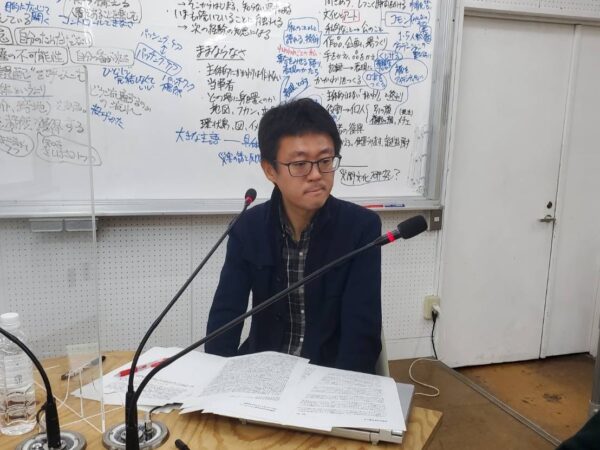
執筆者 : 宮本匠
2022.01.28

執筆者 : 高森順子
2022.01.28

執筆者 : 高森順子
2022.01.19

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 高森順子
2021.09.07

執筆者 : 高森順子
2021.08.18