
2022.01.28
“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)
執筆者 : 佐藤李青

豪雨にて流失した熊本県八代市坂本町の坂本橋。水損の激しかった35mmカラーフィルムのデジタルデータ『令和2年7月豪雨REBORNプロジェクト』(撮影:東儀一郎)
地球規模の気候危機によって、近年大小さまざまな災害が頻発しています。さらに、東日本大震災やコロナ禍などの「災い」は、次々と社会が内包していた課題を露わにしています。
現在の社会は、さまざまな災いと災いの間、つまり「災間」にあると捉えることはできないでしょうか。わたしたち誰もがいつやってくるかわからない災禍の「前」にいて、ときには災禍の「なか」で、当事者となる可能性をもっています。何らかのかたちで支援者となりうることもあるでしょう。文化やアートの視点を携えて災禍の現場に立つには、どのような態度や技術、方法がありうるのか、「災間の社会を生きる術」について考えてみたいと思います。
今回は、災害復興の現場に多様なかかわり方をしてきた3名のナビゲーターとゲストが「災間」を軸にトークを繰り広げます。ナビゲーターは、新潟県中越地震から災害復興の研究に取り組む宮本匠と、阪神大震災を記録しつづける会の高森順子、Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業/ASTT)を行ってきた佐藤李青です。
ゲストには、吉椿雅道さん (CODE海外災害援助市民センター事務局長)、瀬尾夏美さん(アーティスト)、山住勝利さん(NPO法人ふたば/ふたば学舎 震災学習ラボ室長)、坂本顕子さん(熊本市現代美術館 学芸員)をお迎えします。
ゲスト:吉椿雅道 (CODE海外災害援助市民センター事務局長)
ゲスト:瀬尾夏美 (アーティスト)
ゲスト:山住勝利 (NPO法人ふたば/ふたば学舎 震災学習ラボ室長)
ゲスト:坂本顕子 (熊本市現代美術館 学芸員)
6,000円
「ポスト・コロナ」「コロナ後の世界」、書店をのぞけばこんなタイトルの本が並んでいます。この1年半、僕もこれらの言葉を耳にし、それなりの関心をもって接してきました。「ポスト・コロナ」という言葉にこんなにも魅せられたのは、コロナ禍の苦難の先にある希望を語りたいという意味以上の理由がそこにはあったような気がします。
それは、僕たちがうすうす気づきながらも、見なかったことにして、看過しようとしていること、つまり、この危機に実は終わりがないのだということを「ポスト・コロナ」という言説が覆い隠してくれるからだったのではないでしょうか。「いつか終わりはあるんだよ」と。だからこそ、僕たちはそれに飛びつき、救いを見出そうとしたのではないでしょうか。
けれども、最も重要なことは、もはや僕たちの社会に「ポスト」は存在しないということに気づくことではないでしょうか。僕たちの社会には、もう何かの「後」っていうのはなくて、僕たちはひたすら「終わりの中」を生き続けなければならないのではないかということです。
「終わりの中」を生きることは大変苦しいことでしょう。けれど、このような人間の存在を根底から揺るがすような時にこそ、人間は文化でもって、芸術でもって、生き抜いたり、やりすごしたりしてきたように思います。筑豊の炭鉱の中で、死と隣り合わせの中で交わされていたのが笑い話だったという上野英信の『地の底の笑い話』で生き生きと語られているように。
「終わり」の中にあるからこそ見える輝きがあるように思います。「終わり」のなかにあるからこそ獲得できる解放もあるように思います。でも、そのためには、「すべ」が必要です。その「すべ」は、危機的状況におかれた被災地や、社会を斜めから見ることを通して「もうひとつの社会」を見出してきたアートにヒントがあると確信します。
危機をのりこえるには、一部の専門家やリーダーによる「力業」ではなく、ひとりひとりの多様な感受性に基づく「合わせ技」が鍵であるし、サステナブルだと思います。アート×災害にどんな可能性を見出せるか。そんなチャレンジを皆さんと一緒にできたらいいなと思っています。
どこかで大きな災害が起きたと、私たちはメディアを介して頻繁に見聞きします。その都度、不安や緊張で身を固くしたり、心を痛めたりします。そして、しばらくするとその災害のことなどすっかり忘れ、次の災害に目を奪われます。私たちの多くにとって、そうしたことはありきたりで当たり前のことかもしれません。
しかし、実際に災害によって大きな喪失を経験したことのある人々は、失った人やものを想像するたびに、被災という出来事と向き合い続けなければならなくなります。新しい災害に関心を移し続けていく社会のなかで、彼らは「過去の災害」に取り残されているように感じているかもしれません。
そこに横たわる彼らの「ままならなさ」や「わかりあえなさ」を孤立させたままにするのではなく、人々が互いに分け持つことができたなら、災間の社会はもっと生きやすいものになるのではないか。その「分け持つ」手立てとして、アートにその可能性があるのではないか。私はそのように思っています。
新型コロナウイルスが感染拡大している今日の社会はまさに災禍の只中にあって、ある意味では世界中の人々が被災者となっており、それぞれに切迫した「ままならなさ」や「わかりあえなさ」を抱えているともいえるでしょう。だからこそ、誰かの生きづらさを分け持つアートについて考えることは、この社会をともによりよく生きることを考えることにつながるのではないでしょうか。参加者の方々の声が、深い対話に導いてくれると信じています。ご参加、お待ちしています。
2011年の東日本大震災の後から、ずっと抱えている感情に「怒り」があります。それは震災後に身の回りで起こったことが「すでに知っていたこと」だったのではないかという気持ちが拭いされないからだと思います。怒りの矛先は震災が起こる「以前」の自分に向いています。震災は平時にあった課題を露呈させたにすぎない。わかっていただろう、と。
平時から非常時のことを考えたい(いまはコロナ禍という渦中ですが)。非常時について議論することから、平時のありようを変えていきたい。そう思うのは、わたしがArt Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)を担当していたこともかかわっています。震災後に、いち早く動き出した人たちの活動は、震災以前から地続きの理念や行動に支えられていました。震災は、平時での活動の真価を明らかにしたのだと思います。
誰もが災害の「前」にあり、「後」になる可能性をもつ。いま、わたしたちは、そうした災害の「間」に生きているのではないでしょうか。社会学者の仁平典宏さんは「厄災が何度でも回帰しうることを前提」とした「災間の思考」において、一度の「ショック」で社会を変えようとするのではなく、「持続可能でしなやかな社会を構想」し、「社会に様々な『溜め』や『隙間』や<無駄>をつくり、リスクを分散・吸収させることが重要になる」と指摘しています(*)。この「災間」という言葉を手がかりに、平時と非常時を行き来するような「術」について議論をしたいと思っています。
今回、こころ強いナビゲーターのおふたりと、経験豊富なゲストのみなさんと、たっぷり時間をかけて議論を重ねます。災害復興への「かかわり」がテーマになりますが、参加にあたって経験の有無は問いません。異なる技術や経験をもった人たちが出会い、それぞれに思考や手法の選択肢を増やしていく。それが「災間の社会を生きる術」を探るための近道なのだと思います。みなさんのご参加をお待ちしております。
* 仁平典宏「<災間>の思考ーー繰り返す3.11の日付のために」『「辺境」からはじまるー東京/東北論』(赤坂憲雄、小熊英二編著)明石書店、2012年

2022.01.28
執筆者 : 佐藤李青
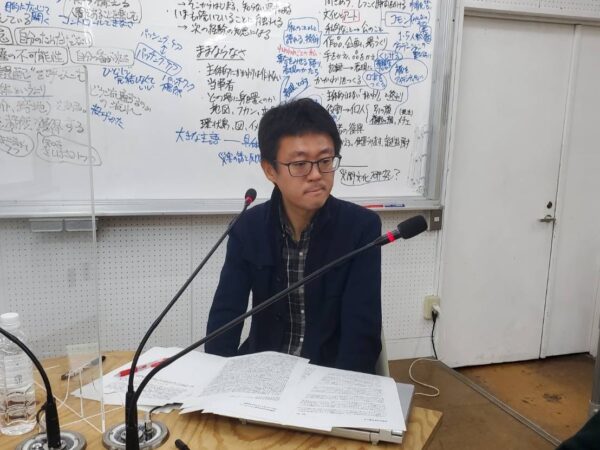
2022.01.28
執筆者 : 宮本匠

2022.01.28
執筆者 : 高森順子

2022.01.19
執筆者 : 高森順子

2021.12.28
執筆者 : 高森順子

2021.12.28
執筆者 : 氏家里菜

2021.12.28
執筆者 : 氏家里菜

2021.09.07
執筆者 : 高森順子

2021.08.18
執筆者 : 高森順子