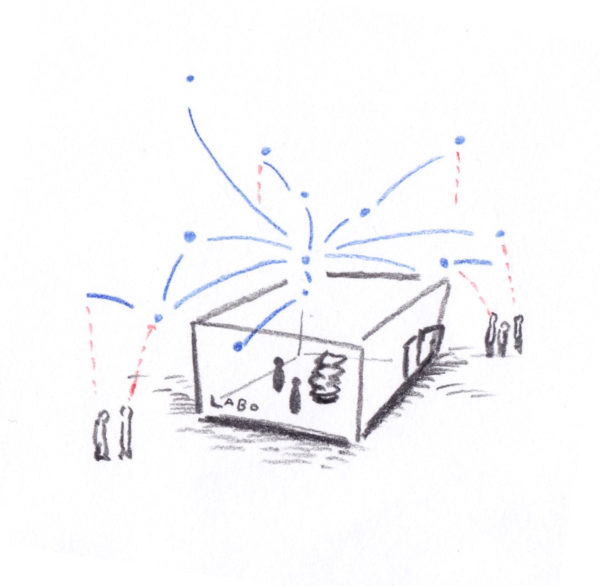アートプロジェクトの現場から外国ルーツの若者の支援について考える

- オンライン

アートプロジェクトの現場では、誰かと何かをはじめようとするとき、考えや視点の違いを理解しながら、互いのイメージを擦り合わせ、つくり方を議論します。そこで起きるコミュニケーションは、「言葉」に限ったものではありません。むしろ、表情やしぐさ、声色、動き、間など身体を用いた非言語の領域が、日々のコミュニケーションに大きな影響を与え、支えています。
新型コロナウイルスの感染拡大を経たいま、互いに目を見つめ、相手の息づかいを感じ、何気ないしぐさを眺めながら話をする、そんな当たり前のことが気軽にできなくなりました。そうした状況だからこそ、あらためて「コミュニケーション」や「身体性」について考えられることがあるのではないでしょうか。
今回は、和田夏実さん(インタープリター)、南雲麻衣さん(ダンサー)、加藤甫さん(写真家)の3名のナビゲーターとともに、身体性の異なる人々の世界に触れ、「言葉だけではない」コミュニケーションのあり方について考えていきます。ゲストは、米内山陽子さん(劇作家/演出家/舞台手話通訳家)、田中結夏さん(舞台人/舞台手話通訳者/手話通訳者)、関川航平さん(美術作家)です。
ゲスト:米内山陽子(劇作家/演出家/舞台手話通訳家)
田中結夏(舞台人/舞台手話通訳者/手話通訳者)
ゲスト:関川航平(美術作家)
ROOM302(東京都千代田区外神田6-11-14-302[3331 Arts Chiyoda 3F])ほか
一般30,000円/学生20,000円
「他者と出会うこと。」まだ先行きの見えない、大きな変化の中で、私たちは互いにどんな風に出会い、どうしたらその人らしさを知ることができるのか、そんなとっても身近で、とっても壮大な実験に、ようこそ。
私は、コーダと呼ばれる両親がろうの聴こえるこどもとして生まれ、手話を第一言語にして育ちました。手話という手で空間に描くように構成される言語と、音や文字で線状に紡がれる日本語という音声言語。それぞれの間で、インタープレート(通訳)していく中で、こどもながら、全然伝わっていないのではないか?! という場面に数多く遭遇しました。それは言語自体の翻訳の難しさももちろんですが、温度や空気、気配といったその人らしさを構成するものを、誰かが介在して伝えることの難しさでもありました。
マスクや画面、透明のビニルシート。私たちを守り、隔てるもので、受け取りにくくなってしまったものが想像以上にたくさんあることに、日々驚いています。けれども同時に、それは今まで知らぬ間に受け取っていた、その人らしさがたくさんあったことに、気づいた機会でもありました。
南雲さんと直接会って手話で会話したり、実験したりしていた時に、ぽこっと生まれていた会話の空間(たぶんまんまるの空気の球みたいな形をしていたと思う)が、画面を介すると時間のズレや目線に気づけず、一緒にいる感覚がしないこと(四角くてガチッとした箱に入って、パラレルワールドの先の彼女に話しかけている感じがする)。会議で話し始めるタイミングをどうにもつかめず、「あっ、どうぞ。」という機会が増えたこと。そういえば、小さな頃、どうにも電話を信じることができなかった5歳の私は、何に恐れていて、何があったら信じることができたんだろう、と考えたりします。
ここは毎日の中のコミュニケーションの中に生まれるほんの少しの違和感について、みんなで話し合い考えることを目指した、プロジェクトスタディです。南雲さんの手話もダンスをも現すからだ、写真を撮ることと視覚的な会話について考えている加藤さん。3人と、スタディチーム、そしてこれから出会う、皆さんと。
ざらざらとした不思議に出会い、これは「リズム」の話かしら。「意識」の方向の話かしら。と考えたり、ともになんだろう、と悩み、ともに絵を描いたり、写真を撮ってみたらどうだろう! とつくったりする、そんな実験にご一緒できたら嬉しいです。
このコロナの影響で、私たちの身の回りのコミュニケーションが少し変化していきました。
第一にマスクをして会話することの困難さ。私の場合ですが、口元が見えなくても人工内耳を使用すれば大体聞き取れます。けれど、言葉を理解する前に、この人はどんな気持ちでこのことを言ったのかをその人の声色からは判断することができないことに気づきました。マスクの奥にある表情が隠れてみえないことにもどかしい気持ちでいます。
ちょっと難しい話をし始めるときに変な顔をする人や、言葉に迷っているときに口をパクパクさせる人など、言葉だけではないところ、その人の顔の表情からも、人間は無意識に情報を読み取っているのではないでしょうか。
これまで苦もなくコミュニケーションできていた人も、マスクやフェイスガードによって声が届かないことを実感することが増えたのではないでしょうか。サービス業では、接客中に身振りなどで伝えようとするパワーが以前より増してきたと思います。私は、マスクからのぞく笑顔に、目尻の皺に注目する癖が身についてしまいました(笑)。
第二に、テクノロジーの進歩により、手話という視覚言語にテクノロジーが追いついてきた感覚があります。巷で流行っているオンライン飲み会や遠隔講演会などは、コロナ禍以降から盛り上がりを見せています。また、手話がわからない人もわかるように字幕を付けるなど、当事者側から発信するアクセシビリティも見られるようになりました。リモートの手話講座はいつも満員だそうです。これまでなかったことでした。
手話とテクノロジーの相性の良さと便益性を発見できたのと同時に、手話という言語は身体をも伴う言語であることを、私のなかで改めて実感しています。オンライン上では、相手の身体がそこにないせいなのか、立体ではない二面の画面であるせいなのか、相手をマークして投げる会話のキャッチボールが、いつもよりうまくキャッチできず戸惑う感覚があります。それはまるで、全力疾走しながら、会話を受け止めている感覚になり、あとから疲労感と物足りなさを感じます。
コミュニケーションの以前に、一人一人の身体や表情がそこに「在る」というリアリティが、ある一定の期間に急速に薄れました。今はその状況を互いにシェアリングできたことで、これまで見えてこなかったものをなんとなく掴みかけているところです。それが一体なんなのか、一人でもやもやしているのではなく、スタディという名前を借りて参加者とともに探してみたい。みんなが同じ状況に立たされた「共在感覚」と一人ひとりの異なる身体を、しぼりだしながらも言葉にして記録し、後世に残すことに大変意味があるのではないかと思います。
インタープリターである和田夏実さんとは、何年も前から手話の先にある視覚身体言語の面白さや、感覚が異なる者の環世界など話し合って、ワークショッププログラムなどを作ってきました。私の手話を翻訳し、音声言語に伝える彼女のパーソナリティを信頼しています。バックグラウンドが違う私たちが二人三脚でやってきたこともこのスタディで発揮できたらと思います。
写真を撮っている時、僕には写したい「所作のポイント」みたいなものがあります。それはわかりやすい決定的瞬間的なものではなく、意識と無意識の中間くらいの、撮る側と撮られる側どちらかの主張が強すぎない、ちょうどいい塩梅の自我の入り方。そういうものを撮ることが僕は「写真」らしいと考えています。撮影者として、所作やたたずまい、人がただ居ることなどから感じる「なにか」。普段ファインダー越しに考えていることの正体っていったいなんなんだろう? ということをテーマに扱っていきたいと思っています。それは、「共存する身体」であったり、「他者」であったり、「コミュニケーション」を考えることに通じるはずです。
いま僕は、6歳になるダウン症の息子と暮らしています。
彼は発育が遅く、まだ言葉を話すことはできません。話せないけれどもちろん意思はあって、その意思の発し方は独特です。ジェスチャーや音、文脈などを使って伝えようとします。彼の発露を「どう受け」「どう返す」のか、僕自身も想像力を駆使しながら試行錯誤する毎日です。
彼らは「療育」と呼ばれる、発育の遅れを補うための訓練を受けています。社会で生きていくために、他人とコミュニケーションが取れるように。そこに立ち会い、息子の成長を嬉しく見ている反面、なぜ彼らはそのままでは生きていけないのだろうと思うことがあります。
「成長」ってなんだ? 社会に適応していくことばかりが「成長」なのだろうか?
コミュニケーションにおいて、発する側だけでなく受ける側のありようも、同じように大切な気がします。だから、このスタディでは身体と視覚を主な手がかりに、コミュニケーションの受け方についても考えていきたいと思っています。
思い立ってあの人に会いに行く、隣に座って、声色や表情、その人がまとう空気に触れながら話をきく。そういう当たり前のことが、こんなにも愛しいと感じていたんだと気づく日々です。2020年春から、わたしたちが目にする暮らしの風景は一変しました。マスク、ビニールシート、パーテーション、消毒液の香り、透明の膜で覆われた暮らしの風景は、人と人、人と社会の距離を物理的にも、心理的にも、どんどんと遠ざけていくようで心許ない気持ちになります。こんなにも遠ざかった者同士が、ちゃんともう一度出会うことができるのだろうか。そもそも、こうなるずっと前から、わたしたちは他者とちゃんと出会ってきていたのだろうか。分断の肌触りを日々体感しながら、そんな問いをわたしは抱えてぐらぐらと揺れています。
大げさかもしれないけれど、人は、生きていく上で、自分とは異なる他者の存在を知ること、また、そこにその人が「いる」んだと実感することが、自分自身の存在を確かめる拠り所となっているのではないかと思うようになりました。そして、その人とコミュニケーションを重ね、互いの考えや感覚の違いにハッとして、ときには喜んだり、悲しんだりしながら、自分と他者との距離感を知っていくこと。この人と人との「間」の部分に触れようと手を伸ばすふるまいは、他者と出会うときのヒントになるんじゃないか、そんなことをぐるぐると考えています。
今回、インタープリター(通訳者/解釈者)の和田夏実さん、ダンサーの南雲麻衣さん、写真家の加藤甫さんという3名のナビゲーターと共に、「身体」を軸に「コミュニケーション」にかかわる実験・実践を重ねていくスタディを立ち上げました。ナビゲーターの3名、運営チーム、そして参加者のみなさんと、それぞれの異なる身体性や眼差しを交換したり、ときにはぶつけ合ったりしながら、わたしたち一人ひとりの「間」にある「何か」への触れ方、ふるまい、他者を想像する新たな方法やとっかかりのようなものを一緒に探ってみたいと思っています。