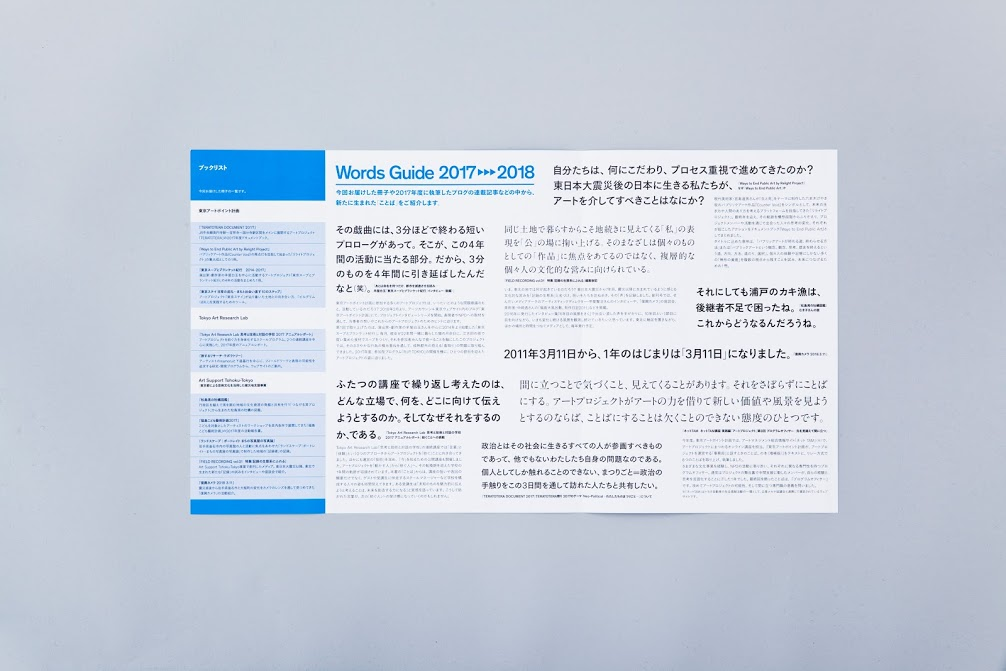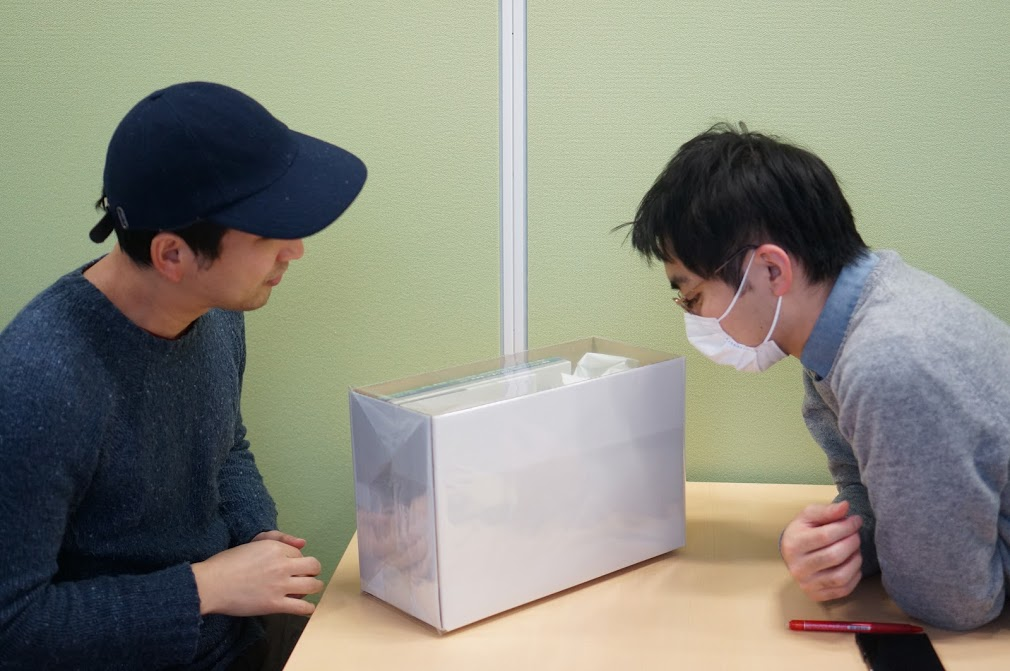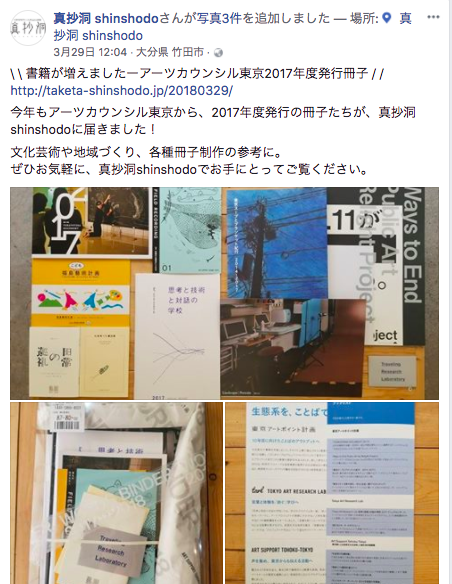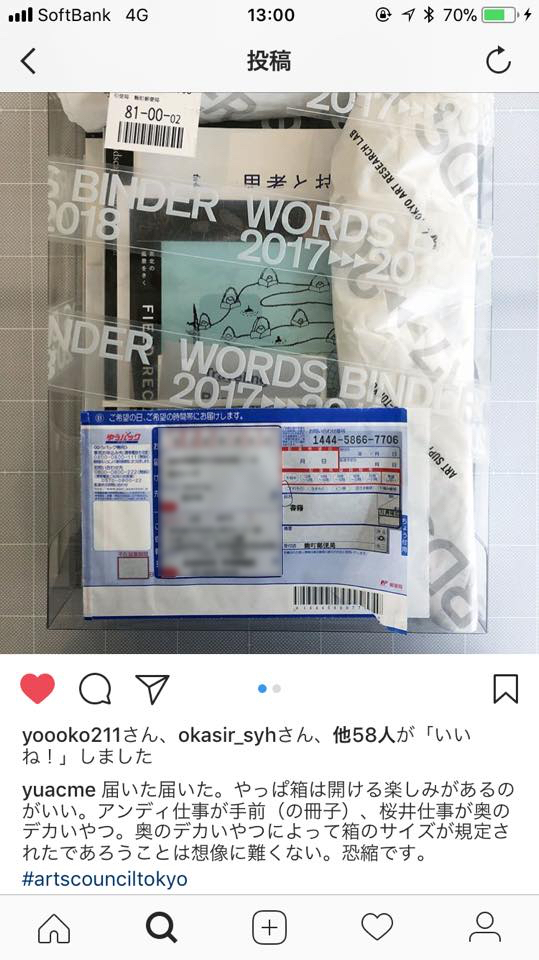日本に暮らす『移民』の若者たちの人材育成を目指すプロジェクト「Betweens Passport Initiative」。様々な可能性を秘めつつも、光が当てられる機会の少ない彼らの力。その価値を広げようと、このプロジェクトでは定時制高校での放課後プログラムや、学校の外にいる『移民』の若者たちに関するリサーチを通じて、若者たちを社会とつなぐコミュニティづくりが進められています。
なかでも、取り組みを行ううえで重視しているのが、若者の多様性を育てる仕組みづくり。持続的にこの場所に関わるためのインターンシップなど、プロジェクトを運営する一般社団法人kuriyaの海老原周子さんが、その重要性を感じた経験とは? 現在進行形の試みについて、伴走する東京アートポイント計画プログラムオフィサーの佐藤李青とともに訊きます。
>〈前篇〉「『移民』の若者のエンパワメントのために、アートプロジェクトができること—海老原周子「Betweens Passport Initiative」インタビュー」
定時制高校に「現場」をつくる
——2年間の活動のなかでBPIが継続して行っているのが、千代田区にある都立定時制一橋高等学校に週2回通い展開している放課後プログラムです。
海老原 :もともと、この学校には外国籍などの高校生たちの支援に長らく取り組んできた角田仁先生という方がおり、多様な高校生たちが集まる多言語交流部「One World」を始められていました。ちょうど私もドロップアウト率の高い定時制高校の現場を知りたいと思っていて、2015年9月に、学校に通わせてもらうことから始めました。そこで、BPIのパートナーでもある徳永智子さんと知り合いました。彼女は慶應義塾大学国際センターで教鞭を執られていたので、その授業を履修する留学生たちにサービスラーニングという形で部活動に参加してもらい、共に部活動をつくってきました。参加しているのはフィリピンを中心にした東南アジアの子たちで、インドや日本の子も来ています。
——現場ではどのようなことをされているのでしょうか?
海老原 :演劇のワークショップなどの始めに自己紹介を兼ねてよく使われるアイスブレイキングから始まり、例えば、言葉を使わない伝言ゲームやお互いの文化を紹介することなど、様々なアクティビティを通じてまずは関係性をつくることを大事にしています。そうすると、例えば、高校生にとってはその学校に通うことが楽しくなる状況をつくることが必要だなとか、大事なことが見えてきます。
——まずはユースとの関係性をつくることに時間をかけたんですね。
佐藤 :実際、海老原さんはBPIを始めたとき、3年ほどこうした活動を続けないと関係性もできないし、プロジェクトを始めることもできないとおっしゃっていましたね。
海老原 :こちらがやりたいアートプロジェクトを押し付けるのではなく、まずはその場に身を置くことが礼儀だと思っています。ブリッジの話ともつながりますが、最近、アートプロジェクトでも社会包摂が語られるようになってきました。その対象には『移民』以外にも、LGBTや障害者など様々な人がいますよね。ただ、すでに福祉や制度が整い包摂する先があるならばまだしも、『移民』は、福祉や支援の政策も制度もまだ整備されていない分野です。私たちが東京アートポイント計画の事業としてアートプロジェクトをやる意義は、これからの社会に必要なソフト面でのインフラをつくるようなもっと長い視野を持ったことなのではと感じています。そのためにも、いきなりアートを持ち込んで何かをしようとするよりも、相手にどんなニーズがあるかを現実に知らないとプロジェクトとして動けないと思ったんです。
佐藤 :例えば社会福祉など制度に支えられた施設に行けば人が集まっていて、現場が見えることにより支援もしやすい。だけど、『移民』の場合は、そもそも社会的にも集まった状態で見えるかたちになっていないから、何が必要かという言語化も進んでいないと。
海老原 :他のマイノリティと比べて、包摂する先がまだなく、『移民』の若者が集まる場すらない段階では、まずは、その「現場」をつくることから始めないといけないし、それには3年くらいはかかるだろうと考えていました。なので定時制高校では放課後の部活動という形で、多様な高校生たちが集まることのできる「場」をつくりました。次に、学校でもない家でもない、若者たちが集える第3の「場」としてインターンシップをつくっていくことをこの2年間ではやってきたのだと思います。
Betweens Passport Initiative インターン活動の様子。 リサーチを通して、ユースが変わった
——定時制高校での活動と並行して、BPIではこれまで、アーティストのOkui Lalaさんや武田力さんと協働してユースとの新たな出会いを模索するリサーチプログラムも行ってきました。
海老原 :定時制高校は学校内のコミュニティですが、BPIにおける「ユース」は、16才から26才を対象年齢としています。そのなかには、すでに高校を卒業した18才以上の子やドロップアウトした子、あるいは20代で来日した子もいます。こうした子は本当に見えづらい状況にいます。彼らはどこにいて、どのように出会うことができるのかという課題があったんです。
佐藤 :そのような状況のリサーチと、出会いの仕組みをつくる必要があるんだろうと。武田さんはフィリピンなどアジアでも活動を展開していますが、地域に入り、人との出会いから作品のフォーマットそのものをつくるアーティストです。話を伺うと日本の移民への関心もあった。それで最初は、フィリピンコミュニティの人が多い定時制高校の活動に参加してもらおうと思いました。でも実際に動き始めてみると、むしろコミュニティの枠から外に出る動きをしてもらう方がいいんじゃないかと、課題だったリサーチをお願いすることになりました。
——いわば、野に放ったわけですね。リサーチとは、具体的には?
海老原 :東京のなかの多文化を巡るリサーチとして、インターンをしているユースに自文化の案内者になってもらいました。武田さんが独自に行っているリサーチに加えて、例えば大久保の路地裏やフィリピンの食材店などの情報を持っているユースと知り合い、助けてもらう。そこからこれまでは掘り起こされていない、新しいユースとの出会いができるのではないかと期待しました。何かをつくるときというのは、結果的に誰かが巻き込まれやすい状況ができるものだと思うんです。
Betweens Passport Initiativeでは、アーティスト・武田力さんとユースが協働し、東京都内の多文化の現場をリサーチした。 海老原 :アーティストと関わることで、案内役のユースにも変化がありました。ちょうど今日、武田さんも含めて錦糸町や高田馬場をみんなで回ったんですけど、関係性が変わるんです。今日もユースたちは、案内のために入念な準備をして、私たちには辿り着けないようなフィリピンのレストランに連れて行ってくれました。
——そこではむしろ海老原さんたちが教わる側になるわけですね。
海老原 :例えば、支援という枠組みでは、どうしても支援者と被支援者という固定された上下関係にあります。でも、リサーチでは、「弱者」になってしまいがちな彼らの持つ価値が転換される。水平でフラットな関係性や、上下関係自体が反転したりする状態をアートプロジェクトではつくりやすい。関係性すらも多様なコミュニティでの経験は、ユースにとって「自分にも何かができるんだ」と実感する場でもあり、エンパワメントの機会になると思っています。
ユースの関わり方は様々。企画や制作を手がけることもあれば、通訳として間に立つこともある。プロジェクトを通じて、それぞれが自分の持つ「多文化」や個性の活かし方に気づくことを目指す。(「Moving Stories / Youth Creative Workshop アジア間国際プラットフォーム形成ー多文化な若者達へのアートを通じた人材育成プロジェクト」) 何かを変えるための包摂とは?
――海老原さんは通訳者としても活動していて、BPIの外でも、『移民』の問題を扱った日本のアートの現場に多く立ち会っているかと思います。その中で、移民の取り上げられ方について疑問に思うことや、理解が進んでいないと感じることはありますか?
海老原 :最近はもう、いろいろな怒りも通り過ぎてしまって……。
佐藤 :(笑)よく怒っていましたよね。『移民』に関する仕事が増えたのは最近ですか?
海老原 :ここ2年ほどで増えたと感じます。「アートと移民」というと、アーティストが自主的に作品で取り上げる場合と、高まる「社会包摂」の流れのひとつとして主催者側が事業や企画に盛り込もうとする場合がありますよね。前者については、私が言えることは何もないです。作品化することで結果的に搾取になるケースもありますが、それはアーティストの自由であると同時に、自由の対価として責任も引き受けるのかは、その人次第だと思っています。一方、後者の社会包摂の取り組みには、何のためにやるのかよくわからないと感じるものもあります。なぜそれをやるの?やったことでどうしたいの?と。
――ある種、「マイノリティに優しい」という大義名分が先行してしまっている?
海老原 :実績づくりを目的に実施する、ということですね。私たちがいただくお問い合わせの中には、こんなプログラムをやりたいからユースに参加してもらえないかと、キャスト会社のような扱いを受けるものもあります。でも、多様な人が参加する強みは、様々な視点を通して従来の仕組みの機能していない部分が見えたり、新しい枠の必要性がわかること。ただ既存の枠組みにはめ込んで、「包摂」と言うだけでは何も変わらないのではと思います。
佐藤 :本当に何かを変えるための包摂というより、言い方は悪いけれど、ただの「トピック」として扱ってしまうものもある。その前提の違いは、大きな問題ですよね。
——一方でその話題は、BPIがなぜ「アートプロジェクト」かという問いにもつながると思います。海老原さんはアートとしての良さ以前に、実際の人の状況が変わることをとても大事にされている。アートか人か、その天秤についてはどう考えていますか?
海老原 :アートをツールとして使うか、ということですよね。そこはすごく悩んできた部分ですが、おそらくそのどちらでもありません。よく誤解されるのですが、私たちは福祉団体でも支援団体でもありません。kuriyaは人材育成の団体としてアートプロジェクトに価値を見出しています。というのも、アートプロジェクトは言語化しづらい部分もありますし、短期的に何か問題を解決するわけでもないと思っています。ただ長期的な視点では、社会を豊かにする何かをつくるものだと信じています。ともすれば必要ないとみえるものかもしれないけど、人の人生にその体験があるかないかの差はすごく大事だと。
——海老原さんが、その大切さを感じた経験というと何ですか?
海老原 :子供の時からアートに救われて来ました。日本で通ったアトリエもそうですし、イギリスでも演劇やアートが身近にあった。それらが別に何かをしてくれるわけではないけど、『外国人』として育つなかで、人との違いやいろんな観点を持っても良いんだよという蓄積があったからこそ今の自分があります。そうした場所を、いまの日本にもつくりたいんです。
ワークショップで制作した自分たちの映像を観るユースたち。(「Moving Stories / Youth Creative Workshop アジア間国際プラットフォーム形成ー多文化な若者達へのアートを通じた人材育成プロジェクト」) 埋もれていた価値を見つけ、物語を伝えていく
——現在、BPIにはインターン生が5人、また過去のメンバーなども含めて20人ほどのユースが関わっているそうですね。彼らとは普段、どのような時間を過ごしているのですか?
海老原 :お茶を飲んだり、ゆで卵の茹で方を教えたり、進学の相談に乗ったり……。ただ一緒の時間を過ごしているように見えて、フラットに話せる関係性の大人と知り合えることが、アートプロジェクトだからこそ築けるセーフティネットのように思うのです。私たちは結局、支援団体ではないので、具体的な何かをしてあげることはできません。支援や福祉と近い領域のアートプロジェクトには、その一線を越えないように堪えるものも多いですが、私たちはあえてそのラインを越境して、従来とは異なるかたちの網を張ることをしたいと思っています。
——支援や福祉の領域にはない、新しい関係性の紡ぎ方をしていきたいと。
海老原 :はい、それと同時に、そこで語られる小さな物語を、社会に伝えていくことで、大きな仕組みをつくれたらと思っています。第一回目の東京オリンピックが道路や建物といったハード面での社会インフラ整備のきっかけになったのに対して、第二回目となる2年後の東京オリンピックに向けて、教育や福祉といったソフト面での社会のインフラ整備が必要なのではないかと個人的に感じています。とくに断絶されてしまった関係性をつなぐ時にアートプロジェクトが有効なのではないかと。BPIを始めたときに「現場」と「ツール」と「物語」が必要だと思っていました。1年目は定時制高校という現場を、2年目はインターンというツールを、3年目は、彼らがここでどんな成長をして、どう巣立って行くのか、その物語を、未来の仕組みづくりのために伝えていきたい。
「Moving Stories / Youth Creative Workshop アジア間国際プラットフォーム形成ー多文化な若者達へのアートを通じた人材育成プロジェクト」 ——移民というと、これまで支援や研究の「対象」になりがちでしたが、今後、彼らが自ら文化の発信者として、日本で大きな存在感を持つことも十分に考えられますよね。
海老原 :実はそういう動きは、すでに起きつつあります。メンバーとして関わってくれているAvinash Ghaleは高校を卒業してからネパールより来日しました。彼がインターンプログラムの一環として、ビデオのワークショップをやったことをきっかけに、映像作品を撮りたいと思っていた若者たちが集まり、仲間を集めてYouTubeチャンネルを始めています。週一回継続的に集まり続けていて、規模も大きくしながら、自身で発信を行っています。ユースと私たちも、ずっと一緒にいられるわけではないなかで、私たちが彼らの物語を語るのではなく、どんどん自分たちで語れる力をつけられるようになるといいなと思います。
佐藤 :今日語ってきたプロジェクトの「準備」が整う中で、BPIは、本当にこれから何をしていくのかがとても大切になると思うんです。海老原さんとユースの付き合いの切実さと共に、これからの実践によって、その真価が問われるのだと思います。ユースが関わる土壌ができたうえで、彼らがどう変わったのか、どんな新しいユースと出会えたのかが、重要だろうと思います。
海老原 :人口減少を迎える日本において、BPIの取り組みは、多文化社会を迎える東京の未来をつくることでもあると思っています。以前、あるインターン生が「日本に来て初めて、自分にも何かできるんだと感じた。この活動がなかったら、自分が日本で何か役に立てるとは思っていなかった。でも、このプロジェクトがあったから、人とは違う自分だからできることがあると、自分の強みがわかった」と言われたんです。BPIには『移民』の若者のみならず日本人の若者も参加しています。そして例えば子育てが一段落したお母さんなども即戦力として関わってくれています。これまで社会に埋もれていた人的資源を見つけて、活躍の機会を提供することで新しい人材を育てるアートプロジェクト。そんな指標を大切にしながら、今後も活動を展開していきたいです。
「Moving Stories / Youth Creative Workshop アジア間国際プラットフォーム形成ー多文化な若者達へのアートを通じた人材育成プロジェクト」 Profile
海老原周子(えびはら・しゅうこ)
一般社団法人kuriya代表、通訳
一般社団法人kuriya
kuriyaは、『移民』の若者たち=未来の可能性と捉え、自らの手で未来を切り開く人材を発掘・育成しています。東京をベースに『移民』の若者たちをはじめとする多様な人たちが集うインターカルチャーな場をつくり、それぞれの持つ知識やスキルを共有し学び合いながらアートプロジェクトを行うことで、彼らに生きる糧やライフスキルを身につける機会を創出します。
Betweens Passport Initiative
『移民』の若者たちを異なる文化をつなぐ社会的資源と捉え、アートプロジェクトを通じた若者たちのエンパワメントを目的とするプロジェクトです。人材育成事業として『移民』の若者たちがプロジェクトの運営を共に行います。https://medium.com/betweens-passport-initiative