アートプロジェクトの担い手を訪ねて話を聞いてきた、インタビューシリーズ。今回はその第11回の節目に、P3 art and environment統括ディレクターで、2011年より東京アートポイント計画の外部評価委員を務める芹沢高志さんをゲストに迎えました。
帯広や別府、さいたまなど、地域で行われる数々のプロジェクトに携わり、しなやかな手法でアートの可能性を開いてきた芹沢さん。そんな芹沢さんは、文化のあり方が足元から揺らぐコロナ禍の現在を、個人が文化芸術に関わる上での拠り所となるような根源を、一度立ち止まって振り返る絶好の好機だと語ります。また、その危機の時代に臨むにあたっては、関係者が立場を超えてともに学び合う関係性や、「たまたま」の潜在力に賭ける行動が重要だと指摘し、それを、生物の進化やこれまでの自身の経験も例に挙げながら話します。
「アートとは、人生を変えるヴィジョン=まぼろしを見せてくれるもの」。そのように語る芹沢さんが、いま、アートプロジェクトに関わる人たちに届けたい言葉とは何か? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司との対談を通して、耳を傾けます。
(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫)
>危機の時代に求められる「共進化的な姿勢」。これからのアートマネジメントに向けて——芹沢高志×森司対談〈後篇〉

「たまたま」が作る、文化の足場としての「大地」
森:今日の対談にあたり、芹沢さんの新刊『別府』を読みました。そこで感じたのは、この対談のテーマは「大地」ではないかということです。コロナ禍で文化活動の土台が揺らいでいるいま、文化に関わる人には、自分の原点を振り返ることが求められている気がします。自分はなぜ文化に携わっているのか。後から得た知識ではなく、自身の背骨となっている体験とは何か。そうした振り返りが重要になる。芹沢さんの文章からは、そうした物事の起点であり、世界を見る上での足場となるような「大地」の存在を感じます。普段はなかなか聞けない、ご自身の原点についてのお話から、お聞きできますでしょうか?
芹沢:「大地」と言ってもらえるのは嬉しいです。おっしゃるとおり、コロナ禍は根源的なところに立ち戻って、自身を振り返る好機だと思います。普段は自分の奥にあって表に出てこないもの、しかし視点の核となるもの、そうした大地的なものがあると、未知の事態に対峙してもオロオロしない。僕の場合、出自はアートではなく、環境計画や学生時代のさまざまな文化体験で、それが物事を見る上での起点になっているのは確かです。
僕が大学に入った1970年頃は、その前の学生運動の季節が落ち着き、環境問題が囁かれ始めた頃でした。神戸大学で数学を学ぶ前、東京で浪人をしていたのですが、そのときにたまたま見たのが、東京都美術館で70年に開催された第10回日本国際美術展、通称「東京ビエンナーレ」でした。うちの親父は新聞社にいて、タダ券をもらったんですね。それでなんとなく見にいったら、衝撃でひっくり返ってしまった。とくに、地下の彫刻室にあったクリストの《床の包装》という作品。なんだこれは、と。芸術といえば、まだ絵や彫刻という時代。アートってすごいんだと強烈に思った体験です。ほかにも、69年に代々木体育館で行われた「クロス・トーク/インターメディア」というイベントをなぜか見にいっていたり、この時期にそうしたいろんな体験をしました。
でも、それは意図的ではなく、「犬も歩けば棒に当たる」式の出会いでした。思えば高校時代からそうで、周りに大島渚の映画に関わっていたり、ローリング・ストーンズに入れてもらおうとロンドンに行った奴とか(笑)、面白い友人が多かった。別に芸術を志向していたわけではないけれど、「よくわからないもの」に触れる機会が多かったんです。
森:わからないものへの耐性は昔からあったんですか? 普通、人はわからないものは嫌がりますよね。
芹沢:僕は大丈夫でした。僕は政治運動のあのスタイルに乗れなかった。その代わりにアート的なものがあったんだと思います。当時の新宿は、伊勢丹くらいまでがエスタブリッシュされた都市で、その奥は何が起きるかわからない「魑魅魍魎」みたいなエリアでした。唐十郎さんの「紅テント」があったり、サイケのお店があったり。街を歩くと、そうしたものと「たまたま」出会う。そして、面白いものにはピンとくる匂いがありました。
時代全体が、微熱状態だったと思います。世代の近い相米慎二監督の『台風クラブ』という映画があるけど、まさに台風が近づいてくるソワソワ感のような、何かが起こりそうな気配がありました。将来の仕事につながるからとかではなくて、後から考えるとあれを見ていたのかというものに出会っている。偶然と必然が混じり合った出会いでした。

アートはヴィジョン=まぼろしを見せるもの
森:環境計画の道にはどのように進んだのでしょうか?
芹沢:たまたま始めた数学も面白く、大学卒業時に研究者になる道もありました。一方、アートとか、当時言われ始めた環境問題への関心もあって、建築に行けば全部がくっつくんじゃないか、と。それで先生に相談したら、当時早稲田で教えていた建築家の吉阪隆正さんを紹介してもらいました。会いにいくと、この人も変な人で、全然本題の話をしてくれない(笑)。「今日どの駅から来たの?」とか、そんな話ばかりを延々としてね。
森:当時の先生方は豊かですよね。
芹沢:いまは世知辛いですよ。効率効率で。もっといいかげんでいいじゃないかと。当時は余裕があったと思う。知らない学生が訪ねてきても、進路のノウハウなんかでなく、どうでもいい話をたくさんしてくれた。それで横浜国立大学の建築に進んだんだけど、あまり馴染めず、その頃出会ったのが環境調査や計画も行う美術家の磯辺行久さんでした。
当時の磯辺さんはアメリカから帰ったばかり。大学で講演があったので聞きにいくと、アートや建築のことを猛烈に批判していた。ほかの学生は反論するけど、僕はもう辞めるつもりだったから彼を擁護したんです。すると終了後、手招きされて「事務所に遊びにこないか」と(笑)。結果、そこで働き始めて、磯辺さんからはアメリカの環境の話をいろいろ聞きました。
森:上の世代からすると、声をかけたくなる何かがあったんでしょうね。
芹沢:自分の興味関心に正直だったんだと思います。「建築」や「数学」や「アート」や、既存のカテゴリーに惹かれたというより、よくわからないけど、後から考えるとこれだったという関心の持ち方。肩書きや門構えからは入っていなくて、街が教師というか、そこで出会ったものをわりと正直に浴びていったら、いまにつながりました。
印象的なのが、あるとき磯辺さんに「キュレーターになりなさい」と言われたこと。当時は意味がわからなかったけど、結果的に自分の行った方向性はそれに近かった。

森:「学芸員」ではなく、「キュレーター」なのが面白いです。実際、芹沢さんが2002年に帯広で手がけた「とかち国際現代アート展デメーテル」のような仕事は、すでに価値化されたものを扱う学芸員的な仕事ではない。芹沢さんの仕事は本人が土地で得た関心との応答で作られていて、まさにキュレトリアル。それは、ある地域に都市から現代美術を持ち込みインストールする、北川フラムさんや南條史生さんらのタッチとは異なります。
芹沢:以前、ある人から「デメーテルは芹沢の地域計画だ」と言われたのですが、たしかにそうだなと思います。地域を計画して、風景を変容させていく。しかも、それをパーマネントなものとして施すのではなく、一夏の夢のような、一種の幻影として見せる。
アートがヴィジョンを見せるものであることは、最近確信を持ち始めています。「ヴィジョン」といっても、近頃ビジネスや行政で使うような大袈裟な意味ではない。それは要するに「幻影」や「まぼろし」で、幻視の力です。よく使うのはシンデレラの例えです。シンデレラは継母たちにいじめられ悲しんでいる。すると魔法使いが来て、かぼちゃの馬車やガラスの靴をくれる。ただ、必ず夜中の12時には戻れ、つまり現実に帰れと忠告される。このシンデレラのまぼろしは、とても儚い。でも、一人の女性のその後の人生を決定的に変えてしまうわけです。
アーティストと仕事をすると、ここではない別の世界を目の前に現してくれます。それはいわば仮初めのまぼろしだけど、人の精神に一種の傷を与える。消えていく一時的なものだからこそ、ヴィジョンの力が発揮される。ユートピアが出入りをしないとその価値に気づけないように、儚いがゆえにヴィジョンの力が生まれるのだと思います。

生活のなかにもう一回り入ったアート
森:いまのお話は、アーティストが見せるマジックを体験したことがある人にはとても響くと思うんです。一方、そうした体験をしたことがない人にどう伝えるか。我々のように行政も含むいろんな人たちと活動をしていると、そんな問題にぶつかることもあります。
芹沢:ある大学で、アートマネジメントを学ぶ学生に「忘れ難い芸術体験は?」と尋ねたことがあります。その経験があれば、どんな苦境に立ったときもそこに戻ることができる。しかし、遠慮もあるのかもしれないけど、誰も手を挙げない。そうした体験もなく、アートと社会を結ばねばならないといってアートマネジメントをやっても、どうなのかなと思いました。
森:アートから入った人がアートじゃないものと出会い、何かを得るための回路をいかに持ちうるのか。そういう問題設定を、今後アートマネジメントに関わる世代の人たちは絶対しないといけないと思います。今日の言葉で言えば、いかに「大地」に起点を持つか。アートのなかだけでループしていると、シュリンクしてしまう。もちろん、僕や芹沢さんはそういうアートマネジメントの原罪を作ってきた面もあり、自戒も込めてですが……。
我々が行うアートプロジェクトという営みも、その価値を社会的に了解しやすい大義でのみ捉えようとする傾向があります。その傾向は近年ますます高まっていて、コロナ後は予算面も含め、さらに余裕がなくなりました。本来、社会が危機のときこそ文化の出番です。阪神・淡路大震災や東日本大震災のときは、表現者たちが一斉に動いた。いまは、出番のキュー出しは来ているけど出方のデザインができない状態で、僕自身も「待機すべき」という立場をとっています。しかし、現在の社会的、精神的な危機を見ると、数年単位ではやはり文化の出番だと思っています。
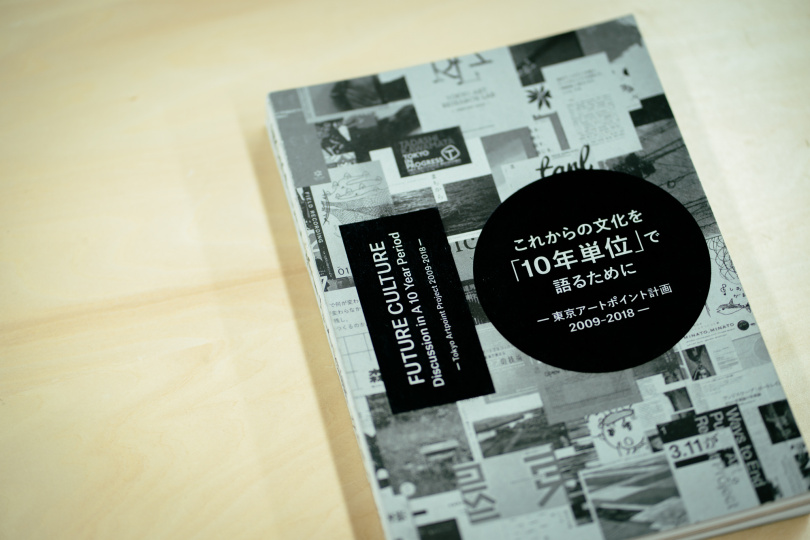
芹沢:東京アートポイント計画の当初、その意義を行政側に伝えるとき、「人材育成」という言葉が使われていました。僕は、これは良いと思ったんです。つまり、一種の教育であり、東京オリンピック・パラリンピックが終わったら不要になるものではない、と。
実際にこの活動は、そこで育ったプログラムオフィサーに支えられている。また、参加する市民のなかに、先ほど話したようなアート体験を持たない人がいたとしても、それは何かの事情でたまたま出会っていなかっただけかもしれない。そうした人に、出会いの環境を提供することで、もともと個人のなかにあったものが花開くかもしれません。
僕は「ライブラリーエンジェル」という言葉が好きです。図書館で探していたわけではない本にふと目が行き、天使に囁かれたように手に取ってしまう。そういう、偶然の出会いの価値を感知するレッスンは、社会の速度が変わったいまこそできる面もあります。
森:そのとき、今後はアートがもう一回り深く生活のなかに入っていかないといけないのかなと思います。芹沢さんの言葉を借りれば、従来はいわば「ピンポンダッシュ」みたいな幻視だった。突然ピンポンと来て、また日常に帰っていく。では、より日常にアートが入ったあり方があるなら、そこで求められるアートプロジェクトの姿とは何なのか。
ここで重要なのは、我々が「支援」の立場から離れることかもしれません。実際、誰も対処の仕方を知らないこのコロナ禍は、我々の経験値を無力化し、良い意味で僕たち従来の支援者側と、被支援者だった共催団体との関係を対等にしました。これまでのマネジメント手法が機能しないという前提に立って、我々が伝えるのではなく、さまざまな立場の人たちと一緒に考える。つまり、「支援」から「協働」へ。そういうインクルーシブなアプローチが、アートシーンではなく生活シーンで求められているのがいまだと思います。
>危機の時代に求められる「共進化的な姿勢」。これからのアートマネジメントに向けて——芹沢高志×森司対談〈後篇〉へ

Profile
芹沢高志(せりざわ・たかし)
P3 art and environment 統括ディレクター
1951年東京生まれ。神戸大学数学科、横浜国立大学建築学科を卒業後、(株)リジオナル・プランニング・チームで生態学的土地利用計画の研究に従事。その後、東京・四谷の禅寺、東長寺の新伽藍建設計画に参加したことから、89年にP3 art and environment を開設。99年までは東長寺境内地下の講堂をベースに、その後は場所を特定せずに、さまざまなアート、環境関係のプロジェクトを展開している。とかち国際現代アート展『デメーテル』総合ディレクター(2002)、横浜トリエンナーレ2005キュレーター、別府現代芸術フェスティバル『混浴温泉世界』総合ディレクター(2009、2012、2015)。さいたまトリエンナーレ2016ディレクター。著書に『別府』(ABI+P3)、訳書にバックミンスター・フラー『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫)など。