
“災間文化研究”のはじまりに寄せて(佐藤李青)
執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28

災禍の現場に立つには、いったい、どんな態度や技術、方法がありうるのか? 災害復興の現場に多様なかかわりかたをしてきたゲストに話を伺うディスカッションシリーズの第1回目回は、ナビゲーターの佐藤李青(アーツカウンシル東京 プログラムオフィサー)、高森順子(愛知淑徳大学助教/阪神大震災を記録しつづける会事務局長)、宮本匠(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科准教授)が話題提供し、3人がそれぞれ関わってきた現場を通して得られた視点を共有し、イントロダクションとしました。このレポートでは、3人の報告と議論のエッセンスをまとめました。
Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業/ASTT)の立ち上げから、まとめに到るまでプログラムオフィサー(中間支援)としての役割から見てきたことを報告。まちなかでアートプロジェクトを展開する東京アートポイント計画の事業スキームを使い、東京から東北へアートによる支援のあり方を探ってきた。ASTTでの10年のかかわりは、次の3つの問いにかかわることだった。
(1)アートに何ができるか?
これは外から問いかけられることもあったし、自問自答でもあった。初動でよく問われていたものだった。この問いの「できる」ということについて、時間軸を長く考える必要がある。関係をつくっていくことで時間をかけて「できる」ようになることがある。表現によって、状況に応答するスピードとタイミングがある。水戸芸術館のキュレーターである竹久侑さんは、「3.11とアーティスト:進行形の記録」という展覧会の図録において、阪神・淡路大震災と異なり、東日本大震災では「市民」を対象にするアーティストの実践があり、それは「市民による参加をベースとして行われる、プロセスを重視した芸術活動」であるアートプロジェクトの影響があることを指摘している(別の論考で竹久さんは美術作品が「もの」から「こと」へ変化し、「ひと」を対象とする活動が現れてきたという言い方もしている)。これはASTTの動きとも重なっている。
(2)外からかかわる意義とはなんだろうか?
震災から6年目に、私たちアーツカウンシル東京を主語にした初めての記録を作成した。そのインタビュー集『6年目の風景をきく』では、ASTTで取り組んできた中間支援としてのふるまい(対話)の構造を、インタビューとコラムを交互に入れることで冊子化した。冊子をつくることで、取材という切り口から関係づくりができる。自分たちが地域内外のメディアになる。2017年に発刊したジャーナル『FIELD RECORDING』では、それを自覚的に展開した。それが、外からさまざまな境界線/関係性を混ぜることを促すのではないかと考えた。
(3)10年目の「節目」をどう使うのか?
2020年6月から「震災後の経験を未来に伝えるメディア」としてウェブサイト 『Art Support Tohoku-Tokyo 2011→2021』を運営し、10年という「節目」の使い方を考えた。「コロナ以前」の計画では、東北の担い手のネットワークづくりや、東京でのフォーラムによる情報発信、そしてそれらのアーカイブを予定していた。コロナ後、対面での出会いづくりや遠距離移動が困難となり、目的はずらさずに、活動をオンラインにシフトすることにした。10年で得られた関係性を生かし、「節目」を外から「使う」ことで、ふだん震災に対して強い関心を持たない人に「関わりしろ」をつくる=より広く「当事者」を増やすことを目指した。
振り返って思うのは、「被災地支援」という目標のある事業で「めざす」ことにかかわったから、「すごす」ことができたということ(「めざす」と「すごす」は後述する宮本の報告に詳しい)。それは目の前の「ひと」と向き合うアートを介したものだったことも大きい。いま、「めざす」事業がなくなって考えるのは、この10年のまなざしを他の経験、他の人とのかかわりにつなげること。「被災地のリレー」をいかに生み出すか。
阪神・淡路大震災を経験し、それを手記として書いてきた人々(阪神大震災を記録しつづける会)と、震災から15年目(2010年)からかかわり始めた。活動の初動にはいない、遅れてやってきた高森が執筆者と取り組んできた実践のうち、記録を本にまとめる活動を2つ紹介し、さらに、その経験が生きた実践として、他の活動の記録をひとつ紹介した。
(1) 阪神大震災を記録しつづける会(編)『阪神・淡路大震災 わたしたちの20年目』, 2015年
(2) 阪神大震災を記録しつづける会(編)『筆跡をきく 手記執筆者のはなし』, 2020年
(3) あいちトリエンナーレ実行委員会(編)『あいちトリエンナーレ2019ラーニング記録集』「アート・プレイグラウンド はなす TALK」受け手ノート──8月18日から最終日までの58日間に及ぶ「対話」のアーカイブ」, 2020年, pp.61-84.
3つの「本を作る」実践で得られたことは、まず、本にまとめるということは、実践の「後始末」ではないということ。本にまとめることこそが実践。本にしていく過程で、活動の「別の見え」が現れる。本にするきっかけとして、それがどんな「見え」かはわからないが、「別の見え」があることは予期している。20年目の手記集は、「もう一度、10年ぶり、20年目に手記を書いたらどんな経験が語られるだろうか」、25年目のインタビュー集は、「私の目の前にいる執筆者のふるまいと、執筆者が書いた手記がどうにも重ならない、執筆者も私も多面的な存在なのに、手記にはその多面の限定された部分しか現れていないのではないか」、あいちトリエンナーレの記録では「『表現の不自由展・その後』の騒動のなかで、その他大多数の展示が世間から見過ごされていること、外野の「見え」と、目の前にいるスタッフたちの声にギャップがある」という、記録することが別の見えをもたらすであろう予期があった。
言葉を本にすることは、別の誰かがそこから何かを引き取り、次につなげていくことになる。つまり、本にするという実践は、外部への回路をつくる、関係のための実践だと捉えている。そして、それは編集する者―掲載される者という内部の関係のための実践でもある。言葉が編集され、本に載るというのは、「確かに私の言葉を受け取ってくれた」ということを喚起させる。現場をもつ実践において、「わかり合う」という感覚は必要だが、得難い。その「わかり合う」という感覚を本にする実践はもたらす可能性がある。
大学学部生の時に、新潟県中越地震(2004年)があった。現地に住み、集落支援をしたことが研究のスタート。現在、内発的な災害復興はいかに可能かを主要な関心としながら、外部支援者の役割などについて研究している。
現在は、「災後」ではなく「災間」だと言われる。これは人類の影響が自然に不可逆的な破滅的影響を与えているのだという「人新世」の議論にも重なる。現在のコロナ禍も「ポストコロナ」ではなく「インターコロナ」であると考えることが、災害という出来事と、そこにどう関わるかということを考える上での前提になる。いつから「災間」の社会になったかを紐解けば、1995年の阪神・淡路大震災であろう。これ以降、毎年のように災害が起こっている。また、各種社会指標も右肩下がりの分岐点となっている。ここで参考になるのは「戦間」(第一次世界大戦から第二次世界大戦までの間:1919〜1939)。「戦間」は、「災間」と違い、「間」であった意識はなく、当時の人々にとっては「戦後」だった。共通なのは、終戦というかたちで一時的なユートピアを迎え、そこから恐慌、混沌へというプロセス。「戦間」期の思想家アントニオ・グラムシは、時代の空白期には多くの病的な兆候が現れるという。それは、「災間」にも重ねて捉えられるのではないか。
哲学者スラヴォイ・ジジェクは、エリザベス・キュブラー=ロスの「死の受容」の五段階を、個人から、社会に拡張して捉えなおし、パンデミックの「受容」に至ってはいない社会において、「否認」「怒り」「取引」「抑圧」という病的兆候があるという。宮本は、この、「受容」への回路をつくることのなかに、「災間」の社会を生きる術(すべ/アート)があるのではないかと考えている。
その病的兆候のなかで注目しているのは、社会資源が縮小する中で災害が頻発することで生じる2つの主体の危機。ひとつは被災地で生じる主体の危機。眼前の課題があまりに大きいときに、人は自分にできることはもう何もないと諦め感や無力感をもつようになる。そこで「より良い状態をめざす」支援をしても、支援をすればするほどむしろ問題を大きくしてしまう。これは、「よりよい状態をめざす」ことが暗黙の裡に「現在を否定」しているため、支援がむしろ当事者の無力感を強めてしまうことで起きてしまう。このような「より良い状態をめざす」支援のかかわりを「めざす」かかわりとすると、「めざす」かかわりがうまくいかないときは、むしろ「変わらないこと」を前提とし、相手の現在のかけがえのなさを肯定する「すごす」かかわりが主体の回復に有効である。
もうひとつの主体の危機は社会全体で生じる。社会資源が縮小する中で災害が頻発し続けると人々がそもそも被災という事実を「見なかったことにする」「集合的否認」が起きるようになる。とはいえ、被災した人を前に見なかったことにするのは容易ではない。そこで「集合的否認」を貫徹するために、採用されるロジックが「悪しき両論併記」だ。これは、本来、同じ土俵で比べてはいけないことを、対等に並べることで、結局のところ問題を見ないで済むようにさせることだ。このような社会に、まだかすかな希望があるとすれば、「見なかったこと」にしたいということは、「他人事ではない」と感じているということ。苦しい経験をしている人たちに、社会がまだ当事者性をもっているということだ。この当事者性をいかに喚起できるかが、災間の「受容」の鍵だろう。現実を他の視点で見せるアートには、この「集合的否認」と「悪しき両論併記」から抜け出し、「集合的受容」へとつながる回路をつくるのではないか。

佐藤:これまでの3人の話を聞いて、災害復興へのかかわり方は、みなさんがイメージしているものよりバリエーションがあると思われたかもしれません。現場にいって、そこで活動するということだけでなく、そこでの話を外へと届けるメディアづくり、時間が経った後にはじめる実践、かかわり方に迷いがある人と当事者とのかかわりを生み出すような仕掛けをつくることなどが見えてきました。
また、宮本さんの話はこれからこのシリーズで考えていく上での大きな基盤になってくると思います。牧紀男さんの『災害の住宅誌』では「『災害』が発生するのは人間がそこに住んでいるからである」といい、自然現象ではなく社会現象であるといっています。今回のシリーズではアートを人の営みという社会現象にかかわる「術(すべ)」として考えていきたいと思っています。その意味で、私たちの日常である「災間」を見たいのだということが今日確認できたのが良かったです。
宮本:牧さんの議論でいうと、もう自然現象と社会現象は区別できない、というところまでいっているのが、いま言われている人新世の議論だと思います。いままでは、「災害は自然現象にみえるけれど、社会現象でもあるんです」という言い方をされてきたんです。ところがいま、自然現象と社会現象が区別できなくなっている。
高森さんが災害から10年、20年と経過した後でも、それを「渦中」と呼んで記録しているということと、李青さんが「これまで紹介した実践がみなさんの思っていたイメージと違ったかもしれないですね」と言ったことに補足すると、まず大きな前提として、私たちは、災害のあと、ちょっとずつ回復していくと思っているということがあると思うんです。右肩上がりの社会に生きてきた時代の私たちの前提です。街なみは少しずつ良くなっていくし、被災した方の心は少なくとも変化していく、良くなっていくだろうと。ただ、それは決してそうではないんです。そういうこととどう折り合いをつけていくかということの一つが、高森さんが震災から26年経っても、手記を書いた人たちとかかわって言葉を編み出しているということなんじゃないかと。
そう考えると、「災後」の社会であれば、李青さんのいうように「節目」を使って、みんなで「あれから何年経ったね」とふりかえり、ちょっとずつ「当事者」という枠を広げていくことができる。ただ、「災間」はそうはいかない。災害が多発しているので、一人ひとりにとっては大きな節目だけれども、それがかつてのように社会全体で「節目」として共有されないですよね。外からの回路が生まれにくくなっています。だからこそ、コミュニケーションを増やしていくことが大切なんだと思います。
佐藤:社会は右肩上がりに成長していくのだ、というような大きな前提が変わると、いろんな言葉の概念自体が揺らぎますね。「節目」が「節目」でなくなっていく。宮本さんのいう「集合的否認」のように、どうしようもないから目を背けたいし、ただ、どうしようもないということだけは皆がわかっている。ASTTは復興支援をするというそれこそ「めざす」事業をしていて、ただ、現場で起こっていたことは「すごす」ことだったと言いましたが、そこでは、つねに固有名でのかかわりをアーティストはつくっていたと思います。つねに「この人とやろう」、「この人とかかわりたい」というのがあった。そう考えると、人と人との関係を切り結ぶ上で、固有名に戻すということは重要だと思います。「どうしようもない」と大きな変化を見出せないようなときに、目の前の具体的な変化をおよぼす現場をつくるというのが、術(すべ)としてあるんじゃないかと改めて思いました。
佐藤:10年目にASTTでの出来事を本にまとめました(『震災後、地図を片手に歩きはじめる』)。事業をはじめたときから、いろんな人に「ちゃんと記録は残しておいたほうがいいよ」といわれてきました。「振り返るためにも、これから同じことで悩む人のために……」と、その意義はわかるのですが、無理なんですよね。記録のためとはいえ、言葉にする、というのがなかなか難しい。
それで写真を撮ることはしていたんです。とにかく、きれいでもない、会議室の様子でもなんでもいいから、写真を撮って、それをGoogleフォトで日付と地名を入れたアルバムにしていました。その写真を見ると、そのときの感覚を思い出せるんです。震災から何年か経って、ブログなんかにASTTのことを書くときは、写真を使って思い出したエピソードを書いてました。そのエピソードを集めたようなものが、10年目につくった本でした。
何かを振り返るときに、後から総括は難しい。点で残しておいて、その点を集めることで結果的に総体を伝えるものにできないだろうかと、ぼんやり考えてました。断片を残すというやり方、というんでしょうか。
宮本:脱線するかもしれないですが、よく記録を残すというときに、ホワイトボードを撮っておくとか、議事録を残すとかがあるけれど、その日食べたものを見れば「あ、そういえばこんなことしてたな」と思い出すことができると思うんです。あれってよくよく考えると不思議で、食べたものを思い出すことで、あの日あんなことあったな、と記録に書かれていないことまで思い出せるという効率的なやり方ですよね。現実を直接記録していくというアーカイブのやり方じゃなくって、現実を変化球で、それこそアートなりを通して象徴的な断片を取り出すことで、かえって全体を効率的にアーカイブしていくことにつながるのかもしれない。食べたものを思い出せばその日のことが思い出せるというのは僕の特殊な能力かもしれませんが(笑)。そういうやり方はあっていいと思いますね。
高森:「食べる」ということは、自分の意思なるものが介在しきれないところがありますよね。「今日カレー食べるぞ」と思っていても、お昼はなぜか蕎麦を食べていたりする。そういういろんな変遷を経て、食べるということがあると思うんです。だからその日のことが思い出せる、ということがあるのかもしれないです。
現実を記録するということを考えると、思い出すことがあるんです。「あいちトリエンナーレ2019」では、ラーニングチームにゲストとして入らせてもらって、トークイベントのファシリテーションをすることになっていました。8月1日にスタートして、8月3日に「表現の不自由展・その後」の公開が中止されて、爆破予告も来るようになっていた。そういう状況をアーカイブするってすごく難しかった。なぜなら、飛び交う言葉のなかにヘイトや暴力的な言葉が含まれていて、残して見せる、ということが難しいものがあったからです。
展示中止によって閉じられたドアには、有志のアーティストが置いた付箋とペンを使って、来場者が多くの言葉を書き残し、貼り出されていました。いま、この言葉の中身は見ることができないです。その理由のひとつは、暴力的な言葉が含まれているからということだと思います。不自由展の再開を願う言葉のなかに、マイノリティに対する暴言や、特定の国へのヘイトも混じっていた。そういう観客たちの言葉、芸術祭を見ようとやってきた人たちの言葉も、暴言を残すためにやってきた人たちの言葉も含めて、残さなければと思ったけれど、しかしどうやって残すのか、すごく悩んだんです。
悩んだ結果として、アーカイブの手法として考えたのが「受け手ログ」というものでした。「アート・プレイグラウンド はなす」という場所で話されたことを、スタッフの方がモノローグとして話をして、それをGoogle音声入力で文字起こしして、それを受け取った私が読みやすいように修正して、さらにそれを現場のコーディネーターが作品名等の間違いがないかチェックをして、翌日には印刷して配架していました。その配架の仕方はとてもこじんまりとしたもので、見たい人は見るけれど、見ようという気持ちのない人は気づかないようなものでした。そういう微妙な位置に置かれたんです。だからこそ、落ち着いてじっくりずっと読んでいた人もいらっしゃいました。

高森:このアーカイブは、すごくいろんな人の手が入っているんですね。記録ということを考えるとき、「手を入れる、編集をする」ことを、「修正する、改竄する」というふうに思う人がいるかもしれない。私もそう思っていたところがありました。「ありのまま」を残すことができれば一番良いのではないかと。でも、そうじゃなくて、即興的な言葉のやりとりを「手を入れる」ことでようやく見せられることがある。
この考え方は、小森はるかさんと瀬尾夏美さんの実践(『波のした、土のうえ』)にとても影響を受けています。彼女たちは、当事者の語りを、瀬尾さんが一回文章に起こして、それを小森さんが携えて当事者に渡して、校正してもらっている。「これは私の感覚と違う」とか「これは私が言ったことないけど、すごく共感する」とか、そういうやりとりを経て、文章のバージョンが変更されていく。そして、当事者が納得するバージョンができたところで、当事者自身がそれを朗読するんです。そこでの語りの「私」というのは、その当事者の方でもあり、瀬尾さんでもあり、陸前高田に住む「私たち」のひとりという「私」でもある。いろんな主体が混ざり合った一人称だと思います。それがヒントになって、今回「受け手ログ」ができて思ったのは、「手を入れる」ということにアートの萌芽があるということなんじゃないかということです。「本音」や「ありのまま」でないと隠蔽だと言われるかもしれない社会で、「手を入れる」という動作を考えたいなと思っています。
佐藤:手を入れることは、届く相手を変える所作でもありますね。例えば、瀬尾さんは目の前の人の話をきいて、それを作品にしている。瀬尾さんは手を入れ、作品化することで、その人たちでは届かないところ、もしかしたら一生出会わないかもしれない人々にパス出しをしている。そこがすごく大事だと思います。
当事者の発話をどう促すか、いかに思いに寄り添うような表現をするかという話だけでなく、その人の経験を思いがけない別のところに届けるとか、別のかたちで見せるとか、そういうことにアートの役割があるように思います。
宮本:高森さんの話から石牟礼道子さんのふるまいを思い出しました。石牟礼さんの表現方法は患者さんの話をきいて文章にするという「聞き書き」かというと、そうじゃない。彼女は患者さんに「なる」。彼女は人だけでなく、あらゆるものになる。水俣の自然にもなれる。それは彼女の感性が凄まじいということでもあるけれど、僕たちにも、石牟礼さんほどではないにしろ、「なる」という力はそなわっているんです。出会ってしまうと、ひとごとじゃないか、関係ないじゃないか、見なかったことにしよう、と思えなくなる。固有名として出会うというのは、その人に「なる」と言い換えられると思います。僕らはそういうふうに、誰かになれちゃうんです。そう考えると、その人に「なる」ことを促すという作業として、「編集」や「アート」というものがあるんじゃないかいうことがあるし、「手を入れる」というとなんらかの作為とか、修正とかそういうニュアンスを感じるけれど、そうじゃなくて、その人に「なる」ことを促すという作業なんだと考えるといいと思いますね。
佐藤:もっと感性を信頼するような残し方をしてもいいのかもしれません。その記録が自分にとっては、過去の出来事をありありと思い出すものだとして、でも自分にしかわからないものだろうと思うと、その記録を社会化すること、ひらくことに躊躇しちゃうんですよね。特に、災害のような社会的な出来事であれば、共有することの意義を先んじて考えるので、ならばすべて記録しようとか、できるだけ他の人にも役に立つようにと意気込むけれど、それはとても重たい作業になってしまう。
自分にしかわからないメモだけれども、これを見れば私は思い出せる。そういう断片があれば、また語り始めることができるし、実はそれは全く違う場所にいる、感性が重なる誰かが見たときに、強烈に思い出すことが起こるかもしれない。宮本さんのいう、その人に「なる」ということが起こりうる可能性がある。その人にしか思い出せないような断片、感性的に思い出せるところに振り切って残す、ということがあってもいいんじゃないかと思います。
高森:誰かに「なる」ということを考えるときに思うのは、かつて「阪神大震災を記録しつづける会」の執筆者の方々が、私との関係のあり方として、研究においては固有名として付き合うのではなく、なにかの集団のひとりとして付き合いたい、というようなものがあったことです。私は彼らと出会ってから5年くらい、20年目の手記集を一緒につくるまでは、なぜか私を彼らが紹介するときには、執筆者の語りの場をつくることを目標にしてやってきた人とは言われず、「高齢者の復興調査をしていて、趣味で執筆者の語りの場をつくっている人」と言われていたんです。でもそれは今思うと、出会ったばかりの人に、かけがえのない「あなた」と、固有名の関係として何かを一緒にしたい、と言われるのってすごく重いことになっていたのかもしれなくて、それで彼らは、「高齢者」という集団として、匿名としてまずはかかわりたいというのがあったのかもしれないです。
それが、手記集をつくってから、手記集をつくること、執筆者の言葉を聞くことが研究なんだと言ってもらえるようになった。25年目のインタビュー集では、手記で書かれていないこととして「いつ、どこで、どんなふうに書いていたのか」ということを、一緒になって探究して、共同研究者になった感じがしました。共同研究者って、第一筆者、第二筆者っていうふうに、固有名が論文に並びますよね。だからここでようやく、固有名の関係になったなという感じがあったんです。
東北でのアート支援では、どういう出会い方が多かったんでしょうか。
佐藤:固有名か集団か、ケースバイケースな気がしますね。ただ、高森さんの話を聞いていて思ったのは、時間をかけるということの大事さだと思います。出会い方って、何かの肩書きがなければうまく出会えないことがあるように思うんです。固有名で出会うこともあれば、何かの肩書きの関係で繋がれることもある。ただ、それが変わっていくことが必要で、そのためには時間が必要で。時間をかけたときに、固有名として出会い直すということがある。
例えばアーティストです、ということで入った方が良い場合もあるし、なんかよくわからないけど、あいつ面白いぞっていうふうに固有名で付き合っているうちに、やっていることが作品や本といった別のかたちになることで肩書きが発見されるようになるとか……。それも時間をかけたやりとりが背景があるから起こる。役割だけ、固有名だけのどちらか一方で終わらないというのが大事なのだと思います。
本日のディスカッション参加者の宮崎汐里さんからのコメントで、「自分が災害にかかわりつづけることを人に説明するとき『執着してるんだと思います』と言っていました」というものがありました。納得しつつ、逆に、執着せずに、それでもかかわれるような方法はないのかなと思ったりもします。というのは、災害が起こると、いままで社会が抱えていた問題が一気に露呈する。それに初動で向き合った人の多くは、「災後」の問題ではなく、「災間」の課題として気づき、その後の日常を変えなきゃいけないと思うようになる。でも、意外と日常は早く戻ってきて、そのなかで議論を続けることに疲れてしまう。そういう、「気づいてしまった人」が日常でも執着せずにかかわりつづけるようなやり方はどうすればつくれるのか。「災後」じゃなく「日常」につなげていくということを、東日本から3年から5年くらいの時によく考えていたな、と思い出しました。
宮本:それこそ、李青さんがまさに取り組んでこられたことだと思います。僕にとっては新潟の中越っていうところが始まりでしたけれど、最初にある集落に濃くかかわって、そのとき僕が考えたのは、「この村を支援したのは宮本くんだ」ってなったら良くないと思ったんです。僕の仕事は、この村にかかわるプレイヤーを増やして、自分のように濃くかかわったんだ、という人を増やしたいと思って、そっちのほうにふりたかったし、そのためにはある程度距離を取る必要があったんです。いまのかかわり方は、一年に一回会って、あとは年賀状のやりとりで、いろんなプレイヤーの人たちの様子を見て、というような感じですね。初動のときのかかわり方と、時間が経ってからのかかわり方は違うし、得意不得意もあるでしょうし、人との相性もありますよね。宮本とはしゃべりたくもないけど、その後にきた高森なら仲良くなれそうとか。そういう意味では、李青さんのプログラムオフィサーっていう立ち位置もプレイヤーを増やすという立ち位置だったんじゃないかと思っていたんです。
佐藤:確かに、時間が経つとかかわり方って限られてくるんですよね。それは資源の問題とか、「後から参加しづらい」っていう心理的な問題とか、いろんな理由があると思うんです。今回参加いただいている方のなかでも、いままでかかわってきてはいなかったけれど、なにか関わりしろがないだろうかという方もいる。誰もがかかわる気がないわけではないんだと思うんです。ただ、時間が経った今、そのかかわり方は自然にあるわけではなくて、つくる必要があるんだと思うんです。それは、高森さんが本を作ったり、そこでやってきたことをもう一度捉え直すことでかかわりやすくなったりするんじゃないかと。なにか具体的な作業をつくるということが大事なんじゃないかと思います。
というわけで、このシリーズでは、ナビゲーターがすごくしゃべります。議論していくことがまだまだあります。私たちも結論をあらかじめ持っているわけではなく、トピックとして話すほどに、さらにトピックが生まれてしまうという状況です。こういう形で、次回以降、実践を重ねてきたゲストを交えながら議論していくことができればと思います。この議論が、参加者それぞれの方法論につながっていくのではないかという見通しを持っています。それでは次回もよろしくお願いします。
執筆:高森順子
日時:2021年7月31日(土)14:00〜17:00
場所:オンライン(Zoom)での実施

執筆者 : 佐藤李青
2022.01.28
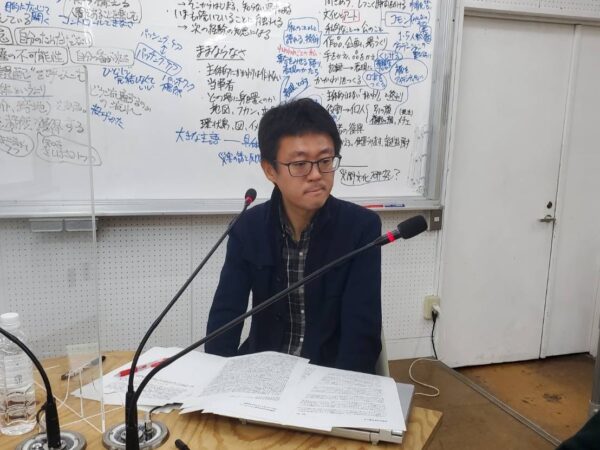
執筆者 : 宮本匠
2022.01.28

執筆者 : 高森順子
2022.01.28

執筆者 : 高森順子
2022.01.19

執筆者 : 高森順子
2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜
2021.12.28

執筆者 : 高森順子
2021.09.07