2022年度の「Tokyo Art Research Lab」のラインアップ発表!


Tokyo Art Research Lab(TARL)では、7月より、「プロジェクトのつくり方を学ぶ」、「プロジェクトの運営の方法を学ぶ」、「運営に必要な技術を学ぶ」の3つの視点で、これからのアートプロジェクトの担い手に向けたプログラムを実施します。
「新たな航路を切り開く」では、数々の現代美術展や芸術祭を手がけ、人と環境の相互作用に焦点をあてながら、社会状況に応答して発生するアートプロジェクトを見続けてきた芹沢高志をナビゲーターに、この10年のアートプロジェクトと、それを取り巻く社会状況とを振り返りながら、これからの時代のアートプロジェクトの形を考えていきます。
また、アートプロジェクトの現場に必要な実践スキルの開発やオープンソース化にも力を入れ、アートプロジェクトの運営にまつわる視点を学ぶ動画シリーズや、配信・収録技術を初歩から学ぶ講座、毎年人気のアートプロジェクトの担い手のための手話講座、ウェブサイトの価値やあり方を考える企画などを展開します。
さまざまな専門家や実践者とともに、プロジェクトの企画や運営に必要な知見やスキル、姿勢を探っていくことで、これからの時代に求められるアートプロジェクトとは何かを思考し、かたちにすることができる人材やコミュニティの育成を目指します。
「新たな航路を切り開く」

来るべきアートプロジェクトの姿を探し求める、旅としてのプロジェクト
この10年で、わたしたちを取り巻く状況はめまぐるしく変化し、それとともにアートプロジェクトの形も多様化しています。これまでの考え方では捉えられないような状況や、炙り出される新たな課題に対して、これからのアートプロジェクトはどのように応答していけるのでしょうか。
この企画では、数々の現代美術展や芸術祭を手がけ、人と環境の相互作用に焦点をあてながら、社会状況に応答して発生するアートプロジェクトを見続けてきた芹沢高志をナビゲーターに迎え、4つのプログラムを通して、この10年のアートプロジェクトと、それを取り巻く社会状況を振り返り、この10年の間に社会がどのように動き、アートプロジェクトがどのように応答してきたのかを考えていきます。
また、これからアートプロジェクトの実践者になりうる人たちとともに、これからのアートプロジェクトの形を考え、新たな時代への新しい航路を見出すことを目指します。
ナビゲーター:芹沢高志|P3 art and environment 統括ディレクター
詳細はこちら
「新たな航路を切り開く」 4つのプログラム紹介
■【研究プログラム】 年表をつくるー2011年以降のアートプロジェクトを振り返る
2011年以降に生まれたアートプロジェクトを俯瞰し、年表を制作します。ナビゲーターの視点に加え、多様な実践者達の視点も組み込みながら、社会にひらかれ、成長を遂げるものとして更新していきます。年表をつくるなかで、プロジェクト間の繋がりや、社会との関係、コミュニティとのかかわりなど、新たな分類が見えてくるはずです。
詳細はこちら
■【映像プログラム】 応答するアートプロジェクト|アートプロジェクトと社会を紐解く5つの視点
独自の視点から時代を見つめ、活動を展開している5名の実践者を招き、2011年からいまへと続くこの時代をどのように捉えているのか、これから必要となるものや心得るべきことについて伺います。またそのなかから、これからの社会状況の変化や、それに応答して発生するアートプロジェクトがどうあるべきかを議論します。この10年を大きく俯瞰し、アートプロジェクトと社会との関係を紐解きます。
詳細はこちら
■【映像プログラム】 応答するアートプロジェクト|ケーススタディ・ファイル
2011年以降に生まれた多様なアートプロジェクトを取り上げ、どのようにプロジェクトが発生し続いてきたのか、これからどこへ向かおうとしているのかを、実践者が語ります。ひとつひとつのアートプロジェクトを詳細に見ていくことで、社会状況とアートプロジェクトとの連関を捉えます。(全8回実施予定)
詳細はこちら
■【ゼミ形式プログラム】 演習|自分のアートプロジェクトをつくる
アートプロジェクトの立ち上げやディレクションに関心のある方を対象に、ゼミナール形式の演習を行います。状況に対してどのような問題意識をもち、どのようにアクションしていけるのかを、アーティストやナビゲーターとのディスカッション、参加者同士でのワークを通して深めながら、自分のアートプロジェクトを構想していきます。アートプロジェクトを構想し、立ち上げ、動かしていくための力を身につけます。
詳細はこちら
企画運営:P3 art and environment
アートプロジェクトの運営をひらく、◯◯のことば。[映像講座]
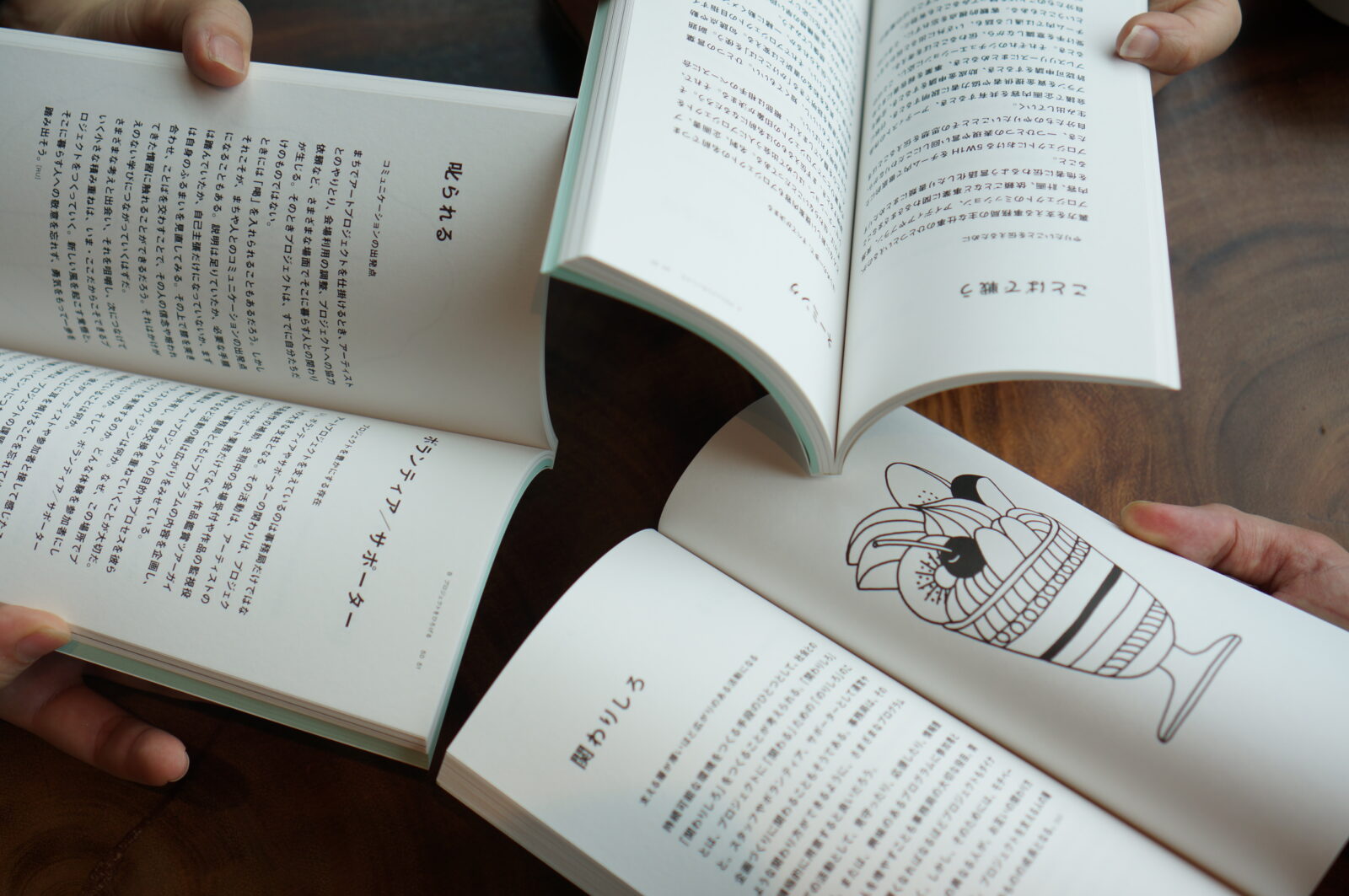
アートプロジェクトの運営を初歩から学ぶ、連続動画シリーズ
まちなかを舞台にする「アートプロジェクト」には、日々の運営にまつわるさまざまなノウハウや事業設計の方法があります。この動画シリーズでは、アートプロジェクトの中間支援を行っているアーツカウンシル東京のスタッフが、アートプロジェクトの運営に必要な視点や課題について、書籍『東京アートポイント計画が、アートプロジェクトを運営する「事務局」と話すときのことば。の本 <増補版>』からテーマを選び、紹介します。
また、アートプロジェクトの視点をさらに深堀りして、現場での実感や具体的な運営手法を学ぶ「実践編」を今秋公開予定です。
詳細はこちら
アートプロジェクトの担い手のための手話講座

ろう者と聴者のコミュニケーションについて考える講座シリーズ
日々の営みのなかで、まち・人・活動をつなぐアートプロジェクト。異なる背景をもつ人々が集い、語り合い、ともに活動をするその現場では、さまざまなコミュニケーションが交わされています。プロジェクトの場や時間をより豊かなものとしているのは、そうした多様なコミュニケーションとの出会いではないでしょうか。
本講座では、言語としての手話を学ぶだけでなく、ろう者と聴者のコミュニケーションの違いや「ろう文化」に触れ、それぞれが現場で活かせるコミュニケーション技術や、アクセシビリティへの視点を育みます。
※本講座は、3ステップで、ろう文化、手話でのコミュニケーションの基礎を体感しながら学びます。
講師:河合祐三子|俳優/手話・身体表現ワークショップ講師
手話通訳:瀬戸口裕子|手話通訳士
■ワークショップ:ろう者の感覚を知る、手話を体験する。(対面講座)
ろう者の感覚を全身を使って学び、手話を体験してみるワークショップ
詳細はこちら
■プラクティス:手話と出会う。(オンライン講座)
映像教材とオンライン講座の2つの場で、手話でのコミュニケーションの基礎を学ぶ
詳細はこちら
■コミュニケーション:手話を使い会話する。(対面講座)
講師やゲストとともに、アートプロジェクトの現場を想定した、手話でのリアルなコミュニケーションを実践できる対面講座
詳細はこちら
アートプロジェクトの担い手のための配信・収録講座

配信・収録技術を初歩から学び、これからのオンライン時代を考える、座学と基礎実践
コロナ禍を経て、アートプロジェクトの企画もオンラインシフト、あるいはオンラインと対面を混ぜたハイブリッドでの開催が日常となりました。事業計画の段階から「オンライン」を想定した企画が飛び交い、あらゆる条件における対応が求められる場面も増えています。
その一方で、急いで身につけた技術への不安や、機材や人材、外注にかけられる予算の限界、あるいは対面開催とのバランスなど、プロジェクトごとにさまざまな課題や条件を抱えていると思います。オンラインだからこそできることをこの約2年で経験しながらも、そのやり方があっているのか、ほかにどのような選択肢があるのか、今後に備えてどこまで準備をしておくべきなのか…など、改めていま、「配信・収録」に向き合うにあたって、「そもそも」を知りたいという方も多いのではないでしょうか。
全3回にわたる本講座では、マイクやカメラの仕組みなど、「配信・収録」のための基礎的な知識・技術について学び、実践するとともに、オンラインの可能性や限界を踏まえた企画制作について考えます。
講師:齋藤彰英|写真家
詳細はこちら
Webサイトの価値や在り方を考える

制作チームでウェブサイトをともに考えるためのガイドマップづくり
2021年度に実施した講座「これからの Webサイトについて考える」では、編集者、広報担当者、デザイナー、エンジニアなど、さまざまなメンバーがディスカッションを重ね、ウェブサイトの制作過程に立ち現れる7つのもやもやへの向き合い方(指針、モノサシ)をまとめ、「ウェブもやもや事典」としてインターネット上に公開しました。
本企画では、その成果をもとに、ウェブサイトをつくるための目的や手順をクライアントやデザイナー、エンジニアら制作チームで共有するためのツールを制作します。ウェブサイトをつくる際は、事業の目的を改めて見つめ、整理していく作業が必要になります。制作したツールは、進め方に悩みがちなウェブサイトの制作プロセスをひらくとともに、アートプロジェクトをはじめとした事業設計を、チームで見つめ直すためのガイドマップとしてご活用いただけるものとして公開します。
企画制作:萩原俊矢|ウェブディレクター
詳細はこちら
関連記事
- 2024.04.01 リリース
- 2023.11.15 リリース
- 2023.06.21 リリース